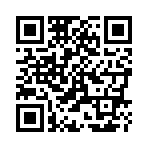2021年12月31日
三つの川の記憶 ~たかせ、なるせ、はつせ~
高瀬川、鳴瀬川、初瀬川。
これまで、三瀬という地名の由来となった三つの川を巡ってエッセイを書いてきた。
いったん今回で、三瀬村の川にまつわるエッセイは終わりにしようと思う。
ところで、第1回目のエッセイで、七十代の三瀬村の男性が、三つの川の名前を即答したのに、さすがだなと感心したということを書いた。
住民の方なので、当たり前のことだと思われたかもしれないが、試しに、ご自身の町の由来や、由来にまつわる山や川、または歴史について、簡単にでも即答できる方はどのくらいいるだろうか。
もちろん、三つの川はいまも三瀬に流れている。
国道や県道に並走する川を、普段に目にすることができるし、その流水が、米作り・果樹栽培などの農業や、蕎麦打ちなど、三瀬村での生活と密接に関わっているからこそ、当たり前のように、川の名を忘れることなんてないのだろう。
三瀬にとって、三つの川は、たかが川ではないのだから。
夏が過ぎ、秋になったころ、いつものように月に1回の会議に出席するために、三瀬支所に行った。
会議の中でも、このエッセイの話題になったので、僕は思ったことを訊いてみた。
「三つの川の名前って、三瀬の人はだれでも言えるのですか?」
「たぶん」
六十代の女性が答えてくれた。となりに座っている女性も、うん、うん、と首を縦に振った。
全員が全員というわけではないだろうが、かなりの割合で言うことができるということなのだろうか。
僕は意外に思う。
川の名前ってそんなに憶えているものだっけ?
それは子どもから大人までということだろうか?
大人だけということかもしれない。いや、小学生でも社会科の授業で地域のことを習うだろうから、小学生に聞いても答えるのだろうな。
何か、記憶を無くさない特別な秘密でもあるのだろうか?
会議が終っても、そんなことを考えながら、支所の玄関を出た。
天気のいい晩秋の午後である。
支所の横には保育園があり、ときおり子どもたちのはしゃいだ声が聴こえてくる。
目の前に、ワゴン型の小型バスが停まっている。
バスの大きさからして、佐賀市営バスや昭和バスの路線バスではなく、地域を巡回するコミュニティバスだろうと思った。
バスをよくよく見ると、
あれ? バスの側面に、
『はつせ号』
と書いてある。
あ~、そういうことだったのか。
バスの名前が川の名前なのだ。
あとで聞いたら、もう1つバスが走っていて、そっちは『なるせ・たかせ号』だという。
なるほど、三瀬に住んでいる人は、いつまでも川の名前を忘れないはずだ。
そして、地名の由来も。
11月某日。
はつせ号

なるせ・たかせ号

※バスの写真は佐賀市ホームページから
--------------------
ちなみに、僕の生まれと育ちは、多久市というところである。
多久の由来を、ネットで検索してみると、以下のようなページがあった。
以下、多久市郷土研究会(Facebook)より
奈良時代に編纂された「肥前風土記」に、「高来(たく)」の地名が出て来ます。
当時主要な所を結ぶ官道には中継地としての「駅」が置かれていました。当時九州の政治の中心であった太宰府から各地に伸びた官道にも駅が作られ馬などが常時置かれていました。
ここ高来郷の駅は、現在の多久市東多久町別府(べふ)にあったとされています。ここで官道は2つに別れ、一つは北西の笹原峠を越え厳木・相知を通って唐津へ、もうひとつは南西の馬神峠を越えて武雄市北方町へと向かっていました。
◎また、平安時代に編纂された日本最古の百科事典と言われる「和名類聚抄」(わみょうるいじゅしょう)に現在の多久の地名のことが出てきます。
そこには『小城郡高來(多久)あり、名義は古に栲木の多き處などにて負せたくるべし』とあります。この中には、「高來東郷」、「高來西郷」とあり、当時の「高來郷」には2つの郷があったものと思われます。(律令制では「国」・「郡」・「郷」の制度のもとで行政が行われていた。)
◎「栲」は「たえ」と読み、人名では「たく」と読みます。「栲」はクワ科のカジノキの樹皮をはぎ、その繊維で織った布「白栲の衣」のことで、古代の多久は、カジノキやヒメコウゾが繁茂し、白栲の衣の産地であったと思われます。
この様に、最初はこの地を『高来』と呼んでいたのです。その後、鎌倉時代に入って地名を現在の『多久』と呼ぶようになったようです。
---------------------
2021年12月15日
川浪秀之(Webプロデューサー、作家)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
これまで、三瀬という地名の由来となった三つの川を巡ってエッセイを書いてきた。
いったん今回で、三瀬村の川にまつわるエッセイは終わりにしようと思う。
ところで、第1回目のエッセイで、七十代の三瀬村の男性が、三つの川の名前を即答したのに、さすがだなと感心したということを書いた。
住民の方なので、当たり前のことだと思われたかもしれないが、試しに、ご自身の町の由来や、由来にまつわる山や川、または歴史について、簡単にでも即答できる方はどのくらいいるだろうか。
もちろん、三つの川はいまも三瀬に流れている。
国道や県道に並走する川を、普段に目にすることができるし、その流水が、米作り・果樹栽培などの農業や、蕎麦打ちなど、三瀬村での生活と密接に関わっているからこそ、当たり前のように、川の名を忘れることなんてないのだろう。
三瀬にとって、三つの川は、たかが川ではないのだから。
夏が過ぎ、秋になったころ、いつものように月に1回の会議に出席するために、三瀬支所に行った。
会議の中でも、このエッセイの話題になったので、僕は思ったことを訊いてみた。
「三つの川の名前って、三瀬の人はだれでも言えるのですか?」
「たぶん」
六十代の女性が答えてくれた。となりに座っている女性も、うん、うん、と首を縦に振った。
全員が全員というわけではないだろうが、かなりの割合で言うことができるということなのだろうか。
僕は意外に思う。
川の名前ってそんなに憶えているものだっけ?
それは子どもから大人までということだろうか?
大人だけということかもしれない。いや、小学生でも社会科の授業で地域のことを習うだろうから、小学生に聞いても答えるのだろうな。
何か、記憶を無くさない特別な秘密でもあるのだろうか?
会議が終っても、そんなことを考えながら、支所の玄関を出た。
天気のいい晩秋の午後である。
支所の横には保育園があり、ときおり子どもたちのはしゃいだ声が聴こえてくる。
目の前に、ワゴン型の小型バスが停まっている。
バスの大きさからして、佐賀市営バスや昭和バスの路線バスではなく、地域を巡回するコミュニティバスだろうと思った。
バスをよくよく見ると、
あれ? バスの側面に、
『はつせ号』
と書いてある。
あ~、そういうことだったのか。
バスの名前が川の名前なのだ。
あとで聞いたら、もう1つバスが走っていて、そっちは『なるせ・たかせ号』だという。
なるほど、三瀬に住んでいる人は、いつまでも川の名前を忘れないはずだ。
そして、地名の由来も。
11月某日。
はつせ号

なるせ・たかせ号

※バスの写真は佐賀市ホームページから
--------------------
ちなみに、僕の生まれと育ちは、多久市というところである。
多久の由来を、ネットで検索してみると、以下のようなページがあった。
以下、多久市郷土研究会(Facebook)より
奈良時代に編纂された「肥前風土記」に、「高来(たく)」の地名が出て来ます。
当時主要な所を結ぶ官道には中継地としての「駅」が置かれていました。当時九州の政治の中心であった太宰府から各地に伸びた官道にも駅が作られ馬などが常時置かれていました。
ここ高来郷の駅は、現在の多久市東多久町別府(べふ)にあったとされています。ここで官道は2つに別れ、一つは北西の笹原峠を越え厳木・相知を通って唐津へ、もうひとつは南西の馬神峠を越えて武雄市北方町へと向かっていました。
◎また、平安時代に編纂された日本最古の百科事典と言われる「和名類聚抄」(わみょうるいじゅしょう)に現在の多久の地名のことが出てきます。
そこには『小城郡高來(多久)あり、名義は古に栲木の多き處などにて負せたくるべし』とあります。この中には、「高來東郷」、「高來西郷」とあり、当時の「高來郷」には2つの郷があったものと思われます。(律令制では「国」・「郡」・「郷」の制度のもとで行政が行われていた。)
◎「栲」は「たえ」と読み、人名では「たく」と読みます。「栲」はクワ科のカジノキの樹皮をはぎ、その繊維で織った布「白栲の衣」のことで、古代の多久は、カジノキやヒメコウゾが繁茂し、白栲の衣の産地であったと思われます。
この様に、最初はこの地を『高来』と呼んでいたのです。その後、鎌倉時代に入って地名を現在の『多久』と呼ぶようになったようです。
---------------------
2021年12月15日
川浪秀之(Webプロデューサー、作家)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
2021年12月03日
三瀬村の歴史秘める北山湖
秋が深まる12月は、三瀬村のあちこちで木々が織りなす紅葉を楽しめる季節。
中でも紅葉のスポットとして知られる北山湖は私が最も魅力を感じる場所の一つです。
静かな湖畔のあちこちには遊歩道が整備され、訪れた人々は色づくイチョウやモミジをゆっくりと歩きながら楽しめます。辺りの山野にはカワウやカワラヒワなどの野鳥の姿が見られ、希に県の絶滅危惧種となっているミサゴが湖面を滑空する姿を目撃することも。
湖にはフナやコイに加え、バスやヘラブナが泳ぐ姿もあり、九州でも有数の釣りのスポットの一つと知られている北山湖には多くの釣り客も訪れます。そんな北山湖で忘れてはならない魚がワカサギです。
大きいものでも体長10cmほどの小魚で10月下旬から3月くらいまでのシーズン中、湖で釣ることが出来ます。
小さい為、初心者にも釣りやすく、天ぷらにして食べると美味だということもあり、ワカサギ釣りには小さなお子さんのいらっしゃる家族連れなどに人気です。私が会った家族は小学校低学年の娘さんと親子3人で半日をかけ、100匹近くをつり上げていました。
常連客の中には一日でおよそ1000匹をつり上げる人もいるというから驚きです。
三瀬村を取材しはじめたばかりのころは、ただただ観光気分で好きになった北山湖ですが湖畔で貸しボート店を営む男性から話を聞いたことをきっかけにその歴史を知り、より深く魅力を感じるようになりました。
話によれば、北山湖周辺は三瀬村の中で最も大きく変化した地域の一つだそうです。
昭和32年、佐賀平野に農業用水を送る為のダム湖として作られた北山湖。入り組んだ山々を縫うように広がる湖の湖底には、かつて100軒ほどの家々からなる集落があったそうです。しかし、ダム建設計画の際に人々は周辺の地域に移り住みました。そしてダム完成後、一帯は県の自然公園に指定。湖畔には貸しボート店や宿などがオープンし、スワンボート乗り場には長蛇の列が出来るなど、昭和50年頃をピークに北山湖は一大観光地としての様相を呈したのだそうです。しかしやがて、他のレジャー施設などの観光地の隆盛と共に、北山湖を訪れる観光客は減少していきました。
12月、農業用水が放出された北山湖は満水の夏場と比べて13mほど水位が下がっています。この時期にボートに乗ると、あちこちに時代の足跡を見ることが出来ます。所々で露わになった湖底には、しっかりと形を残す家の石垣やきれいな台形状の田んぼの跡、「天照大神」の文字が深く刻まれた石碑などたくさんの人の生活の痕跡が見つけられます。ボートに同行してくれた男性は「かつてここでお祭りなんかが行われていたんやろうね」と自分も知らない昔の人々の暮らしに思いを馳せていました。
失われたものがある一方、息づいてきたものもあります。
それがワカサギです。
ダム湖では建設当初からワカサギの放流が行われてきました。今も放流は湖畔に暮らす人達や行政の協力で続けられており、私も取材させていただきました。卵を取り寄せた、三瀬村のあちこちからダム湖に流れ込む川に放流するのです。その数およそ6000万個。膨大な数ですが、鯉など他の魚に食べられ、成長するのは1%にも満たないそうです。それでも放流する人たちは「少しでも多く生き残って湖で育って欲しい」と願いを込めています。ダム湖で釣れるほどにワカサギが生息しているのは人と自然が作り出してきた営みの賜物なのです。
湖畔の男性は「人の営みも含めて自然なのかもしれないけれど 人の手でダム湖が出来て、その時間の連続の中に私も飛び込んで今、ここで暮らしているわけで その自然が肌で感じられる場所で生活できるのは幸せだと思う」と思いを語ります。
そんな魅力的な場所が、三瀬村のふらっと立ち寄れる身近な所にあること。私はそのことに深い感慨を感じずにはいられません。





2021年12月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
中でも紅葉のスポットとして知られる北山湖は私が最も魅力を感じる場所の一つです。
静かな湖畔のあちこちには遊歩道が整備され、訪れた人々は色づくイチョウやモミジをゆっくりと歩きながら楽しめます。辺りの山野にはカワウやカワラヒワなどの野鳥の姿が見られ、希に県の絶滅危惧種となっているミサゴが湖面を滑空する姿を目撃することも。
湖にはフナやコイに加え、バスやヘラブナが泳ぐ姿もあり、九州でも有数の釣りのスポットの一つと知られている北山湖には多くの釣り客も訪れます。そんな北山湖で忘れてはならない魚がワカサギです。
大きいものでも体長10cmほどの小魚で10月下旬から3月くらいまでのシーズン中、湖で釣ることが出来ます。
小さい為、初心者にも釣りやすく、天ぷらにして食べると美味だということもあり、ワカサギ釣りには小さなお子さんのいらっしゃる家族連れなどに人気です。私が会った家族は小学校低学年の娘さんと親子3人で半日をかけ、100匹近くをつり上げていました。
常連客の中には一日でおよそ1000匹をつり上げる人もいるというから驚きです。
三瀬村を取材しはじめたばかりのころは、ただただ観光気分で好きになった北山湖ですが湖畔で貸しボート店を営む男性から話を聞いたことをきっかけにその歴史を知り、より深く魅力を感じるようになりました。
話によれば、北山湖周辺は三瀬村の中で最も大きく変化した地域の一つだそうです。
昭和32年、佐賀平野に農業用水を送る為のダム湖として作られた北山湖。入り組んだ山々を縫うように広がる湖の湖底には、かつて100軒ほどの家々からなる集落があったそうです。しかし、ダム建設計画の際に人々は周辺の地域に移り住みました。そしてダム完成後、一帯は県の自然公園に指定。湖畔には貸しボート店や宿などがオープンし、スワンボート乗り場には長蛇の列が出来るなど、昭和50年頃をピークに北山湖は一大観光地としての様相を呈したのだそうです。しかしやがて、他のレジャー施設などの観光地の隆盛と共に、北山湖を訪れる観光客は減少していきました。
12月、農業用水が放出された北山湖は満水の夏場と比べて13mほど水位が下がっています。この時期にボートに乗ると、あちこちに時代の足跡を見ることが出来ます。所々で露わになった湖底には、しっかりと形を残す家の石垣やきれいな台形状の田んぼの跡、「天照大神」の文字が深く刻まれた石碑などたくさんの人の生活の痕跡が見つけられます。ボートに同行してくれた男性は「かつてここでお祭りなんかが行われていたんやろうね」と自分も知らない昔の人々の暮らしに思いを馳せていました。
失われたものがある一方、息づいてきたものもあります。
それがワカサギです。
ダム湖では建設当初からワカサギの放流が行われてきました。今も放流は湖畔に暮らす人達や行政の協力で続けられており、私も取材させていただきました。卵を取り寄せた、三瀬村のあちこちからダム湖に流れ込む川に放流するのです。その数およそ6000万個。膨大な数ですが、鯉など他の魚に食べられ、成長するのは1%にも満たないそうです。それでも放流する人たちは「少しでも多く生き残って湖で育って欲しい」と願いを込めています。ダム湖で釣れるほどにワカサギが生息しているのは人と自然が作り出してきた営みの賜物なのです。
湖畔の男性は「人の営みも含めて自然なのかもしれないけれど 人の手でダム湖が出来て、その時間の連続の中に私も飛び込んで今、ここで暮らしているわけで その自然が肌で感じられる場所で生活できるのは幸せだと思う」と思いを語ります。
そんな魅力的な場所が、三瀬村のふらっと立ち寄れる身近な所にあること。私はそのことに深い感慨を感じずにはいられません。





2021年12月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com