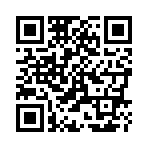2021年11月15日
初瀬川~そば街道考~
初瀬川
前回の続きから。
高瀬川、鳴瀬川を見たあと、次は初瀬川ということで、国道263号線に戻った。
国道263号線は、別名『そば街道』とも呼ばれるくらい国道沿いや付近に蕎麦屋が点在している。
しかし、三瀬村と蕎麦の関係はけして古くからあった話ではなく、どうやら、三十数年前に国道沿いに『三瀬そば』の看板が立ったのが、そのはじまりのようだ。
なんでも、この辺りでは良質の湧き水が出るというのも、蕎麦屋が立つ理由らしい。
さて、初瀬川である。
「初瀬川はどこで見ましょうか?」
と同行の男性に訊くと、
「風羅坊(ふうらぼう)に行ってみますか?」
風羅坊(ふうらぼう)とは、国道沿いにある、印象的な手書きの看板が目印の蕎麦屋のことで、僕は行ったことがなかったので、
「行ってみましょう!」
と二つ返事で、行ってみることにした。
風羅坊の看板から敷地内に入ると、合瀬橋という小橋がかかっていて、その下を流れるのが初瀬川だ。
橋の欄干に手をついて、しばし川を眺める。
いまでは三瀬村の代表的なシンボルとなった『そば街道』に、沿うようにして流れている。
ん? いや、違う。
初瀬川が先で、街道が後なのだ。
古来より初瀬川に沿って人が歩き、それがいつか街道となった。そして時を経て、『そば街道』と言われるようになったのだ。
川があるけん、三瀬たい。
と昔なじみの某ローカルCMのように、博多弁でいうこともないが、昔も今も川と縁の深い土地なのだ。
それから僕たちは、次なる目的地のモクモクハウスへ向かった。
佐賀から行くと三瀬トンネルの手前にある、丸太小屋造りの建物が特徴的な喫茶店だ。
この店ももちろん以前から知っていたが、目の前の道を通過するだけで、入ったことがなかった。
中に入ると、奥にテラス席がある。
僕たちの他には客がいなかったので、テラス席に出てみた。
「いやあ、ここは最高ですね!」
僕は思わず、唸ってしまった。
目の前に初瀬川が流れている。
豊かな水量で、川のせせらぎがひっきりなしに聴こえている。
初瀬川ウォッチの絶好の場所を見つけた瞬間だった。
続きはまた次回。
六月某日。
風羅坊

合瀬橋

初瀬川

モクモクハウス

テラス席から見る初瀬川

2021年11月15日
川浪秀之(Webプロデューサー、作家)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
前回の続きから。
高瀬川、鳴瀬川を見たあと、次は初瀬川ということで、国道263号線に戻った。
国道263号線は、別名『そば街道』とも呼ばれるくらい国道沿いや付近に蕎麦屋が点在している。
しかし、三瀬村と蕎麦の関係はけして古くからあった話ではなく、どうやら、三十数年前に国道沿いに『三瀬そば』の看板が立ったのが、そのはじまりのようだ。
なんでも、この辺りでは良質の湧き水が出るというのも、蕎麦屋が立つ理由らしい。
さて、初瀬川である。
「初瀬川はどこで見ましょうか?」
と同行の男性に訊くと、
「風羅坊(ふうらぼう)に行ってみますか?」
風羅坊(ふうらぼう)とは、国道沿いにある、印象的な手書きの看板が目印の蕎麦屋のことで、僕は行ったことがなかったので、
「行ってみましょう!」
と二つ返事で、行ってみることにした。
風羅坊の看板から敷地内に入ると、合瀬橋という小橋がかかっていて、その下を流れるのが初瀬川だ。
橋の欄干に手をついて、しばし川を眺める。
いまでは三瀬村の代表的なシンボルとなった『そば街道』に、沿うようにして流れている。
ん? いや、違う。
初瀬川が先で、街道が後なのだ。
古来より初瀬川に沿って人が歩き、それがいつか街道となった。そして時を経て、『そば街道』と言われるようになったのだ。
川があるけん、三瀬たい。
と昔なじみの某ローカルCMのように、博多弁でいうこともないが、昔も今も川と縁の深い土地なのだ。
それから僕たちは、次なる目的地のモクモクハウスへ向かった。
佐賀から行くと三瀬トンネルの手前にある、丸太小屋造りの建物が特徴的な喫茶店だ。
この店ももちろん以前から知っていたが、目の前の道を通過するだけで、入ったことがなかった。
中に入ると、奥にテラス席がある。
僕たちの他には客がいなかったので、テラス席に出てみた。
「いやあ、ここは最高ですね!」
僕は思わず、唸ってしまった。
目の前に初瀬川が流れている。
豊かな水量で、川のせせらぎがひっきりなしに聴こえている。
初瀬川ウォッチの絶好の場所を見つけた瞬間だった。
続きはまた次回。
六月某日。
風羅坊

合瀬橋

初瀬川

モクモクハウス

テラス席から見る初瀬川

2021年11月15日
川浪秀之(Webプロデューサー、作家)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
2021年11月02日
秋祭りに息づく“変わらないもの”
三瀬村の人家から少し離れた山深い場所に、400年の歴史を持つ神社があると聞き、私が訪れたのは2年前の10月下旬でした。
棚田を横目に細いアスファルトを登ると、山と人の生活領域を明確に仕切るようにそびえる濃い緑の杉林が姿を現します。
その麓には石造りの白い鳥居が鎮座していました。鳥居をくぐり、間近に野鳥の声を聞きながら参道を進むと木造の拝殿が見えてきます。わずかに水気を孕んだ冷気の中、佇む拝殿は杉の葉の隙間を縫って差し込む鋭い秋の陽光に照らされ、とても厳かに見えました。
この神社では秋になると集落の人たちが祭りを行うと言います。
準備は集落の4~5軒ごとに幾つか分けられた茶講地という班が毎年、持ち回りで担当。班の人たちはまず、境内を手分けして掃除します。男性陣は草刈り機で境内を手入れし、女性陣は拝殿の壁や床などを雑巾で磨き、一年の汚れを清めるのです。
「他の茶講地の時より俺らの時の祭りがよかったって言われるようにって競い合うんですよ」
と人々はやりがいを語ります。
掃除の後、行われるのはしめ縄作り。男性陣が車座になって、その年に採れた米の藁を使い、それぞれが縄をよります。
ある程度の大きさになると、今度は小屋の天井の梁などからぶら下げて、さらに太くします。大人三人が一本ずつ縄を持ち、それぞれの縄を体を回転させながら一つの縄によっていくのです。かけ声と持てる握力を振り絞って縄をよる若手。その若手を鼓舞し、指導するのは班の年長者。
「俺が死んだ時はあれがこうしろって言い寄ったと覚えておけ」
と年長者が言い、若手は威勢のいいかけ声でそれに答えるのです。やがてしめ縄は太いところで直径およそ30cm、長さは8mにも達し、完成。鳥居に飾られます。
女性陣は祭り当日、祭りの直会(なおらい)で参拝者に振る舞う料理をこしらえます。
野菜の煮物やごま和え様々な料理の中で特に眼をひくのは「しとぎ」と呼ばれる、白玉粉を水で溶いたもの。
一昔前は生米をすりつぶして作っていたそうで、神聖さを表す白を表現するものとして祭りには欠かせないのだそうです。
女性達は、これらの料理を年配者に習い、ノートにまとめるなど工夫して受け継いできました。
秋祭りの時間を迎えると、山王社には集落の人たちが集まります。
神主による祝詞の奏上が行われた後、人々は拝殿の奥に続く本殿に向かい、玉串を捧げます。人々は山の厳しい冬を乗り越え、大雨や獣の害などと向き合いながら米を育ててきました。神事の静謐な様子から、神様に頭を垂れる人たちの胸中には今年も無事に米が収穫できたことへの感謝の念があることをうかがい知ることが出来ます。
神事の後の直会では女性達が作った料理が振る舞われます。しとぎは薄く輪切りにした大根の上に茹でた大豆と共にのせた状態で勧められ、それを口にしながら参拝者は酒を酌み交わし、互いの一年の苦労を分かち合うのです。
祭りに集う人たちは皆、草刈りや水路掃除など稲作に関わる作業を一年を通し、共同で行っている米の兼業農家です。共に過ごす時間は多く、世代を超えたつきあいも頻繁で、コロナ禍になる前は直会に限らず、共同作業の後は決まって集まり、酒を飲んでいました。
互いに家族構成から性格や価値観に至るまでをよく知り、時には冗談を言いながらも相手の田の米の育ち具合を自分の事のように心配する。そんなつきあいが直会の中にはありました。
その事が祭りが「伝統や歴史」だけでなく、「自分にとって大切な人が大事にしているものだからこそ、自分も大事にする」という気持ちの繋がりによっても受け継がれてきたのだと気付かせてくれました。
三瀬村で大切にされてきた“変わらないもの”。
村の秋祭りは、その精神を今も私に教えてくれます。





2021年11月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
棚田を横目に細いアスファルトを登ると、山と人の生活領域を明確に仕切るようにそびえる濃い緑の杉林が姿を現します。
その麓には石造りの白い鳥居が鎮座していました。鳥居をくぐり、間近に野鳥の声を聞きながら参道を進むと木造の拝殿が見えてきます。わずかに水気を孕んだ冷気の中、佇む拝殿は杉の葉の隙間を縫って差し込む鋭い秋の陽光に照らされ、とても厳かに見えました。
この神社では秋になると集落の人たちが祭りを行うと言います。
準備は集落の4~5軒ごとに幾つか分けられた茶講地という班が毎年、持ち回りで担当。班の人たちはまず、境内を手分けして掃除します。男性陣は草刈り機で境内を手入れし、女性陣は拝殿の壁や床などを雑巾で磨き、一年の汚れを清めるのです。
「他の茶講地の時より俺らの時の祭りがよかったって言われるようにって競い合うんですよ」
と人々はやりがいを語ります。
掃除の後、行われるのはしめ縄作り。男性陣が車座になって、その年に採れた米の藁を使い、それぞれが縄をよります。
ある程度の大きさになると、今度は小屋の天井の梁などからぶら下げて、さらに太くします。大人三人が一本ずつ縄を持ち、それぞれの縄を体を回転させながら一つの縄によっていくのです。かけ声と持てる握力を振り絞って縄をよる若手。その若手を鼓舞し、指導するのは班の年長者。
「俺が死んだ時はあれがこうしろって言い寄ったと覚えておけ」
と年長者が言い、若手は威勢のいいかけ声でそれに答えるのです。やがてしめ縄は太いところで直径およそ30cm、長さは8mにも達し、完成。鳥居に飾られます。
女性陣は祭り当日、祭りの直会(なおらい)で参拝者に振る舞う料理をこしらえます。
野菜の煮物やごま和え様々な料理の中で特に眼をひくのは「しとぎ」と呼ばれる、白玉粉を水で溶いたもの。
一昔前は生米をすりつぶして作っていたそうで、神聖さを表す白を表現するものとして祭りには欠かせないのだそうです。
女性達は、これらの料理を年配者に習い、ノートにまとめるなど工夫して受け継いできました。
秋祭りの時間を迎えると、山王社には集落の人たちが集まります。
神主による祝詞の奏上が行われた後、人々は拝殿の奥に続く本殿に向かい、玉串を捧げます。人々は山の厳しい冬を乗り越え、大雨や獣の害などと向き合いながら米を育ててきました。神事の静謐な様子から、神様に頭を垂れる人たちの胸中には今年も無事に米が収穫できたことへの感謝の念があることをうかがい知ることが出来ます。
神事の後の直会では女性達が作った料理が振る舞われます。しとぎは薄く輪切りにした大根の上に茹でた大豆と共にのせた状態で勧められ、それを口にしながら参拝者は酒を酌み交わし、互いの一年の苦労を分かち合うのです。
祭りに集う人たちは皆、草刈りや水路掃除など稲作に関わる作業を一年を通し、共同で行っている米の兼業農家です。共に過ごす時間は多く、世代を超えたつきあいも頻繁で、コロナ禍になる前は直会に限らず、共同作業の後は決まって集まり、酒を飲んでいました。
互いに家族構成から性格や価値観に至るまでをよく知り、時には冗談を言いながらも相手の田の米の育ち具合を自分の事のように心配する。そんなつきあいが直会の中にはありました。
その事が祭りが「伝統や歴史」だけでなく、「自分にとって大切な人が大事にしているものだからこそ、自分も大事にする」という気持ちの繋がりによっても受け継がれてきたのだと気付かせてくれました。
三瀬村で大切にされてきた“変わらないもの”。
村の秋祭りは、その精神を今も私に教えてくれます。





2021年11月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com