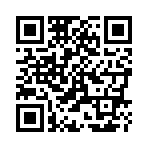2023年01月01日
“美しい里山” 三瀬村
“美しい里山”。
それは「三瀬ってどんなところ?」と尋ねられた時、浮かんできた言葉でした。でもそのまま口にしても、うまく伝わらないし、その理由を語ろうとすると長くなるので、僕はいつも「自然豊かで空気も食べ物もおいしい村だよ」と答えてしまっていました。今回は、そんな“美しい里山”について話です。
最初にそう感じたのは、取材を始めたばかりだった六年近く前の秋。取材の為、稲刈りを行う初老の男性に出会った時でした。日に焼けた男性の浅黒い肌には力強さが漲り、節くれだった手には内に身に秘めている苦労がにじみ出ていました。しかし、その男性は苦労などは一切、語らず、朗らかに「今年もよう実った。豊作よ」と言って笑いました。その背後にはまだ狩り残してある黄金の海が広がっていて、時折拭く秋風に身重の穂を大きく揺らしていました。
その光景に僕は、この実りの為に男性が掛けてきた苦労と時間、そしてそんな人々の営みの連続が里山を作り上げてきたことを想像し、それがそのまま人と山との関わりの歴史であることにも気づいて、三瀬村を“美しい里山”だと思ったのでした。
その印象は長年の取材の中で、今も確かに息づく人の営みの姿としてより具体的に像を結んでいくようになっていきました。
例えば冬。三瀬村は平野部とは全く違う様相を呈します。脊振山系の裾野に広がる標高400~500ほどの村のあちこちには雪が降り積もり、木々などで少しでも陰ったところはなかなか溶けることがありません。
佐賀駅周辺では見たこともないような、大きなつららが家の軒先に伸びている光景を僕は何度も目にしてきました。村の土木建築会社の人たちは冬場、天気予報を小まめにチェックしながら、困っている人たちがいないか村のあちこちを見回ります。雪の予報の出ている時には道路凍結防止の薬を散布したり、積雪後、塞がれてしまった生活道路の除雪をしたりするのです。この冬の厳しさへの対策は農家でも行われます。
ある女性の家では、氷点下の気候から収穫した里芋を守る為、畑に穴を掘って石灰をまき、その中に里芋を入れて藁で蓋をして土などを被せます。こうすることで冬場、里芋を貯蔵することが出来るのだそうです。今はほとんど行われていませんが、一昔前は、冬場は炭焼きが行われ、山のあちこちから煙が上がっていたのだそうです。
冬はそればかりではありません。年末に向けて行われる、収穫した稲わらを使ったしめ縄作り。田んぼで採れたもち米を使った餅つきに、畑で採れた蕎麦を粉にして農家自らが打ち、親戚や親類に配る年越しの傍作り。新年になれば、子どもたちが集落の家々を回り、無病息災を祈る七福神や櫓を汲んで火を炊くホンゲンギョウなどの行事も行われます。恐らく、僕が知らないだけで冬場に行われる大小さまざまな行事はまだたくさん、あるのだと思います。
こういった山に暮らす人々の営みは春から秋にかけても続いていきます。水路に水を引くための井手区役や水の恵みに感謝する川祭りと田植え。日照りで水が足りない年には、川の上流に田を持つ人がわざと米を作らず、下流の人の田の為にに水を流すといった光景も見られました。
初夏にはブルーベリー園も開園。さらに真夏になれば村の若者が夏祭りを開き、やがて運動会や村の産品を販売し、都市部の人と交流するふれあい祭りなども開催されます。稲刈りが終わるとそれぞれの集落の神社では、五穀豊穣を感謝する神社のお祭りが行われます。山の営みはそれだけではありません。暮らしを守る為、地域の消防団は山からの川の堰から水を取り、消火を行う訓練が定期的に行われています。
賑やかでひたむきな人々の山の営み。高台に上ると山と人とが紡いできた、その里山の光景を前にすると、僕はこの土地に暮らす人たちの生きざまにただただ頭を垂れる思いを抱くようになりました。そして昔、何かの本で読んだ「人間は自然界では一つの動物である。山でその生を営むことは、それそのものが奇跡であることを知らねばならない」という言葉を思い出したのです。恐らく、三瀬村の人たちが見ている世界は、町中に暮らす僕が見ているものよりもずっと広くて深いのです。
集落に子どもが生まれると、皆が祝いの言葉をささげ、子ど達は野山や川に親しんで遊ぶ。青年たちは勤めに出ながらも、集落の生活道路に伸びてくる山の草木を刈るために共同の草刈りに参加するし、集落ごとに地域の営みを守り、引き継いできた年配者へ感謝を伝える為の敬老会が開かれる。村の誰かが亡くなれば、皆で弔いながら葬儀も協力して行う。村の人たちは命というものの、かけがえのない大切さを日々の営みの中で常に感じながら、だからこそ今を懸命に生きている、だからこそ、そんな人たちが暮らす里山が美しいのだと、僕はつくづく思いました。
人の命を脅かす積雪や洪水、水不足。そんな自然の厳しさを力を合わせ、乗り越えながら、その恵みを共に分かち合って感謝する。祭りや共同作業の後には決まって宴会が開かれ、大人たちは笑い合いながら酒を酌み交わします。肴になるのは山で採れたイノシシの肉を焼いたものや里芋などの畑での収穫物。そんなごちそう目当てに子どもたちも宴会に加わり、にぎやかな会場はさながら正月を迎えた大所帯の家族の集まりのようです。
少子高齢化や過疎化で人が減っていく中、今も村の年配の人たちは山の暮らしを大切にしています。その暮らしを引き継ぐため、若者や子供たちも年配者に稲刈り機の使い方を教わったり、米の乾燥作業を共に行うなどして、各々が必死にその営みに参加しています。その思いはどこから生まれるのか、尋ねたことがあります。
ある30代の若者は「うちのお母さんが集落の人に農作業とか家のこととかで本当にお世話になった。今度は僕がお返しせんといかん。ふるさとも好きやしね」と答えてくれました。その言葉を補足するように、ある農家の年配の女性は言います。
「大人たちが集まって楽しそうにしている姿を見て育っているからね。あれが子供たちにとっては「ふるさとの幸せな暮らし」
だからふるさとを、この里山の三瀬村を大切に引き継いでいきたいと思っているんだろうね」
受け継がれてきた“美しさ”。それを大切にし、今を生きる三瀬村の人々と出会えたことは、僕の人生にとって大きな財産です。
---------------------
2023年1月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
それは「三瀬ってどんなところ?」と尋ねられた時、浮かんできた言葉でした。でもそのまま口にしても、うまく伝わらないし、その理由を語ろうとすると長くなるので、僕はいつも「自然豊かで空気も食べ物もおいしい村だよ」と答えてしまっていました。今回は、そんな“美しい里山”について話です。
最初にそう感じたのは、取材を始めたばかりだった六年近く前の秋。取材の為、稲刈りを行う初老の男性に出会った時でした。日に焼けた男性の浅黒い肌には力強さが漲り、節くれだった手には内に身に秘めている苦労がにじみ出ていました。しかし、その男性は苦労などは一切、語らず、朗らかに「今年もよう実った。豊作よ」と言って笑いました。その背後にはまだ狩り残してある黄金の海が広がっていて、時折拭く秋風に身重の穂を大きく揺らしていました。
その光景に僕は、この実りの為に男性が掛けてきた苦労と時間、そしてそんな人々の営みの連続が里山を作り上げてきたことを想像し、それがそのまま人と山との関わりの歴史であることにも気づいて、三瀬村を“美しい里山”だと思ったのでした。
その印象は長年の取材の中で、今も確かに息づく人の営みの姿としてより具体的に像を結んでいくようになっていきました。
例えば冬。三瀬村は平野部とは全く違う様相を呈します。脊振山系の裾野に広がる標高400~500ほどの村のあちこちには雪が降り積もり、木々などで少しでも陰ったところはなかなか溶けることがありません。
佐賀駅周辺では見たこともないような、大きなつららが家の軒先に伸びている光景を僕は何度も目にしてきました。村の土木建築会社の人たちは冬場、天気予報を小まめにチェックしながら、困っている人たちがいないか村のあちこちを見回ります。雪の予報の出ている時には道路凍結防止の薬を散布したり、積雪後、塞がれてしまった生活道路の除雪をしたりするのです。この冬の厳しさへの対策は農家でも行われます。
ある女性の家では、氷点下の気候から収穫した里芋を守る為、畑に穴を掘って石灰をまき、その中に里芋を入れて藁で蓋をして土などを被せます。こうすることで冬場、里芋を貯蔵することが出来るのだそうです。今はほとんど行われていませんが、一昔前は、冬場は炭焼きが行われ、山のあちこちから煙が上がっていたのだそうです。
冬はそればかりではありません。年末に向けて行われる、収穫した稲わらを使ったしめ縄作り。田んぼで採れたもち米を使った餅つきに、畑で採れた蕎麦を粉にして農家自らが打ち、親戚や親類に配る年越しの傍作り。新年になれば、子どもたちが集落の家々を回り、無病息災を祈る七福神や櫓を汲んで火を炊くホンゲンギョウなどの行事も行われます。恐らく、僕が知らないだけで冬場に行われる大小さまざまな行事はまだたくさん、あるのだと思います。
こういった山に暮らす人々の営みは春から秋にかけても続いていきます。水路に水を引くための井手区役や水の恵みに感謝する川祭りと田植え。日照りで水が足りない年には、川の上流に田を持つ人がわざと米を作らず、下流の人の田の為にに水を流すといった光景も見られました。
初夏にはブルーベリー園も開園。さらに真夏になれば村の若者が夏祭りを開き、やがて運動会や村の産品を販売し、都市部の人と交流するふれあい祭りなども開催されます。稲刈りが終わるとそれぞれの集落の神社では、五穀豊穣を感謝する神社のお祭りが行われます。山の営みはそれだけではありません。暮らしを守る為、地域の消防団は山からの川の堰から水を取り、消火を行う訓練が定期的に行われています。
賑やかでひたむきな人々の山の営み。高台に上ると山と人とが紡いできた、その里山の光景を前にすると、僕はこの土地に暮らす人たちの生きざまにただただ頭を垂れる思いを抱くようになりました。そして昔、何かの本で読んだ「人間は自然界では一つの動物である。山でその生を営むことは、それそのものが奇跡であることを知らねばならない」という言葉を思い出したのです。恐らく、三瀬村の人たちが見ている世界は、町中に暮らす僕が見ているものよりもずっと広くて深いのです。
集落に子どもが生まれると、皆が祝いの言葉をささげ、子ど達は野山や川に親しんで遊ぶ。青年たちは勤めに出ながらも、集落の生活道路に伸びてくる山の草木を刈るために共同の草刈りに参加するし、集落ごとに地域の営みを守り、引き継いできた年配者へ感謝を伝える為の敬老会が開かれる。村の誰かが亡くなれば、皆で弔いながら葬儀も協力して行う。村の人たちは命というものの、かけがえのない大切さを日々の営みの中で常に感じながら、だからこそ今を懸命に生きている、だからこそ、そんな人たちが暮らす里山が美しいのだと、僕はつくづく思いました。
人の命を脅かす積雪や洪水、水不足。そんな自然の厳しさを力を合わせ、乗り越えながら、その恵みを共に分かち合って感謝する。祭りや共同作業の後には決まって宴会が開かれ、大人たちは笑い合いながら酒を酌み交わします。肴になるのは山で採れたイノシシの肉を焼いたものや里芋などの畑での収穫物。そんなごちそう目当てに子どもたちも宴会に加わり、にぎやかな会場はさながら正月を迎えた大所帯の家族の集まりのようです。
少子高齢化や過疎化で人が減っていく中、今も村の年配の人たちは山の暮らしを大切にしています。その暮らしを引き継ぐため、若者や子供たちも年配者に稲刈り機の使い方を教わったり、米の乾燥作業を共に行うなどして、各々が必死にその営みに参加しています。その思いはどこから生まれるのか、尋ねたことがあります。
ある30代の若者は「うちのお母さんが集落の人に農作業とか家のこととかで本当にお世話になった。今度は僕がお返しせんといかん。ふるさとも好きやしね」と答えてくれました。その言葉を補足するように、ある農家の年配の女性は言います。
「大人たちが集まって楽しそうにしている姿を見て育っているからね。あれが子供たちにとっては「ふるさとの幸せな暮らし」
だからふるさとを、この里山の三瀬村を大切に引き継いでいきたいと思っているんだろうね」
受け継がれてきた“美しさ”。それを大切にし、今を生きる三瀬村の人々と出会えたことは、僕の人生にとって大きな財産です。
---------------------
2023年1月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
2022年12月02日
集落結ぶ新年行事“ホンゲンギョウ”
集落の人たちが力を合わせて年越しの準備をするという話を聞いて、取材で行ってみると、山つきの畑の傍の竹林には大勢の集落の人たちが集まっていました。竹は集落の公民館に飾る門松作りとホンゲンギョウに使われるそうです。
ホンゲンギョウとは厄除けの火祭り。三メートルほどの大きな竹と枯草などで作った櫓を年が明けてから炊きつけ、その年、集落の人たちが無病息災で過ごせることを祈る大切な新年行事です。
いつの頃から行われているのか定かではありませんが、この集落では少なくとも今の八十代の方々が幼いころには既に行われていたようです。
そんな行事が今も人々の手によって続けられているという話を聞いて、それがどのような形で、そんな思いの元に受け継がれているのか、実際のところを知りたいというのが僕が取材に伺ったきっかけでした。
霧雨が降る、師走の冷え込みの中、チェンソーを持った幾人かの人たちが畑に覆いかぶさるように成長した竹林の根の暗闇に分け入っていきます。すぐに雨の静寂を破る様に、けたたましいチェンソーの音が響き渡りました。
しばらく続いたその音が急に静かになったと思ったら、太い竹が一本、その細い体をしならせながら葉擦れの音を立てて畑に倒れてきました。その竹の周りに倒竹作業を見守っていた他の人たちが集まり、鉈で枝葉を切り落としていきます。そうして一本の長い柱になった竹は真ん中くらいで更に分割され、軽トラックの荷台に積み込まれました。新年を迎える為の、この倒竹作業は畑などに迫る竹林の除去作業も兼ねているのだとか。
冷え込みが増す中、そう言いながらカッパ姿で黙々と作業する人たちを見ていると、僕は山の行事と暮らしがいかに強く結びついているかを改めて感じました。
切り出された竹の一部は集落の公民館に運ばれます。そこで年間を通して集落の大事な会合を重ねる場所の為の、門松を作るのです。手掛けるのは主に年配の男性の人たちです。
そして、そのすぐ近くを流れる川の袂。畑との境にある野原では竹の櫓が組まれます。太く長い竹の柱を中心に、いくつかの方向から他の竹の柱を先端近くで交わらせ、骨組みを作ります。そうして後は枯草などを敷き詰めて太くしていくのです。この作業には更に多くの人たちが加わり、集落のリーダーの男性の指示に従って動いていきます。まだ霧雨は続いており、冷え込みは骨を痺れさせるほどです。しかし、人々は懸命に体を動かし、ホンゲンギョウの象徴である櫓を協力し合って作り上げていくのです。そうして櫓が完成したのは竹の切り出しからおよそ六時間近くが経った頃でした。
年が明けて間もない五日の早朝、僕は再び、この集落を訪れました。この日はホンゲンギョウ当日。
まだ薄暗い畑の櫓の周りには集落の大勢の人たちが集まっていました。作業を行った男性たちばかりではなく、その奥さんや子供たち、年配の人たちなど様々な世代の人たちです。その人たちが見守る中、朝六時を待って櫓には火がつけられます。枯草と竹で作られた櫓は瞬く間に巨大な炎に包まれました。
黙ってその炎を見つめたり、携帯で動画を撮ったり、人々はそれぞれのやり方で、新年最初に灯された厄除けの炎と相対し、家族や集落、ひいては村の仲間の無病息災を祈っていました。僕はこういった場に自分も立ち会えていることが嬉しく、受け入れていただいていることに感謝しながら、人々に習って鬼火に祈りを捧げました。
年末に六時間近くもかけて作り上げた櫓は、火を点けてわずか十五分ほどで崩れ落ちました。そこからは集落の人たちの新年の交流が始まります。
残り火の上に網を敷き、村で採れたイノシシの肉や持ち寄った魚の干物、餅などを焼くのです。大人はこれを肴に酒を飲みかわしますが、子供たちは更にこの熾火で焼き芋やウィンナー、マシュマロなどを焼いて食べるのを楽しみにしています。
孫が生まれた家族は集落の人たちのお披露目にと、その孫を連れてきたり、冬休みでしばらく会えていなかった友達にも、この時に会って話したり。賑やかな新年最初の交流の様子は日の出と共に行われるのです。
交流の終わりごろ、人々は竹で何やら作り始めました。熾火で竹の一部を熱して折り曲げて三角みたいな形にして作り上げたのは「鬼の手」と呼ばれるもの。これを家の玄関先に置くことで魔除けにするのだそうです。
この時、話を聞いた男性の言葉が強く印象に残っています。
「年々、少子高齢化などで山の暮らしは厳しくなっている。そんな中でホンゲンギョウをやってこうして交流できることが何より大事。皆で気合を入れて今年も一年、頑張ろうと思える。そんな思いを共有できる。山で暮らす中で大切なことだと思っている」
ホンゲンギョウはまさに集落の人たちにとって、結の炎なのだと、僕はつくづく思いました。この行事が今年も、来年も、その先もずっと続けられていくことを願わずにはいられません。





---------------------
2022年12月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
ホンゲンギョウとは厄除けの火祭り。三メートルほどの大きな竹と枯草などで作った櫓を年が明けてから炊きつけ、その年、集落の人たちが無病息災で過ごせることを祈る大切な新年行事です。
いつの頃から行われているのか定かではありませんが、この集落では少なくとも今の八十代の方々が幼いころには既に行われていたようです。
そんな行事が今も人々の手によって続けられているという話を聞いて、それがどのような形で、そんな思いの元に受け継がれているのか、実際のところを知りたいというのが僕が取材に伺ったきっかけでした。
霧雨が降る、師走の冷え込みの中、チェンソーを持った幾人かの人たちが畑に覆いかぶさるように成長した竹林の根の暗闇に分け入っていきます。すぐに雨の静寂を破る様に、けたたましいチェンソーの音が響き渡りました。
しばらく続いたその音が急に静かになったと思ったら、太い竹が一本、その細い体をしならせながら葉擦れの音を立てて畑に倒れてきました。その竹の周りに倒竹作業を見守っていた他の人たちが集まり、鉈で枝葉を切り落としていきます。そうして一本の長い柱になった竹は真ん中くらいで更に分割され、軽トラックの荷台に積み込まれました。新年を迎える為の、この倒竹作業は畑などに迫る竹林の除去作業も兼ねているのだとか。
冷え込みが増す中、そう言いながらカッパ姿で黙々と作業する人たちを見ていると、僕は山の行事と暮らしがいかに強く結びついているかを改めて感じました。
切り出された竹の一部は集落の公民館に運ばれます。そこで年間を通して集落の大事な会合を重ねる場所の為の、門松を作るのです。手掛けるのは主に年配の男性の人たちです。
そして、そのすぐ近くを流れる川の袂。畑との境にある野原では竹の櫓が組まれます。太く長い竹の柱を中心に、いくつかの方向から他の竹の柱を先端近くで交わらせ、骨組みを作ります。そうして後は枯草などを敷き詰めて太くしていくのです。この作業には更に多くの人たちが加わり、集落のリーダーの男性の指示に従って動いていきます。まだ霧雨は続いており、冷え込みは骨を痺れさせるほどです。しかし、人々は懸命に体を動かし、ホンゲンギョウの象徴である櫓を協力し合って作り上げていくのです。そうして櫓が完成したのは竹の切り出しからおよそ六時間近くが経った頃でした。
年が明けて間もない五日の早朝、僕は再び、この集落を訪れました。この日はホンゲンギョウ当日。
まだ薄暗い畑の櫓の周りには集落の大勢の人たちが集まっていました。作業を行った男性たちばかりではなく、その奥さんや子供たち、年配の人たちなど様々な世代の人たちです。その人たちが見守る中、朝六時を待って櫓には火がつけられます。枯草と竹で作られた櫓は瞬く間に巨大な炎に包まれました。
黙ってその炎を見つめたり、携帯で動画を撮ったり、人々はそれぞれのやり方で、新年最初に灯された厄除けの炎と相対し、家族や集落、ひいては村の仲間の無病息災を祈っていました。僕はこういった場に自分も立ち会えていることが嬉しく、受け入れていただいていることに感謝しながら、人々に習って鬼火に祈りを捧げました。
年末に六時間近くもかけて作り上げた櫓は、火を点けてわずか十五分ほどで崩れ落ちました。そこからは集落の人たちの新年の交流が始まります。
残り火の上に網を敷き、村で採れたイノシシの肉や持ち寄った魚の干物、餅などを焼くのです。大人はこれを肴に酒を飲みかわしますが、子供たちは更にこの熾火で焼き芋やウィンナー、マシュマロなどを焼いて食べるのを楽しみにしています。
孫が生まれた家族は集落の人たちのお披露目にと、その孫を連れてきたり、冬休みでしばらく会えていなかった友達にも、この時に会って話したり。賑やかな新年最初の交流の様子は日の出と共に行われるのです。
交流の終わりごろ、人々は竹で何やら作り始めました。熾火で竹の一部を熱して折り曲げて三角みたいな形にして作り上げたのは「鬼の手」と呼ばれるもの。これを家の玄関先に置くことで魔除けにするのだそうです。
この時、話を聞いた男性の言葉が強く印象に残っています。
「年々、少子高齢化などで山の暮らしは厳しくなっている。そんな中でホンゲンギョウをやってこうして交流できることが何より大事。皆で気合を入れて今年も一年、頑張ろうと思える。そんな思いを共有できる。山で暮らす中で大切なことだと思っている」
ホンゲンギョウはまさに集落の人たちにとって、結の炎なのだと、僕はつくづく思いました。この行事が今年も、来年も、その先もずっと続けられていくことを願わずにはいられません。





---------------------
2022年12月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
2022年11月01日
山の魅力に溢れた“三瀬村 ふれあい祭り”
「3年ぶりにふれあい祭りが開催される」
三瀬村の人から、その知らせを聞きつけ、僕が会場を訪れたのは先月10月22日、土曜日のことでした。
高く抜けた秋空の下、三瀬小学校のグランドは3年ぶりに村の人たちの活気に溢れていました。ステージでは子供たちが生き生きとダンスを踊り、消防局の楽団が音楽を生演奏し、会場を沸かせています。周りのテントでは、サツマイモやキャベツなどの取れたての野菜を売る威勢のいい村の人たちの声が飛び交い、そこに嬉しそうな観光客の声が混じります。
その隙間を縫うように、ふるまいのイノシシ焼肉やしし汁の食欲をそそる香りが立ち込めてきます。祭りの会場はまさに“山の魅力”に溢れていました。訪れた人たちはそれぞれのテントに立ち寄り、村の人たちと明るく声を交わします。地元の子供たちや学校や仕事で村を離れて暮らしている人たちも訪れ、久しぶりの故郷の祭りを楽しんでいました。
「三瀬村・田舎と都市(まち)のふれあい祭り」
今年で36回目を迎える、この祭りは隣接する福岡を中心とした都市の人たちに向け、村の魅力を知ってもらう為に開かれてきました。
地場産品を扱う部会、商工会や地元の飲食店、農園など16ほどの団体が店を出し、都市部から訪れる人たちをもてなすのです。村の人たちは、この日に向けて名産のゆずごしょうや様々な野菜、食材加工品などを準備し、祭りを通して村外の人たちと文字通り、“ふれあう”機会を楽しみにしてきました。訪れる常連客にとっても、この祭りは三瀬の魅力が凝縮した、楽しみな行事です。
しかし、ここ2年、コロナ禍の為、祭りは中止となり、村では寂しい秋が続いていました。
会場で村の人たちに話を聞くと、祭りの再開の喜びと共に複雑な心境を語ってくれました。
「まだコロナ感染を懸念して止めた方がいいのではないか、という声もあった。でも祭りに携わり、続けてきた人たちは再開を待ち望んでいたし、是非、やりたいという思いもあった」
その言葉を聞いて、僕は今年、この祭りが再開され、本当によかったと心から思いました。仕事の中で様々なお祭りごとを取材してきた僕は、そういった取り組みが何かしらの理由によって一度、中止された後、そのまま再開されることなくなくなっていった事例を数多く見てきました。
「中止することは容易だが、再開は難しい」
とかつての取材先の人が漏らしていた言葉が未だに頭の片隅に残っていたからです。
しかし、閉塞感の中、じっとしていても何も始まらないこともまた事実。現に祭りの会場は、コロナ前に取材した時よりも出店数が減ってはいたものの、人々の顔には以前の祭りとはまた違った深い喜びの色があったことが僕には嬉しく感じられたのです。
祭りの中で、特に印象深かったのは「三瀬もりの会」という森の保全活動を行う団体の人たちの様子です。佐賀市の委託を受け、森の保全活動を進める為、もりの会の人たちは訪れる人たちに募金を求めます。そして募金してくれた人にはイロハモミジ、コブシ、コムラサキ、ヤマツツジといった樹木の苗木をプレゼントします。
その様子を見ていると、苗木を渡し、受け取るやりとりの中には明るい笑い声が聞こえてきました。会の人に話を聞くと「かつて募金してくれた人が、「苗木がこんなに大きな木になった」といって写真を見せによってくれる。そんな常連さんとの再会が嬉しい」と、その喜びの心情を話してくれました。
祭りは小さな苗木が、大きく成長するまでの長い年月、村の人たちと常連客との縁をつないでいたのだ。僕にはそう思えました。
年に一度、村外の三瀬ファンをもてなす「ふれあい祭り」。それはただのイベントではなく、村の人たちが常連客との絆を確かめ合い、深める為の大切な行事です。
この先も祭りが大切に受け継がれていって欲しいと僕は切に願っています。





---------------------
2022年11月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
三瀬村の人から、その知らせを聞きつけ、僕が会場を訪れたのは先月10月22日、土曜日のことでした。
高く抜けた秋空の下、三瀬小学校のグランドは3年ぶりに村の人たちの活気に溢れていました。ステージでは子供たちが生き生きとダンスを踊り、消防局の楽団が音楽を生演奏し、会場を沸かせています。周りのテントでは、サツマイモやキャベツなどの取れたての野菜を売る威勢のいい村の人たちの声が飛び交い、そこに嬉しそうな観光客の声が混じります。
その隙間を縫うように、ふるまいのイノシシ焼肉やしし汁の食欲をそそる香りが立ち込めてきます。祭りの会場はまさに“山の魅力”に溢れていました。訪れた人たちはそれぞれのテントに立ち寄り、村の人たちと明るく声を交わします。地元の子供たちや学校や仕事で村を離れて暮らしている人たちも訪れ、久しぶりの故郷の祭りを楽しんでいました。
「三瀬村・田舎と都市(まち)のふれあい祭り」
今年で36回目を迎える、この祭りは隣接する福岡を中心とした都市の人たちに向け、村の魅力を知ってもらう為に開かれてきました。
地場産品を扱う部会、商工会や地元の飲食店、農園など16ほどの団体が店を出し、都市部から訪れる人たちをもてなすのです。村の人たちは、この日に向けて名産のゆずごしょうや様々な野菜、食材加工品などを準備し、祭りを通して村外の人たちと文字通り、“ふれあう”機会を楽しみにしてきました。訪れる常連客にとっても、この祭りは三瀬の魅力が凝縮した、楽しみな行事です。
しかし、ここ2年、コロナ禍の為、祭りは中止となり、村では寂しい秋が続いていました。
会場で村の人たちに話を聞くと、祭りの再開の喜びと共に複雑な心境を語ってくれました。
「まだコロナ感染を懸念して止めた方がいいのではないか、という声もあった。でも祭りに携わり、続けてきた人たちは再開を待ち望んでいたし、是非、やりたいという思いもあった」
その言葉を聞いて、僕は今年、この祭りが再開され、本当によかったと心から思いました。仕事の中で様々なお祭りごとを取材してきた僕は、そういった取り組みが何かしらの理由によって一度、中止された後、そのまま再開されることなくなくなっていった事例を数多く見てきました。
「中止することは容易だが、再開は難しい」
とかつての取材先の人が漏らしていた言葉が未だに頭の片隅に残っていたからです。
しかし、閉塞感の中、じっとしていても何も始まらないこともまた事実。現に祭りの会場は、コロナ前に取材した時よりも出店数が減ってはいたものの、人々の顔には以前の祭りとはまた違った深い喜びの色があったことが僕には嬉しく感じられたのです。
祭りの中で、特に印象深かったのは「三瀬もりの会」という森の保全活動を行う団体の人たちの様子です。佐賀市の委託を受け、森の保全活動を進める為、もりの会の人たちは訪れる人たちに募金を求めます。そして募金してくれた人にはイロハモミジ、コブシ、コムラサキ、ヤマツツジといった樹木の苗木をプレゼントします。
その様子を見ていると、苗木を渡し、受け取るやりとりの中には明るい笑い声が聞こえてきました。会の人に話を聞くと「かつて募金してくれた人が、「苗木がこんなに大きな木になった」といって写真を見せによってくれる。そんな常連さんとの再会が嬉しい」と、その喜びの心情を話してくれました。
祭りは小さな苗木が、大きく成長するまでの長い年月、村の人たちと常連客との縁をつないでいたのだ。僕にはそう思えました。
年に一度、村外の三瀬ファンをもてなす「ふれあい祭り」。それはただのイベントではなく、村の人たちが常連客との絆を確かめ合い、深める為の大切な行事です。
この先も祭りが大切に受け継がれていって欲しいと僕は切に願っています。





---------------------
2022年11月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
2022年10月03日
受け継がれるまなざし 三瀬村のりんご園
SNSで開園情報を知り、僕は今年も高ぶる気持ちに促されるまま、三瀬村のりんご園へと出かけました。先月上旬のことでした。
大きな音を響かせて平野より一足早い稲刈りに動き回るコンバインの姿を横目に、僕が向かったのは平松集落。村で二軒のリンゴ園がある谷間の集落です。
谷底には背振山系からの清水が流れ、既にこの季節、ヒヤリとする秋の風が吹いていました。谷に広がる緑の木々の隙間には今年も色鮮やかな赤に熟した無数のリンゴが実っています。
三瀬村の取材を始めて五年。その最初の頃に出会って以来、僕は三瀬村のりんごのファンになり、毎年通うようになりました。
三瀬村のりんごは格別です。園の中では訪れた人たちが特に色づいたものを木から直接、もぎ取り、食べることができます。皮ごとかじるとパリッとした歯触りの後に水水しい甘味が口の中じジュワっと広がるのです。それぞれの園におよそ300本、植えられているという木、一本ごとに実るりんごの数はおよそ1000個。園の人たちはその一つ一つに袋掛けしている為、来園者は病気や虫などの心配をせず、そのまま新鮮なりんごを味わうことができるのです。
他にも園には注文を受けてから絞ってくれるジュースやパイ、生キャラメル、ジャム、チーズケーキなどりんごを生かした様々な品が並びます。今年はりんご飴も新たに販売されていて、園は小さなお子さんを連れた家族連れで賑わっていました。
今年の来園者の様子を尋ねると、園の人たちは多くの常連さんが来てくれていると嬉しそうに話してくれました。
佐賀や福岡を中心とした日本人客はもちろん、「今年は中国やベトナムなど海外からもお客さんが来ている」という声もあれば、「佐世保の米軍基地からアメリカ人も訪れる」との声も。九州の中でも珍しいりんごの観光農園は、それだけ注目され、人気を博しているのです。園の人とお客さんとの会話に聞こえてくるのは「今年も来たよ」という懐かしさの籠る言葉。そんな言葉を聞く度、僕はお客さんが帰ってくるような気持ちで園に訪れているのだなと感じます。
村でりんご園が開園したのは、今からおよそ40年前。平松集落の十軒の農家が集まり、人々で賑わう豊かな集落のまだ見ぬ未来を見つめ、始めたものでした。
しかし、全国的な産地である青森や長野と比べ、温暖で湿気も多い九州、佐賀県の三瀬村。虫や病気などに加え、毎年、決まって訪れる台風など、りんご栽培には困難な土地柄です。農家が次々と辞めていく中、懸命に栽培を続けてきたのが今、村で園を営む二軒。それぞれの園は互いにライバルである以上に、同じ志を持った仲間。今や先代の志を受け継いだ2代目、3代目が中心となり、園を盛り上げ、台風被害を受けた時には助け合ったり、励まし合ったりしています。
僕は仕事で取材という機会を得て、それぞれのリンゴ園の人たちから話を聞く多くの機会をいただき、受け継がれているのが、その「まなざし」であることを知ることができました。ある園の若手の男性は「じいちゃんの懸命な姿を見てきて、色々話も聞いてきたからからね」と話します。
一番の思い出は?と尋ねると、
「幼稚園のころに園の遠足で自分の家のりんご園に来て楽しんだ」
と嬉しそうに答えてくれました。
先祖代々、受け継いできた動かせない土地で暮らし、生きていく為に成してきた村の人たちの歴史。「人々で賑わう豊かな集落の未来」を見据えて始めた祖父のまなざしを男性は、共に暮らす中で感じ、そのまなざしの先のあるものを共に見るようになったのではないでしょうか。
僕がそう思うのは今、男性が家族や仲間と共に実現している光景は、祖父たちが園を始める時に思い描いた「人々で賑わう豊かな集落」の姿そのものだからです。
今、園を営む人たちのまなざしの先にある未来には、どんな光景が広がっているのでしょうか。これからもまた、僕は秋を迎える度、三瀬村に通い続けたいと思っています。




---------------------
2022年10月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
大きな音を響かせて平野より一足早い稲刈りに動き回るコンバインの姿を横目に、僕が向かったのは平松集落。村で二軒のリンゴ園がある谷間の集落です。
谷底には背振山系からの清水が流れ、既にこの季節、ヒヤリとする秋の風が吹いていました。谷に広がる緑の木々の隙間には今年も色鮮やかな赤に熟した無数のリンゴが実っています。
三瀬村の取材を始めて五年。その最初の頃に出会って以来、僕は三瀬村のりんごのファンになり、毎年通うようになりました。
三瀬村のりんごは格別です。園の中では訪れた人たちが特に色づいたものを木から直接、もぎ取り、食べることができます。皮ごとかじるとパリッとした歯触りの後に水水しい甘味が口の中じジュワっと広がるのです。それぞれの園におよそ300本、植えられているという木、一本ごとに実るりんごの数はおよそ1000個。園の人たちはその一つ一つに袋掛けしている為、来園者は病気や虫などの心配をせず、そのまま新鮮なりんごを味わうことができるのです。
他にも園には注文を受けてから絞ってくれるジュースやパイ、生キャラメル、ジャム、チーズケーキなどりんごを生かした様々な品が並びます。今年はりんご飴も新たに販売されていて、園は小さなお子さんを連れた家族連れで賑わっていました。
今年の来園者の様子を尋ねると、園の人たちは多くの常連さんが来てくれていると嬉しそうに話してくれました。
佐賀や福岡を中心とした日本人客はもちろん、「今年は中国やベトナムなど海外からもお客さんが来ている」という声もあれば、「佐世保の米軍基地からアメリカ人も訪れる」との声も。九州の中でも珍しいりんごの観光農園は、それだけ注目され、人気を博しているのです。園の人とお客さんとの会話に聞こえてくるのは「今年も来たよ」という懐かしさの籠る言葉。そんな言葉を聞く度、僕はお客さんが帰ってくるような気持ちで園に訪れているのだなと感じます。
村でりんご園が開園したのは、今からおよそ40年前。平松集落の十軒の農家が集まり、人々で賑わう豊かな集落のまだ見ぬ未来を見つめ、始めたものでした。
しかし、全国的な産地である青森や長野と比べ、温暖で湿気も多い九州、佐賀県の三瀬村。虫や病気などに加え、毎年、決まって訪れる台風など、りんご栽培には困難な土地柄です。農家が次々と辞めていく中、懸命に栽培を続けてきたのが今、村で園を営む二軒。それぞれの園は互いにライバルである以上に、同じ志を持った仲間。今や先代の志を受け継いだ2代目、3代目が中心となり、園を盛り上げ、台風被害を受けた時には助け合ったり、励まし合ったりしています。
僕は仕事で取材という機会を得て、それぞれのリンゴ園の人たちから話を聞く多くの機会をいただき、受け継がれているのが、その「まなざし」であることを知ることができました。ある園の若手の男性は「じいちゃんの懸命な姿を見てきて、色々話も聞いてきたからからね」と話します。
一番の思い出は?と尋ねると、
「幼稚園のころに園の遠足で自分の家のりんご園に来て楽しんだ」
と嬉しそうに答えてくれました。
先祖代々、受け継いできた動かせない土地で暮らし、生きていく為に成してきた村の人たちの歴史。「人々で賑わう豊かな集落の未来」を見据えて始めた祖父のまなざしを男性は、共に暮らす中で感じ、そのまなざしの先のあるものを共に見るようになったのではないでしょうか。
僕がそう思うのは今、男性が家族や仲間と共に実現している光景は、祖父たちが園を始める時に思い描いた「人々で賑わう豊かな集落」の姿そのものだからです。
今、園を営む人たちのまなざしの先にある未来には、どんな光景が広がっているのでしょうか。これからもまた、僕は秋を迎える度、三瀬村に通い続けたいと思っています。




---------------------
2022年10月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
2022年09月01日
蜂蜜というふるさと、三瀬村の味
朝の光に輝いてスプーンから流れ落ちる黄金色のはちみつを見る度、僕は幸せな気分になります。
焼きたてのトーストに少し塗って、サラダと淹れたての珈琲でいただくという朝の習慣は、僕が三瀬村ではちみつを取材したころに始まりました。
それはある年の9月、村で養蜂に取り組むという男性を取材で訪ねたことがきっかけでした。季節は採蜜の時期。男性は家の庭に設置した巣箱から蜜を採る作業の真っ最中。まだ暑さの名残りが残る中、彼は奥さんと共に真っ白な防護服をすっぽり被り、巣箱の蓋を開けていました。中には黄金色に輝く二ホンミツバチの巣がぎっしり。飛び回る蜂を刺激しないよう男性はそっと手を伸ばし、巣の状態を確かめます。よく見ると黄金色のところどころに僅かに濃い茶色に染まる部分がありました。
「熟成が進んでいる証拠 薄いところは出来立てなんです」
そう言って男性は太い糸を取出し、巣箱に巻き付けます。巣箱は枠箱が5段ほど重なった構造。その一番上の段のつなぎ目に男性はそっと糸を入れ、反対側に力いっぱい引いて中の巣を切断します。そして奥さんの手を借り、箱を持ち上げると見事に箱ごと巣の一部を切ることに成功しました。
「全部は取らないんですか?」と尋ねると
「蜂が越冬の為、貯めている蜜だから残しておかないと」と言います。
改めて残された巣箱を見ると、その入口では二ホンミツバチが花粉を足に付け、懸命に出入りしていました。それを見て、僕は彼らが厳しい三瀬村の冬を乗り越えるために懸命なのだと、つくづく思いました。
「頻繁に巣箱の世話をしていると、箱による蜂の性格の違いとか、なんとなく分かるようになって、言葉は通じないけど話をしているような感じ」。
時折、男性の指の先には蜂が挨拶するようにそっと止まります。そんな時、男性は手を動かさず、その様子を眺めながら、「何かほっとしますね」と言います。すると蜂は応えるように再び飛んでいくのです。
男性は蜂に「分けてもらった」巣を、部屋に持ち込み、採蜜作業に取り掛かります。包丁を使い、枠箱から外した巣を少しずつ切り分けて、ボウルに敷いたザルに置いていきます。「一気に絞ったら苦みが出るので、こうして三日ほど置き、たれ蜜を取るんです」
作業中、男性は巣の一欠片を口に含み、「すっきりとして甘い 採れたてが楽しめるのは養蜂やっている楽しみよ」と嬉しそうに言いました。
聞けば二ホンミツバチは巣箱から2キロほどの範囲を飛び回っているそうです。その範囲には、脊振山系からの清流に沿って、様々な野草や草花が生い茂り、集落の田畑も広がっています。
「ハチミツの味はまさに村の、この集落の味というわけですよ」
その言葉に、僕は「ふるさとの味」という表現がこれほどぴったりくるものはないと思いました。遥か昔から日本に生息し、江戸時代ごろには養蜂も行われていたと言われている二ホンミツバチ。自然を生かし、その恵みを糧としていただく養蜂に、男性は運命的に出会ったのだと話してくれました。
建築士として佐賀を拠点に公共物や住居の設計を行ってきた男性は、30代のころ、最大3日徹夜で図面を引くこともあるほど、多忙だったと言います。50代を迎えると、同じ業界にいる近い歳の仲間が病などで次々と亡くなっていきました。自身も抱えていた病が悪化し、自分の人生を見つめ直すようになったと言います。
「建築はおよそ百年後には廃棄物になる その設計をするのが私の仕事です。それは人の営みとして致し方ない部分ではあるけども、色々と思うところもありました」
そんな人生の節目で男性が出会ったのが二ホンミツバチでした。
「建築士の私が二ホンミツバチに出会った 運命を感じました」
養蜂を始めて、男性は巣箱の傍に蜂を寄せる花を置いたり、設置場所を工夫したりと熱心に励みました。箱に全く蜂が入らない時期がしばらく続きましたが、それでも男性は努力を続け、数年が経った頃、蜂はようやく入るようになりました。男性は言葉にはならないほど嬉しかったと言います。
より一層、励むようになった男性は、建築士として培ってきたノウハウや分析力を生かし、巣箱の改良や世話の仕方を工夫し、努力を重ねました。そしてついに採蜜の量は村の直売所で販売できるほどに。今では村外から訪れる人たちにも評判の品となっています。
そんな男性の養蜂を村の人たちも見守っています。ある80代の男性は散歩の度に山林に置かれた巣箱の様子を確認してくれています。その男性は、巣箱に昔の暮らしを思い出すのだと言うのです。
「まだ甘味料が貴重だった60年ほど前、私の親父が養蜂して蜂蜜を取っていた それが懐かしくてね」
今、まさに養蜂に取り組む男性は、その話を聞き、結果的に自分がふるさとの味を引き継いでいるのだと自覚したそうです。
「先輩の話に昔のふるさとの暮らしを知って、今は孫が私の蜂蜜を喜んで食べてくれる 養蜂のおかげで、この土地に暮らしていくことに、より豊かを感じるようになりました」
この男性の他にも、三瀬村ではたくさんの人たちが養蜂に励んでいます。
焼きたてのトーストに蜂蜜を塗って食べる度、頭に浮かぶ自然豊かな村の風景。
それは僕にとって、揺るぎない三瀬の味です。





---------------------
2022年9月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
焼きたてのトーストに少し塗って、サラダと淹れたての珈琲でいただくという朝の習慣は、僕が三瀬村ではちみつを取材したころに始まりました。
それはある年の9月、村で養蜂に取り組むという男性を取材で訪ねたことがきっかけでした。季節は採蜜の時期。男性は家の庭に設置した巣箱から蜜を採る作業の真っ最中。まだ暑さの名残りが残る中、彼は奥さんと共に真っ白な防護服をすっぽり被り、巣箱の蓋を開けていました。中には黄金色に輝く二ホンミツバチの巣がぎっしり。飛び回る蜂を刺激しないよう男性はそっと手を伸ばし、巣の状態を確かめます。よく見ると黄金色のところどころに僅かに濃い茶色に染まる部分がありました。
「熟成が進んでいる証拠 薄いところは出来立てなんです」
そう言って男性は太い糸を取出し、巣箱に巻き付けます。巣箱は枠箱が5段ほど重なった構造。その一番上の段のつなぎ目に男性はそっと糸を入れ、反対側に力いっぱい引いて中の巣を切断します。そして奥さんの手を借り、箱を持ち上げると見事に箱ごと巣の一部を切ることに成功しました。
「全部は取らないんですか?」と尋ねると
「蜂が越冬の為、貯めている蜜だから残しておかないと」と言います。
改めて残された巣箱を見ると、その入口では二ホンミツバチが花粉を足に付け、懸命に出入りしていました。それを見て、僕は彼らが厳しい三瀬村の冬を乗り越えるために懸命なのだと、つくづく思いました。
「頻繁に巣箱の世話をしていると、箱による蜂の性格の違いとか、なんとなく分かるようになって、言葉は通じないけど話をしているような感じ」。
時折、男性の指の先には蜂が挨拶するようにそっと止まります。そんな時、男性は手を動かさず、その様子を眺めながら、「何かほっとしますね」と言います。すると蜂は応えるように再び飛んでいくのです。
男性は蜂に「分けてもらった」巣を、部屋に持ち込み、採蜜作業に取り掛かります。包丁を使い、枠箱から外した巣を少しずつ切り分けて、ボウルに敷いたザルに置いていきます。「一気に絞ったら苦みが出るので、こうして三日ほど置き、たれ蜜を取るんです」
作業中、男性は巣の一欠片を口に含み、「すっきりとして甘い 採れたてが楽しめるのは養蜂やっている楽しみよ」と嬉しそうに言いました。
聞けば二ホンミツバチは巣箱から2キロほどの範囲を飛び回っているそうです。その範囲には、脊振山系からの清流に沿って、様々な野草や草花が生い茂り、集落の田畑も広がっています。
「ハチミツの味はまさに村の、この集落の味というわけですよ」
その言葉に、僕は「ふるさとの味」という表現がこれほどぴったりくるものはないと思いました。遥か昔から日本に生息し、江戸時代ごろには養蜂も行われていたと言われている二ホンミツバチ。自然を生かし、その恵みを糧としていただく養蜂に、男性は運命的に出会ったのだと話してくれました。
建築士として佐賀を拠点に公共物や住居の設計を行ってきた男性は、30代のころ、最大3日徹夜で図面を引くこともあるほど、多忙だったと言います。50代を迎えると、同じ業界にいる近い歳の仲間が病などで次々と亡くなっていきました。自身も抱えていた病が悪化し、自分の人生を見つめ直すようになったと言います。
「建築はおよそ百年後には廃棄物になる その設計をするのが私の仕事です。それは人の営みとして致し方ない部分ではあるけども、色々と思うところもありました」
そんな人生の節目で男性が出会ったのが二ホンミツバチでした。
「建築士の私が二ホンミツバチに出会った 運命を感じました」
養蜂を始めて、男性は巣箱の傍に蜂を寄せる花を置いたり、設置場所を工夫したりと熱心に励みました。箱に全く蜂が入らない時期がしばらく続きましたが、それでも男性は努力を続け、数年が経った頃、蜂はようやく入るようになりました。男性は言葉にはならないほど嬉しかったと言います。
より一層、励むようになった男性は、建築士として培ってきたノウハウや分析力を生かし、巣箱の改良や世話の仕方を工夫し、努力を重ねました。そしてついに採蜜の量は村の直売所で販売できるほどに。今では村外から訪れる人たちにも評判の品となっています。
そんな男性の養蜂を村の人たちも見守っています。ある80代の男性は散歩の度に山林に置かれた巣箱の様子を確認してくれています。その男性は、巣箱に昔の暮らしを思い出すのだと言うのです。
「まだ甘味料が貴重だった60年ほど前、私の親父が養蜂して蜂蜜を取っていた それが懐かしくてね」
今、まさに養蜂に取り組む男性は、その話を聞き、結果的に自分がふるさとの味を引き継いでいるのだと自覚したそうです。
「先輩の話に昔のふるさとの暮らしを知って、今は孫が私の蜂蜜を喜んで食べてくれる 養蜂のおかげで、この土地に暮らしていくことに、より豊かを感じるようになりました」
この男性の他にも、三瀬村ではたくさんの人たちが養蜂に励んでいます。
焼きたてのトーストに蜂蜜を塗って食べる度、頭に浮かぶ自然豊かな村の風景。
それは僕にとって、揺るぎない三瀬の味です。





---------------------
2022年9月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
2022年08月01日
夏の三瀬村 ブルーベリーの実り
一年ぶりに来たという、その小学生の兄弟は、たわわに実ったブルーベリーの畑の中を元気よく駆け回っていました。
七月末の週末、三瀬村にあるブルーベリーの観光農園で見かけた光景でした。
小学四年生くらいの兄が自分の背丈ほどの細木の鉢の林をはしゃいですり抜け、時折、立ち止まって、しゃがみこみます。何度も枝に手を伸ばし、何かを掴んだかと思ったら、くるりと後ろを振り向き、後ろでソワソワして待っている小学一年生くらいの小さな妹に何かを言って手のひらを広げさせ、黒く光る粒をそっと掴ませていました。
僕の隣で共にその様子を眺めていた農園の女性が「採れたね〜?」と叫ぶと、二人は笑顔でこちらを振り向き、自分たちの獲物を誇りたい一心で私たちの所まで駆け寄って来て、僕らにめいいっぱい掲げた両手の平に溢れるブルーベリーを披露してくれました。
真夏の強い日差しの中で、豊かな水気にほどよく膨らんだ果実は、その一粒一粒が黒い真珠のように光っていました。
「いっぺんに口に放り込むといいよ」
農園の女性の大胆なアドバイスに背中を押され、その顔つきから意を決したらしい少年は、妹の右手いっぱいの実を左手で雑に掴み取り、いっぺんに口に放り込みました。
クルミで頬を膨らませたリスみたいな顔で、少年は「むふふ」と笑い、それを見た妹も慌てて残り半分を乗せた手のひらを、小さな口より高く上げて、たどたどしく転がり落としていきました。もぐもぐと頬を動かす兄弟の顔は、感想など聞くまでもない喜色満面な様子でした。
長年、三瀬村を取材してきた僕にとって、ブルーベリーといえば三瀬村の夏に欠かせない果物です。
毎年、七月中旬から八月下旬にかけては、村にある観光農園がオープンし、採れたての実を使ったブラマンジェなどのスイーツが味わえます。村のある宿でも、この時期、宿泊すれば畑のブルーベリーを収穫し放題というもてなしを行っています。さらに幾つかの喫茶店や食堂ではブルーベリーを使ったパフェなども楽しめます。どこも隣県、福岡からの常連客が多く、農園に至っては少し早い時期から、「今年のオープンは何日からですか」と問い合わせの電話も少なくないのだとか。
人気の秘密は?作り手の農家さんのやりがいは?そんな取材の果てに僕が見つけたのはブルーベリーに象徴される、村のある魅力でした。
「実りある人生」
それはブルーベリーの花言葉でもあります。
福岡からの常連客は一年のうち、この時期を狙って、毎週のように家族連れで通ってきます。そして収穫だけであっても自ら体験し、その味をその場で感じる「自然に触れる体験」を得ます。農園の人々は土造りに枝の剪定、肥料の調整に草刈りなどの苦労を積み重ね、一年間で二ヶ月足らずの開園期間を迎えます。そんな商売の先に農園の人々が得るのは、常連客がその場で直に表す喜びの感情です。
僕は夏の三瀬で交わり、喜びを分かち合う人々の姿を見つめていると、互いが今、その場で様々なものを得ながらも、一方で各々が普段、求めながらも得られないものへの渇望を抱えている姿もまた想像してしまうのです。
笑顔でブルーベリー園を駆け回っていた兄弟は十年後、どんな感情と共に三瀬の記憶を思い出すのでしょうか。
そんな常連客の喜びの姿を年々、確実に年老いていく村の農園の人々は、どんな思いで見つめ、これから三瀬村で生きていくのでしょうか。
ここで実っているのは果実ばかりではないのかもしれません。



---------------------
2022年8月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
七月末の週末、三瀬村にあるブルーベリーの観光農園で見かけた光景でした。
小学四年生くらいの兄が自分の背丈ほどの細木の鉢の林をはしゃいですり抜け、時折、立ち止まって、しゃがみこみます。何度も枝に手を伸ばし、何かを掴んだかと思ったら、くるりと後ろを振り向き、後ろでソワソワして待っている小学一年生くらいの小さな妹に何かを言って手のひらを広げさせ、黒く光る粒をそっと掴ませていました。
僕の隣で共にその様子を眺めていた農園の女性が「採れたね〜?」と叫ぶと、二人は笑顔でこちらを振り向き、自分たちの獲物を誇りたい一心で私たちの所まで駆け寄って来て、僕らにめいいっぱい掲げた両手の平に溢れるブルーベリーを披露してくれました。
真夏の強い日差しの中で、豊かな水気にほどよく膨らんだ果実は、その一粒一粒が黒い真珠のように光っていました。
「いっぺんに口に放り込むといいよ」
農園の女性の大胆なアドバイスに背中を押され、その顔つきから意を決したらしい少年は、妹の右手いっぱいの実を左手で雑に掴み取り、いっぺんに口に放り込みました。
クルミで頬を膨らませたリスみたいな顔で、少年は「むふふ」と笑い、それを見た妹も慌てて残り半分を乗せた手のひらを、小さな口より高く上げて、たどたどしく転がり落としていきました。もぐもぐと頬を動かす兄弟の顔は、感想など聞くまでもない喜色満面な様子でした。
長年、三瀬村を取材してきた僕にとって、ブルーベリーといえば三瀬村の夏に欠かせない果物です。
毎年、七月中旬から八月下旬にかけては、村にある観光農園がオープンし、採れたての実を使ったブラマンジェなどのスイーツが味わえます。村のある宿でも、この時期、宿泊すれば畑のブルーベリーを収穫し放題というもてなしを行っています。さらに幾つかの喫茶店や食堂ではブルーベリーを使ったパフェなども楽しめます。どこも隣県、福岡からの常連客が多く、農園に至っては少し早い時期から、「今年のオープンは何日からですか」と問い合わせの電話も少なくないのだとか。
人気の秘密は?作り手の農家さんのやりがいは?そんな取材の果てに僕が見つけたのはブルーベリーに象徴される、村のある魅力でした。
「実りある人生」
それはブルーベリーの花言葉でもあります。
福岡からの常連客は一年のうち、この時期を狙って、毎週のように家族連れで通ってきます。そして収穫だけであっても自ら体験し、その味をその場で感じる「自然に触れる体験」を得ます。農園の人々は土造りに枝の剪定、肥料の調整に草刈りなどの苦労を積み重ね、一年間で二ヶ月足らずの開園期間を迎えます。そんな商売の先に農園の人々が得るのは、常連客がその場で直に表す喜びの感情です。
僕は夏の三瀬で交わり、喜びを分かち合う人々の姿を見つめていると、互いが今、その場で様々なものを得ながらも、一方で各々が普段、求めながらも得られないものへの渇望を抱えている姿もまた想像してしまうのです。
笑顔でブルーベリー園を駆け回っていた兄弟は十年後、どんな感情と共に三瀬の記憶を思い出すのでしょうか。
そんな常連客の喜びの姿を年々、確実に年老いていく村の農園の人々は、どんな思いで見つめ、これから三瀬村で生きていくのでしょうか。
ここで実っているのは果実ばかりではないのかもしれません。



---------------------
2022年8月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
2022年07月01日
三瀬村 夏の兆し
ある薄曇りの日、六月の昼間でした。
僕は北山ダムを周遊するサイクリングロードの一角に設けられたベンチに座り、ぼんやりと湖を眺めていました。ヘラブナの産卵の季節も終わり、湖には釣り客のボートはほとんどありませんでした。
湖は空梅雨の中、これから始まる佐賀平野の農業に備え、八十パーセント以上の水位となり、湖は広葉樹の木々に触れんばかりの水に満たされていました。
この日はたまたま平日だったせいか、レンタサイクルやスワンボートを借りて楽しむ人もほとんどなく、ただダムサイトの周辺で動く作業服姿の人影が数人。これらはその時の僕の心持と不思議なくらい似つかわしい景色でした。
僕は休日であるにも関わらず、特に何かを楽しみたいという動機がわかず、かといって今、住んでいる佐賀駅の周辺の自宅にじっとしているのもなんだか無駄なように思えて、この湖を訪れ、目的もなく湖を眺めていたのでした。
しばらくするとエンジン音が聞こえてきました。僕がかすかに心の寛ぎを感じながら音の方に目を向けると、ボートを操りながら釣り客が湖面を走ってきました。時折、ミサゴが飛び回り、木の実が落下し、風が水面に波を作り出す。
そういった湖の景色にさえ無感動になっていた僕はボートの何の変哲もない釣り客に景色の変化を感じ、心が動きました。舞台の主人公として自分の心境を変えてくれるのではないかという期待を抱いたのです。中年男性らしき釣り客は勢いよく、ボートを広葉樹の枝葉が作り出した木陰に滑り込ませ、ロープで結ばれた錨変わりのブロックを下ろすと、竿を伸ばし、釣りを始めました。
僕は持ってきていた水筒のお茶を飲みながらしばらく、その様子を見ていましたが、一行に釣れる気配がありません。僕は次第に、その青いライフジャケットや角ばったエンジンの形から普段住んでいる街中の人工的な環境を連想してしまい、それが嫌になって観察を辞め、バックから文庫本を取出して読み始めました。
しかし、本の内容とは関係なく、文字を追うだけでも様々な街中の記憶がよみがえってしまいます。仕事に追われる毎日、街中に飛び交う人の声や店の音楽の入り混じったノイズ、新聞記事をびっしりと埋め尽くす情報の海。半年近く続いていた息つく暇もない仕事の忙しさや人間関係のストレスに疲れ、この時の僕は自分を騒がす様々な刺激から逃れたいと必死でした。
しかし、一度、そうやって騒がしくなってしまっていた心持は、湖をいくら眺めても、本を読み漁っても解消されません。僕はすぐに本を閉じ、バックにしまおうとしました。
その時でした。目の前から小さな水しぶきが聞こえました。僕が目を上げると先ほどの男性が湖面からピンと釣り糸を引き上げていました。その先には時折、湖面を打つひれが見えます。ヘラブナ?いやバスかもしれない。僕は思わず立ち上がり、小さな歓声を上げていました。遠目ながらも、その釣り客が上半身を前後に揺らし、喜んでいる様子がうかがえました。僕は息をのみ、その刹那に一切を悟った気がしました。この釣り客も普段の忙しい仕事の日々を抜け、釣りを楽しみに来ている一人だ。境遇は僕とそう変わらないのかもしれない。
尾ひれをバタつかせる魚をタモですくう嬉しそうな釣り客と、その周りを飛び回るミサゴ。木の枝から落下する木の実。
湖面をかすかに揺らす風。すべては北山湖の上を一瞬で通り過ぎた景色でしたが、僕の心の中には印象的な一枚の写真として焼き付けられました。僕は休日、この場所に来たことに意味があったことを初めて実感し、得も言われぬ朗らかな気持ちになりました。
同時に、三瀬村に暮らす、ある友人から進められた今の湖の楽しみ方についての話を思い出しました。釣りの目的でなくてもボートを借り、木陰に浮かべてぼんやりするのがよいと。この季節は湖面には虫も少ないし、渡ってくる風も涼しく揺れも心地よい。一日中、そうしているのがいい、と。
人には自分を空にして、環境に身をゆだねることが必要な瞬間があるのだと思います。その環境の自然が豊かであればあるほど、素直にその変化を感じ、喜び、自分を取り戻せるのではないのか。自分も自然の一部であるということを思い出せるのではないか。そんな確信に満ちた思いが内側から湧きあがり、僕はまた再び、この湖を訪れようと心に決めました。
ふと見上げると薄い雲は風に流され、広い抜けるような青空が見え始めていました。揺れる湖面は空梅雨の空の光を反射し、きらめいています。もうすぐ三瀬村に夏が訪れます。




---------------------
2022年7月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
僕は北山ダムを周遊するサイクリングロードの一角に設けられたベンチに座り、ぼんやりと湖を眺めていました。ヘラブナの産卵の季節も終わり、湖には釣り客のボートはほとんどありませんでした。
湖は空梅雨の中、これから始まる佐賀平野の農業に備え、八十パーセント以上の水位となり、湖は広葉樹の木々に触れんばかりの水に満たされていました。
この日はたまたま平日だったせいか、レンタサイクルやスワンボートを借りて楽しむ人もほとんどなく、ただダムサイトの周辺で動く作業服姿の人影が数人。これらはその時の僕の心持と不思議なくらい似つかわしい景色でした。
僕は休日であるにも関わらず、特に何かを楽しみたいという動機がわかず、かといって今、住んでいる佐賀駅の周辺の自宅にじっとしているのもなんだか無駄なように思えて、この湖を訪れ、目的もなく湖を眺めていたのでした。
しばらくするとエンジン音が聞こえてきました。僕がかすかに心の寛ぎを感じながら音の方に目を向けると、ボートを操りながら釣り客が湖面を走ってきました。時折、ミサゴが飛び回り、木の実が落下し、風が水面に波を作り出す。
そういった湖の景色にさえ無感動になっていた僕はボートの何の変哲もない釣り客に景色の変化を感じ、心が動きました。舞台の主人公として自分の心境を変えてくれるのではないかという期待を抱いたのです。中年男性らしき釣り客は勢いよく、ボートを広葉樹の枝葉が作り出した木陰に滑り込ませ、ロープで結ばれた錨変わりのブロックを下ろすと、竿を伸ばし、釣りを始めました。
僕は持ってきていた水筒のお茶を飲みながらしばらく、その様子を見ていましたが、一行に釣れる気配がありません。僕は次第に、その青いライフジャケットや角ばったエンジンの形から普段住んでいる街中の人工的な環境を連想してしまい、それが嫌になって観察を辞め、バックから文庫本を取出して読み始めました。
しかし、本の内容とは関係なく、文字を追うだけでも様々な街中の記憶がよみがえってしまいます。仕事に追われる毎日、街中に飛び交う人の声や店の音楽の入り混じったノイズ、新聞記事をびっしりと埋め尽くす情報の海。半年近く続いていた息つく暇もない仕事の忙しさや人間関係のストレスに疲れ、この時の僕は自分を騒がす様々な刺激から逃れたいと必死でした。
しかし、一度、そうやって騒がしくなってしまっていた心持は、湖をいくら眺めても、本を読み漁っても解消されません。僕はすぐに本を閉じ、バックにしまおうとしました。
その時でした。目の前から小さな水しぶきが聞こえました。僕が目を上げると先ほどの男性が湖面からピンと釣り糸を引き上げていました。その先には時折、湖面を打つひれが見えます。ヘラブナ?いやバスかもしれない。僕は思わず立ち上がり、小さな歓声を上げていました。遠目ながらも、その釣り客が上半身を前後に揺らし、喜んでいる様子がうかがえました。僕は息をのみ、その刹那に一切を悟った気がしました。この釣り客も普段の忙しい仕事の日々を抜け、釣りを楽しみに来ている一人だ。境遇は僕とそう変わらないのかもしれない。
尾ひれをバタつかせる魚をタモですくう嬉しそうな釣り客と、その周りを飛び回るミサゴ。木の枝から落下する木の実。
湖面をかすかに揺らす風。すべては北山湖の上を一瞬で通り過ぎた景色でしたが、僕の心の中には印象的な一枚の写真として焼き付けられました。僕は休日、この場所に来たことに意味があったことを初めて実感し、得も言われぬ朗らかな気持ちになりました。
同時に、三瀬村に暮らす、ある友人から進められた今の湖の楽しみ方についての話を思い出しました。釣りの目的でなくてもボートを借り、木陰に浮かべてぼんやりするのがよいと。この季節は湖面には虫も少ないし、渡ってくる風も涼しく揺れも心地よい。一日中、そうしているのがいい、と。
人には自分を空にして、環境に身をゆだねることが必要な瞬間があるのだと思います。その環境の自然が豊かであればあるほど、素直にその変化を感じ、喜び、自分を取り戻せるのではないのか。自分も自然の一部であるということを思い出せるのではないか。そんな確信に満ちた思いが内側から湧きあがり、僕はまた再び、この湖を訪れようと心に決めました。
ふと見上げると薄い雲は風に流され、広い抜けるような青空が見え始めていました。揺れる湖面は空梅雨の空の光を反射し、きらめいています。もうすぐ三瀬村に夏が訪れます。




---------------------
2022年7月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
2022年06月01日
せせらぎの村 三瀬の祭りに見えたもの
川のせせらぎが三瀬の音だということに気づいたのは、今から4年ほど前のこと。
僕が取材の仕事で村に通い始めて1年が経ったころでした。それは水の里だと言っても過言ではないほど、水が村の人たちの暮らしに密接に結びついていることを知ったからです。
国道263号線をせわしなく行き来する車の騒音の中を歩いていても、村の奥で青い空をピカッと映す田園の傍で休んでいる時も、せせらぎは常に風景の奥にあって、それは知らぬ間に意識の底に入り込んでいるのでした。仕事に疲れ、立ち止まった時、そのせせらぎは意識の水面に浮き上がってきて、心の澱を取り除いてくれます。僕はなんだか無性にうれしくなって川のうねりに手を突っ込んで澄んだ音の源の体温を味わったものでした。
村の人たちにとって水ってどれくらい大事なんだろうか。
僕が当時、話を聞いた村の60代の男性は「畑の野菜なんかを洗うのにいい」と言って、川にザルに入れた里芋をつけていました。つけた傍から泥が流れ落ち、きれいになっていく里芋の一つを拾い上げ、男性は「3時間もつけたら皮まで向ける」と笑って教えてくれました。
彼が小学生のころは母親が川で洗濯もしていたそうです。さらに水は年間7度から9度と大きく水温が変わないため、夏はスイカやラムネを冷やすのにも使っていたとか。その水をある集落ではコンクリート製の枠を作ってため、生活用水にも使っていました。
そんな村の人たちは毎春、冬の積雪量のことを気にします。米や農作物にも欠かせないものだからです。
「今年は雪少なかったなぁ 水が足りるやろうか 上の田んぼは犠牲田にせんといかんかもしれんなぁ」とぼやいたり、
「今年はよう降ったけん、なんも心配いらん」
と喜んだりします。
水は村の人たちの気持ちを毎年、振り回しながらも素知らぬ顔で淡々と川を流れ続けます。
水は火災から村の人たちを守るためにも活用されます。川の堰で貯められているのです。川は村のあちこちに流れているため、貯まった水は防火水槽の役割を果たすのです。
恩恵ばかりのような山水の恵みはしかし、脅威として村の人たちを脅かすものでもあります。昭和38年、大雨が村を襲い、7戸が全壊。3人が亡くなったそうです。
僕が話を聞いた村の男性は当時、小学生低学年。家に土砂が流れ込み、命からがら逃げ伸びた記憶を今でも鮮明に覚えていました。
村には、そんな人々の水への思いが形となって表れている行事があります。100年以上前から受け継がれるとされる「川祭り」という伝統行事です。
春と秋の年に2回、田植え前と稲の収穫後に行われる祭りは水の神様に感謝するもの。わらを使い、佐賀で治水の神様と伝えられる成富兵庫茂安(なりどみひょうごしげやす)の名にちなんだ「兵庫皿」という皿を作り、竹で川の袂に作った神棚に置きます。
そこには水の恵みによってとれた農作物の料理や、水にちなんだものということで、ちりめんじゃこや貝などを混ぜ込んだ「ごっくうさん」というおにぎりを供えるのです。
お神酒をささげて川に手を合わせ、供えたものを食べることで、その力を分けてもらう。祭りの一連の儀式を執り行うとき、村人の顔からは、つい先ほどまでの朗らかな表情は消え、厳かな神様への畏敬の一念があらわれます。その姿はとても神聖で僕はただじっとカメラを回していることに罪悪感を覚えながら、ことの成り行きを黙って見届けることしたできませんでした。
川祭りの取材を通して、考えるようになったことがあります。
水の恵みが大切であることは、たとえ街中に住んでいても同じこと。ただ「自然の恩恵であり、恐怖をもたらすものである」ことは、マンションの一室に住んでいる僕にとってはひどく遠い世界の出来事のように感じてしまいます。
いくら意識しても、すぐに意識の底に沈んでしまうのです。しかし、村に暮らす人たちは文字通り、「肌で」その恩恵や恐怖といったものを感じています。年間を通し、暮らしのあらゆる場面で恵みをもたらしてくれるもの。脅威と恐怖をもたらすもの。そんな水と日々、密接に関わる中で村の人たちは、その存在の自分たちにとっての意味を深く感じ取っています。
そのせいか、当たり前のように村の人たちが口にする「水への畏怖の念」という言葉の響きは重く、強いものとして僕の中にも響きました。それは村の人たちにとって抽象的な言葉の表現などではなく、まぎれもない事実の積み重ねの経験から生まれる感情だからです。
変わらぬせせらぎの音を聞きながら6月、僕は再び三瀬村に遊びに行きました。
あたりには青い空を鏡のように映した田んぼが広がっています。思わず水路の傍にしゃがみ込み、僕は流れへと手を伸ばしました。山の冷気をまとった水の体温を指の先に感じ、僕はそのままじっと指先をつけたまま、しばらく水の感触を味わいました。山からの恩恵は変わらず村の田畑や人々の暮らしを潤している。その水は平野に住む僕の暮らしの中にも確実に恩恵をもたらしてくれている。そのつながりを僕は三瀬村との出会いの中で、ようやく実感として持てたような気がしたのです。






---------------------
2022年6月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
僕が取材の仕事で村に通い始めて1年が経ったころでした。それは水の里だと言っても過言ではないほど、水が村の人たちの暮らしに密接に結びついていることを知ったからです。
国道263号線をせわしなく行き来する車の騒音の中を歩いていても、村の奥で青い空をピカッと映す田園の傍で休んでいる時も、せせらぎは常に風景の奥にあって、それは知らぬ間に意識の底に入り込んでいるのでした。仕事に疲れ、立ち止まった時、そのせせらぎは意識の水面に浮き上がってきて、心の澱を取り除いてくれます。僕はなんだか無性にうれしくなって川のうねりに手を突っ込んで澄んだ音の源の体温を味わったものでした。
村の人たちにとって水ってどれくらい大事なんだろうか。
僕が当時、話を聞いた村の60代の男性は「畑の野菜なんかを洗うのにいい」と言って、川にザルに入れた里芋をつけていました。つけた傍から泥が流れ落ち、きれいになっていく里芋の一つを拾い上げ、男性は「3時間もつけたら皮まで向ける」と笑って教えてくれました。
彼が小学生のころは母親が川で洗濯もしていたそうです。さらに水は年間7度から9度と大きく水温が変わないため、夏はスイカやラムネを冷やすのにも使っていたとか。その水をある集落ではコンクリート製の枠を作ってため、生活用水にも使っていました。
そんな村の人たちは毎春、冬の積雪量のことを気にします。米や農作物にも欠かせないものだからです。
「今年は雪少なかったなぁ 水が足りるやろうか 上の田んぼは犠牲田にせんといかんかもしれんなぁ」とぼやいたり、
「今年はよう降ったけん、なんも心配いらん」
と喜んだりします。
水は村の人たちの気持ちを毎年、振り回しながらも素知らぬ顔で淡々と川を流れ続けます。
水は火災から村の人たちを守るためにも活用されます。川の堰で貯められているのです。川は村のあちこちに流れているため、貯まった水は防火水槽の役割を果たすのです。
恩恵ばかりのような山水の恵みはしかし、脅威として村の人たちを脅かすものでもあります。昭和38年、大雨が村を襲い、7戸が全壊。3人が亡くなったそうです。
僕が話を聞いた村の男性は当時、小学生低学年。家に土砂が流れ込み、命からがら逃げ伸びた記憶を今でも鮮明に覚えていました。
村には、そんな人々の水への思いが形となって表れている行事があります。100年以上前から受け継がれるとされる「川祭り」という伝統行事です。
春と秋の年に2回、田植え前と稲の収穫後に行われる祭りは水の神様に感謝するもの。わらを使い、佐賀で治水の神様と伝えられる成富兵庫茂安(なりどみひょうごしげやす)の名にちなんだ「兵庫皿」という皿を作り、竹で川の袂に作った神棚に置きます。
そこには水の恵みによってとれた農作物の料理や、水にちなんだものということで、ちりめんじゃこや貝などを混ぜ込んだ「ごっくうさん」というおにぎりを供えるのです。
お神酒をささげて川に手を合わせ、供えたものを食べることで、その力を分けてもらう。祭りの一連の儀式を執り行うとき、村人の顔からは、つい先ほどまでの朗らかな表情は消え、厳かな神様への畏敬の一念があらわれます。その姿はとても神聖で僕はただじっとカメラを回していることに罪悪感を覚えながら、ことの成り行きを黙って見届けることしたできませんでした。
川祭りの取材を通して、考えるようになったことがあります。
水の恵みが大切であることは、たとえ街中に住んでいても同じこと。ただ「自然の恩恵であり、恐怖をもたらすものである」ことは、マンションの一室に住んでいる僕にとってはひどく遠い世界の出来事のように感じてしまいます。
いくら意識しても、すぐに意識の底に沈んでしまうのです。しかし、村に暮らす人たちは文字通り、「肌で」その恩恵や恐怖といったものを感じています。年間を通し、暮らしのあらゆる場面で恵みをもたらしてくれるもの。脅威と恐怖をもたらすもの。そんな水と日々、密接に関わる中で村の人たちは、その存在の自分たちにとっての意味を深く感じ取っています。
そのせいか、当たり前のように村の人たちが口にする「水への畏怖の念」という言葉の響きは重く、強いものとして僕の中にも響きました。それは村の人たちにとって抽象的な言葉の表現などではなく、まぎれもない事実の積み重ねの経験から生まれる感情だからです。
変わらぬせせらぎの音を聞きながら6月、僕は再び三瀬村に遊びに行きました。
あたりには青い空を鏡のように映した田んぼが広がっています。思わず水路の傍にしゃがみ込み、僕は流れへと手を伸ばしました。山の冷気をまとった水の体温を指の先に感じ、僕はそのままじっと指先をつけたまま、しばらく水の感触を味わいました。山からの恩恵は変わらず村の田畑や人々の暮らしを潤している。その水は平野に住む僕の暮らしの中にも確実に恩恵をもたらしてくれている。そのつながりを僕は三瀬村との出会いの中で、ようやく実感として持てたような気がしたのです。






---------------------
2022年6月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
2022年05月01日
受け継がれていく故郷の餅とまんじゅう
ふるさとの味が一つ、なくなるかもしれない。
突然、そんなニュースを聞いて、僕が井手野の集落を尋ねたのは 2022年3月の中旬ごろ。早朝の事でした。
およそ470mと村で標高が最も高い場所にある、この集落はとても冷え込んでいて朝の5時ごろは真っ暗。静かな山の闇の中にポツンと灯る加工所の窓の明かりに妙な懐かしさを感じ、吸い寄せられるように扉を開きました。中からはゴンゴンゴンと大型の機械が動く音と共にたくさんの人の動く気配がします。
「おはようございます」
と僕が声をかけると
「おお~」、「来たね~」
と様々なおばちゃんたちの声がサラウンドで聞こえてきました。
妙に嬉しくなり、無意識に中に入るとかつて訪れた時と変わらず、7人のおばちゃんたちが加工所の所々で餅とまんじゅう作りに励んでいました。
「なくなるって聞いたんですけど」。
「休業ね休業 まあとにかく中に入らんね」。
僕は促されるままに中に入り、久しぶりにその賑やかな餅加工の場の空気に触れました。
餅つき機がつく餅を確認する人。機械が次々と切り出すつきたて餅を巧みに広げ、次々にあんこを包んで丸めていく人。
突いてから時間を置きすぎたり、もたもたしていると餅が固くなったり、効率が落ちたりしてしまいます。おばちゃんたちは手のひらと指先を器用に動かし、数秒でさっと餡を餅の中に包み込みます。その技はまんじゅうの生地におからを包む時にもいかんなく発揮されます。言葉で書くのも難しい、写真で撮影しても伝えにくい、目の前でよく観察しながら真似し、習い、失敗を繰り返し、経験を積まないと会得できない匠の技です。
出来上がった餅やまんじゅうはパック詰めされ、ラベルが張られていきます。
おばちゃんの一人が「今日は誕生餅がある」と言って大きな鏡餅も見せてくれました。
1歳の子が餅踏みに使うものだそうで、傍には茹でた小豆が添えてありました。踏むときに小豆を餅の上にまぶして踏むことで、「でこぼこ道を歩いていけるくらい強い子に育つように」という願いを込めるそうです。「私たちが作る最後の誕生餅よ」と物悲しそうにつぶやくおばちゃんの言葉が妙に記憶に焼き付きました。
この加工所は昭和61年、集落の女性たちの生きがいづくりにと始まり、以来36年もの間、営まれてきました。酒まんじゅうを原点によもぎもち、おからまんじゅうなど、作られてきた加工品は実に15種類以上。特にかつて作っていたという玄米餅は自慢の逸品。もち米の玄米を発芽させて作ったもので県内の食のコンテストで最優秀賞を受賞したこともありました。
「自分たちで育てた餅米のおいしさを伝える為に私たちはやってきたんだよね」。
餅を丸めながら、おばちゃんたちは実に楽しそうに自分たちの軌跡を語ります。
そんな加工品の餅やまんじゅうは直売所ばかりではなく、保育園の子どもたちのおやつや年末の鏡餅など、様々な村の暮らしの場面で親しまれてきたのです。
作業がひと段落した頃、僕はずっと尋ねるタイミングをうかがっていた質問をおばちゃんに投げかけました。
「やめるんですか?」。
「休業よ 一応ね」。
聞くと今、加工所で働くおばちゃんたちの平均年齢は78歳。そろそろ体力的にも辛くなってきたのだと言います。3年ほど前にも一度、高齢化の為、加工所は存続に揺れたことがありましたが、その時は活動する日を週2回ほどに減らしてなんとか存続することにしました。しかし、さらに月日が経ち、とうとう継続は難しいという話になったそうです。
「いつ誰が体調を崩して出来なくなるか分からないからね そうなったら商品として出しているからお客さんに迷惑かける」。
「残念ですね 僕もショックです」
と正直な感想を告げると、「そう言ってくれる人が多いのよ」と言って、おばちゃんは加工所の留守電を聞かせてくれました。
そこには常連客らしい女性の声で「やめないでほしいです せめて加工所の味を若い人に引き継いでほしい」という声が入っていました。
「みんなから言われる ありがたいけど相当、みんなで考えた結果だから」
と少し寂しそうにおばちゃんは笑いました。
「でもね」と言っておばちゃんは言葉を続けます。
「休業にしたの 廃業じゃないの休業にしていれば誰かやりたい時に教えたり、何かあれば再開したりと希望が持てるでしょう?」。
毎週、土曜日、加工所におばちゃんたちの手伝いに来ている女性がいます。30代の移住者で、おばちゃんが声をかけたのをきっかけに餅やまんじゅう作りに興味をもち、4年ほど前から朝5時の出勤にも関わらず、手伝いに通っています。
「彼女も大分、餅まるめもうまくなったしね 糀を託そうかと思って」
餅を懸命に丸める彼女を見ながら、おばちゃんは冷蔵庫から容器を取り出しました。加工所の味の原点、さけまんじゅうの種である糀です。おばちゃんたちが井手野集落で育てた米を炊いて糀とぬるま湯で混ぜ、発酵させながら育ててきたもの。失敗を繰り返してながら育て、取り出したこの糀は4年前から引き継いできたものだと言います。
その作り方を女性に丁寧に教えながら、おばちゃんは、
「仕事では難しかろうけど、家でも作ってみてよ ふるさとの味を少しでも引き継いでくれれば」と思いも伝えます。
女性は泣きそうになりながら、「大事にしていきたい」とおばちゃんの思いに答えていました。
僕はこれまで幾度も賑やかに、いかにも楽しそうにおばちゃんたちが餅やまんじゅう作りに励む姿を見てきました。それは朝4時から作業する大変さを感じさせないほどの朗らかで明るい姿でした。一つの場所、一つの活動がなくなることを寂しいと感じずにはいられませんが、そんな中でも明るい兆しはあります。
おばちゃんたちの味とその元気な姿を覚えている人たちが確実にいることです。願わくばその情景と共におばちゃんたちの味と思いがこれからも受け継がれていってほしいと思います。






---------------------
2022年5月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
突然、そんなニュースを聞いて、僕が井手野の集落を尋ねたのは 2022年3月の中旬ごろ。早朝の事でした。
およそ470mと村で標高が最も高い場所にある、この集落はとても冷え込んでいて朝の5時ごろは真っ暗。静かな山の闇の中にポツンと灯る加工所の窓の明かりに妙な懐かしさを感じ、吸い寄せられるように扉を開きました。中からはゴンゴンゴンと大型の機械が動く音と共にたくさんの人の動く気配がします。
「おはようございます」
と僕が声をかけると
「おお~」、「来たね~」
と様々なおばちゃんたちの声がサラウンドで聞こえてきました。
妙に嬉しくなり、無意識に中に入るとかつて訪れた時と変わらず、7人のおばちゃんたちが加工所の所々で餅とまんじゅう作りに励んでいました。
「なくなるって聞いたんですけど」。
「休業ね休業 まあとにかく中に入らんね」。
僕は促されるままに中に入り、久しぶりにその賑やかな餅加工の場の空気に触れました。
餅つき機がつく餅を確認する人。機械が次々と切り出すつきたて餅を巧みに広げ、次々にあんこを包んで丸めていく人。
突いてから時間を置きすぎたり、もたもたしていると餅が固くなったり、効率が落ちたりしてしまいます。おばちゃんたちは手のひらと指先を器用に動かし、数秒でさっと餡を餅の中に包み込みます。その技はまんじゅうの生地におからを包む時にもいかんなく発揮されます。言葉で書くのも難しい、写真で撮影しても伝えにくい、目の前でよく観察しながら真似し、習い、失敗を繰り返し、経験を積まないと会得できない匠の技です。
出来上がった餅やまんじゅうはパック詰めされ、ラベルが張られていきます。
おばちゃんの一人が「今日は誕生餅がある」と言って大きな鏡餅も見せてくれました。
1歳の子が餅踏みに使うものだそうで、傍には茹でた小豆が添えてありました。踏むときに小豆を餅の上にまぶして踏むことで、「でこぼこ道を歩いていけるくらい強い子に育つように」という願いを込めるそうです。「私たちが作る最後の誕生餅よ」と物悲しそうにつぶやくおばちゃんの言葉が妙に記憶に焼き付きました。
この加工所は昭和61年、集落の女性たちの生きがいづくりにと始まり、以来36年もの間、営まれてきました。酒まんじゅうを原点によもぎもち、おからまんじゅうなど、作られてきた加工品は実に15種類以上。特にかつて作っていたという玄米餅は自慢の逸品。もち米の玄米を発芽させて作ったもので県内の食のコンテストで最優秀賞を受賞したこともありました。
「自分たちで育てた餅米のおいしさを伝える為に私たちはやってきたんだよね」。
餅を丸めながら、おばちゃんたちは実に楽しそうに自分たちの軌跡を語ります。
そんな加工品の餅やまんじゅうは直売所ばかりではなく、保育園の子どもたちのおやつや年末の鏡餅など、様々な村の暮らしの場面で親しまれてきたのです。
作業がひと段落した頃、僕はずっと尋ねるタイミングをうかがっていた質問をおばちゃんに投げかけました。
「やめるんですか?」。
「休業よ 一応ね」。
聞くと今、加工所で働くおばちゃんたちの平均年齢は78歳。そろそろ体力的にも辛くなってきたのだと言います。3年ほど前にも一度、高齢化の為、加工所は存続に揺れたことがありましたが、その時は活動する日を週2回ほどに減らしてなんとか存続することにしました。しかし、さらに月日が経ち、とうとう継続は難しいという話になったそうです。
「いつ誰が体調を崩して出来なくなるか分からないからね そうなったら商品として出しているからお客さんに迷惑かける」。
「残念ですね 僕もショックです」
と正直な感想を告げると、「そう言ってくれる人が多いのよ」と言って、おばちゃんは加工所の留守電を聞かせてくれました。
そこには常連客らしい女性の声で「やめないでほしいです せめて加工所の味を若い人に引き継いでほしい」という声が入っていました。
「みんなから言われる ありがたいけど相当、みんなで考えた結果だから」
と少し寂しそうにおばちゃんは笑いました。
「でもね」と言っておばちゃんは言葉を続けます。
「休業にしたの 廃業じゃないの休業にしていれば誰かやりたい時に教えたり、何かあれば再開したりと希望が持てるでしょう?」。
毎週、土曜日、加工所におばちゃんたちの手伝いに来ている女性がいます。30代の移住者で、おばちゃんが声をかけたのをきっかけに餅やまんじゅう作りに興味をもち、4年ほど前から朝5時の出勤にも関わらず、手伝いに通っています。
「彼女も大分、餅まるめもうまくなったしね 糀を託そうかと思って」
餅を懸命に丸める彼女を見ながら、おばちゃんは冷蔵庫から容器を取り出しました。加工所の味の原点、さけまんじゅうの種である糀です。おばちゃんたちが井手野集落で育てた米を炊いて糀とぬるま湯で混ぜ、発酵させながら育ててきたもの。失敗を繰り返してながら育て、取り出したこの糀は4年前から引き継いできたものだと言います。
その作り方を女性に丁寧に教えながら、おばちゃんは、
「仕事では難しかろうけど、家でも作ってみてよ ふるさとの味を少しでも引き継いでくれれば」と思いも伝えます。
女性は泣きそうになりながら、「大事にしていきたい」とおばちゃんの思いに答えていました。
僕はこれまで幾度も賑やかに、いかにも楽しそうにおばちゃんたちが餅やまんじゅう作りに励む姿を見てきました。それは朝4時から作業する大変さを感じさせないほどの朗らかで明るい姿でした。一つの場所、一つの活動がなくなることを寂しいと感じずにはいられませんが、そんな中でも明るい兆しはあります。
おばちゃんたちの味とその元気な姿を覚えている人たちが確実にいることです。願わくばその情景と共におばちゃんたちの味と思いがこれからも受け継がれていってほしいと思います。






---------------------
2022年5月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
2022年04月02日
三瀬村 人と山の色彩
うぐいすらしき鳴き声と共に3月末の山里は花の匂いに満ちていました。三瀬村の春で す。
国道263号沿いを車で通っていると、小学校や中学校の前には薄紫やピンクの紫桜や控 えめな黄色のすいれんがこちらに顔を向けています。まるで迎えられているようで、僕はこ の季節、この道を通る度に嬉しくなります。
村に通っているうちに、僕はこの花々の植え込みを始めた男性に出会いました。当時、村 の老人クラブの会長を務めていた80代後半の男性です。
「三瀬村は観光地だから名所みたいなものを作れないかと きれいな花のある村というこ とではじめのですよ」
男性は続けて、かつての村の思い出を語ってくれました。
「昔は雑木の生い茂る山の裾野にわらびを取りに行ったり、川で石を並べて魚とりの罠を 作ったり、それを夕食のおかずにしたり そんな山でたくさんの友達と遊んだり」。
目を細 めながら話す男性はとても誇らしげで、その様子から、僕はどれだけこの人が村を愛してい るかを感じることができました。 しかし男性は21歳の時、就職の為、当時まだ発足したばかりだった警察予備隊に入隊。 故郷を離れることになります。その後、高度経済成長期が訪れ、男性が長い年月を経て故郷 に戻った時、村は大きく変わってしまっていたと言います。
雑木の森は杉ヒノキの人工林に 変わり、道路近くまで迫っていました。
川も魚が少なくなり、故郷に残っていたはずの友達 の多くは病などで施設に入っていたり、亡くなっていたりして会うことさえ難しくなって いたと言います。
その時、男性は寂しさを感じると同時に「昔の誇れる故郷を取り戻したい」 と強く思い、「花いっぱい活動」という取り組みを始めることを決めました。
「花を見て腹を立てる人はいないと思いますので」
朗らかに笑う男性の表情が僕は今で も忘れられません。
その後、男性は老人クラブに声をかけ、小中学校の前や車通りの多い国道263号線沿い にたくさんの花を植えました。
僕が聞いただけでもあじさいを800株、芝桜5000株、 すいせんは2万2000株にものぼると言います。
男性の情熱に惹かれ、村の人たちは懸命 に株の植え込みや草取りなどの手入れを行い続け、およそ20年。手入れをする年配の人た ちも、その花が咲く通学路を通う子供たちも春に咲く花々の姿に自分たちの故郷への誇り を感じるようになりました。
近年、男性は亡くなられましたが、その思いは今も村の人たちの中に引き継がれています。 それは何気ない風景を見ると感じることが出来ます。
スイセンなどの花は畑の一角に、集落 の公民館の脇に、そして家の庭に積んである肥料袋の傍や石垣にも植えられ、村の暮らしを そっと彩っています。 仕事の合間に花を楽しみながら村を歩いていると、そんな庭先の花を嬉しそうに眺めて いる年配の女性に出会いました。
その女性は
「あの人が老人クラブなんかで株を配っていた だからみんな持って帰って 植えているんよ」
と教えてくれました。
村の人たちが故郷の為、懸命に植えてきた花々の周りには、それを見守るように菜の花や 山桜など山の花々が咲き誇っています。
その情景はそこに暮らす人達はもちろん、訪れる人 たちの心も豊かさにしてくれています。
男性が特に熱心に植えていた芝桜の花言葉は「合意」。
男性から始まった村の人たちの意 志が一つとなって、村に鮮やかな春の彩という豊かさを与えてくれているのだと僕は思い ます。






---------------------
2022年4月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
国道263号沿いを車で通っていると、小学校や中学校の前には薄紫やピンクの紫桜や控 えめな黄色のすいれんがこちらに顔を向けています。まるで迎えられているようで、僕はこ の季節、この道を通る度に嬉しくなります。
村に通っているうちに、僕はこの花々の植え込みを始めた男性に出会いました。当時、村 の老人クラブの会長を務めていた80代後半の男性です。
「三瀬村は観光地だから名所みたいなものを作れないかと きれいな花のある村というこ とではじめのですよ」
男性は続けて、かつての村の思い出を語ってくれました。
「昔は雑木の生い茂る山の裾野にわらびを取りに行ったり、川で石を並べて魚とりの罠を 作ったり、それを夕食のおかずにしたり そんな山でたくさんの友達と遊んだり」。
目を細 めながら話す男性はとても誇らしげで、その様子から、僕はどれだけこの人が村を愛してい るかを感じることができました。 しかし男性は21歳の時、就職の為、当時まだ発足したばかりだった警察予備隊に入隊。 故郷を離れることになります。その後、高度経済成長期が訪れ、男性が長い年月を経て故郷 に戻った時、村は大きく変わってしまっていたと言います。
雑木の森は杉ヒノキの人工林に 変わり、道路近くまで迫っていました。
川も魚が少なくなり、故郷に残っていたはずの友達 の多くは病などで施設に入っていたり、亡くなっていたりして会うことさえ難しくなって いたと言います。
その時、男性は寂しさを感じると同時に「昔の誇れる故郷を取り戻したい」 と強く思い、「花いっぱい活動」という取り組みを始めることを決めました。
「花を見て腹を立てる人はいないと思いますので」
朗らかに笑う男性の表情が僕は今で も忘れられません。
その後、男性は老人クラブに声をかけ、小中学校の前や車通りの多い国道263号線沿い にたくさんの花を植えました。
僕が聞いただけでもあじさいを800株、芝桜5000株、 すいせんは2万2000株にものぼると言います。
男性の情熱に惹かれ、村の人たちは懸命 に株の植え込みや草取りなどの手入れを行い続け、およそ20年。手入れをする年配の人た ちも、その花が咲く通学路を通う子供たちも春に咲く花々の姿に自分たちの故郷への誇り を感じるようになりました。
近年、男性は亡くなられましたが、その思いは今も村の人たちの中に引き継がれています。 それは何気ない風景を見ると感じることが出来ます。
スイセンなどの花は畑の一角に、集落 の公民館の脇に、そして家の庭に積んである肥料袋の傍や石垣にも植えられ、村の暮らしを そっと彩っています。 仕事の合間に花を楽しみながら村を歩いていると、そんな庭先の花を嬉しそうに眺めて いる年配の女性に出会いました。
その女性は
「あの人が老人クラブなんかで株を配っていた だからみんな持って帰って 植えているんよ」
と教えてくれました。
村の人たちが故郷の為、懸命に植えてきた花々の周りには、それを見守るように菜の花や 山桜など山の花々が咲き誇っています。
その情景はそこに暮らす人達はもちろん、訪れる人 たちの心も豊かさにしてくれています。
男性が特に熱心に植えていた芝桜の花言葉は「合意」。
男性から始まった村の人たちの意 志が一つとなって、村に鮮やかな春の彩という豊かさを与えてくれているのだと僕は思い ます。






---------------------
2022年4月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com