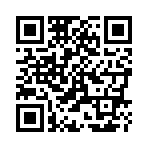2022年04月15日
北山ダムのワカサギ釣り(3)
北山ダムのワカサギ釣り(3)
さて、前回の続きから
ワカサギ釣りは、一番下にオモリがついた5本バリの仕掛けを湖底まで落として、リールを少し巻く。
ボートハウスの篠原さんの教えでは、この時期(1月はじめ)のワカサギは底を泳いでいるということみたいだ。
釣りは、魚が水面近くを泳いでいるのか、底を泳いでいるのか、真ん中あたりを泳いでいるのかを知らないとならない。
魚が泳いでる層のことをタナ(棚)という。その日、その時間に目当ての魚が泳いでいるタナを探り当てるのが、釣りの基本的なコツというか、釣るために必要な条件となる。
魚の種類や季節や水温によっても違うので、目当ての魚の棚がどこなのかは、その場所で釣り馴れている人に訊いておくのも準備のひとつだし、当日、仕掛けを底につけたり、底から五十センチくらい上げたり、中ほどまで上げたりして、アタリを見ながら、タナを探ることが重要だ。
と、そのくらいのことは小学生のときから鮒釣りに親しんでいたので、判っていた。
寒空の中、ボートにゆらりゆらりと揺られながら、アタリを待つ。
玉ウキが、水面に浮かんでいる。
このウキが水面に姿を消した瞬間に、竿を握っている左腕の肘から先を曲げて、上に立てて、竿先を上げる。
するとアタリにアワセ(合わせ)た格好になり、ワカサギが餌を吸い込んでいる口に針先がひっかかる、というイメージである。
頭の中で、いつでも来い、と思いながらシュミレーションをした。
・
・
三分経過。
・
・
うんともすんとも言わない。
餌だけ取られたかな? 釣りは久しぶりで、腕も感覚も鈍っていることだし、もしかするとアタリを見過ごしたかな?
と思って、リールを巻いた。
水面から仕掛けが出てきた。
餌(サシ虫)が5本とも付いている。しかもピンク色もまだ鮮やかだ。ワカサギが餌をつついた形跡もない。。
ほう。なるほど。
第一投目で、アタリが来るとはもちろん思ってはいないのだが。
五分くらいは普通に我慢しないとならない釣りなのかな?
一投してどのくらい待ってアタリがなかったら、餌を替えたほうがいいとか、そういうのが判らない。
じっと待ったほうがいいいのか? それとも、投入する場所を替えたり、ちょこちょこ餌を替えたりしたほうがいいのか?
タナや、ワカサギの居場所を探るためにも、釣り始めはあまり長く待たずに動かしたほうがいいだろう。
ということで、三分くらいを限度に、アタリがなければリールを巻いて、投入を繰り返すことにした。
仕掛けはうんともすんともいわない。
樋口さんはどうだろうか? と思い、振り向いて訊いてみた。
「樋口さん、アタリどうですか?」
樋口さんが半笑いの顔で、首を横に振った。
空は相変わらず曇天である。灰色の濃さが増したような気がする。
なんだか雲行きが怪しくなってきたなあ。。
続きはまた次回。
---------------------
2022年4月15日
川浪秀之(Webプロデューサー、作家)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
さて、前回の続きから
ワカサギ釣りは、一番下にオモリがついた5本バリの仕掛けを湖底まで落として、リールを少し巻く。
ボートハウスの篠原さんの教えでは、この時期(1月はじめ)のワカサギは底を泳いでいるということみたいだ。
釣りは、魚が水面近くを泳いでいるのか、底を泳いでいるのか、真ん中あたりを泳いでいるのかを知らないとならない。
魚が泳いでる層のことをタナ(棚)という。その日、その時間に目当ての魚が泳いでいるタナを探り当てるのが、釣りの基本的なコツというか、釣るために必要な条件となる。
魚の種類や季節や水温によっても違うので、目当ての魚の棚がどこなのかは、その場所で釣り馴れている人に訊いておくのも準備のひとつだし、当日、仕掛けを底につけたり、底から五十センチくらい上げたり、中ほどまで上げたりして、アタリを見ながら、タナを探ることが重要だ。
と、そのくらいのことは小学生のときから鮒釣りに親しんでいたので、判っていた。
寒空の中、ボートにゆらりゆらりと揺られながら、アタリを待つ。
玉ウキが、水面に浮かんでいる。
このウキが水面に姿を消した瞬間に、竿を握っている左腕の肘から先を曲げて、上に立てて、竿先を上げる。
するとアタリにアワセ(合わせ)た格好になり、ワカサギが餌を吸い込んでいる口に針先がひっかかる、というイメージである。
頭の中で、いつでも来い、と思いながらシュミレーションをした。
・
・
三分経過。
・
・
うんともすんとも言わない。
餌だけ取られたかな? 釣りは久しぶりで、腕も感覚も鈍っていることだし、もしかするとアタリを見過ごしたかな?
と思って、リールを巻いた。
水面から仕掛けが出てきた。
餌(サシ虫)が5本とも付いている。しかもピンク色もまだ鮮やかだ。ワカサギが餌をつついた形跡もない。。
ほう。なるほど。
第一投目で、アタリが来るとはもちろん思ってはいないのだが。
五分くらいは普通に我慢しないとならない釣りなのかな?
一投してどのくらい待ってアタリがなかったら、餌を替えたほうがいいとか、そういうのが判らない。
じっと待ったほうがいいいのか? それとも、投入する場所を替えたり、ちょこちょこ餌を替えたりしたほうがいいのか?
タナや、ワカサギの居場所を探るためにも、釣り始めはあまり長く待たずに動かしたほうがいいだろう。
ということで、三分くらいを限度に、アタリがなければリールを巻いて、投入を繰り返すことにした。
仕掛けはうんともすんともいわない。
樋口さんはどうだろうか? と思い、振り向いて訊いてみた。
「樋口さん、アタリどうですか?」
樋口さんが半笑いの顔で、首を横に振った。
空は相変わらず曇天である。灰色の濃さが増したような気がする。
なんだか雲行きが怪しくなってきたなあ。。
続きはまた次回。
---------------------
2022年4月15日
川浪秀之(Webプロデューサー、作家)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
2022年04月10日
古代から国際的な三瀬村
古代から国際的な三瀬村
佐賀県の霊峰・天山の頂上から北を臨むと、まるで洗濯板(古い!)のように次々と山並みが見られ、一番北には右から脊振山、金山、井原山、雷山などが見通せます。太古の平原が北側から徐々に盛り上がって脊振山系がつくられたことがよくわかります。三瀬村はこうした山々の一角にある盆地であることは皆様ご承知の通りです。
さてそこで、この三瀬村がそんな単なる山村ではなく、古代から極めて国際的な場所であったということを「ロマン」を交えて記してみたいと思います。
☆ ☆
別の本にも書きましたが、脊振山や金山からは遥かに韓国が見えるということを江戸時代の福岡の学者・貝原益軒が『筑前国続風土記』に書いています(中村学園大学から無料のウェブで読めます)。
「背振山は、板屋村の西南に在り。国中にて勝れたる高山也。……山上より四方窺い望めばはなはだしく遠也。秋の頃天気晴朗にし烟靄なき時は、朝鮮国見ゆ。春月霞多き時と云へ共、曇らざる日は、壱岐対馬まで能(く)見ゆ。」、
「又里民の云傳ふるは、古(いにしえ)辯才百済国より爰に来り給ふ時、乗給ひし馬の背を振たる故に、背振山て(と)名付たりと云。」などと。
富士山も、京都や福島からも見ることができ、和歌山県の那智勝浦から見た富士山は、「証拠写真」もネットにあるとおりですから、それよりも距離的に近い韓国との話を述べた貝原説は本当でしょう。そして私は、三瀬からたくさんの土器や石器が発見されていることも、このことを裏付けるのではないかと正に「ロマン」ながら思うのです。
宿から山中に向かう三叉路の北、つまり263号線沿いからは、韓国などでよく見られる縄文時代の刷毛目紋土器が発見されたことが七田忠志先生により『佐賀県史跡名勝記念物調査報告(昭和22年)』に紹介されています(宮崎県立西都原考古博物館『人の来た道―東アジア旧石器時代と宮﨑―』)。
更には、黒曜石やサヌカイトの石鏃や破片が今原、松尾、釜頭、岸高などからも出ています。
そして、七田先生は、こうした石器が三瀬峠を越えて福岡側にまで点々と発見されていることに興味を示されています。
私の推測をたくましくすると、古代、福岡から登って来た渡来人が金山や脊振山に登って故郷・韓半島を眺め、そんな三瀬に定住して、よそから持ってきた黒曜石などの石器や土器をあちこちに残し、それが七田先生の報告で言うと宿から松尾や釜頭、岸高辺りにまで点々とそうした遺物が残ったのかもしれません(『三瀬村誌』には更にたくさんの発見例があります)。
私が生まれた今原は、今原と書いて「いまばる」と読みます。九州では一般的に「原」を「ばる」と読みますが、この原・ばるは、韓国のポル即ち村落を意味する言葉であるとも言われています。ですので、三瀬は山の上ですが、大陸と非常に近い、いわば国際的な場所なのだということをしっかりと自覚したいと思うのです。
ちょうどそんなことを物語るように、時代はずれますが、福岡側の室見川の左岸には、吉武遺跡があって、そこからは韓半島にもつながる装飾古墳が発見されています。装飾古墳、特に福岡と小倉との間にある竹原古墳においては、正に高麗やもっと北の胡服のようなものを着た武人の絵が描かれ、ここでも大陸との深いつながりが見えます。三瀬の遺跡もそういう九州(日本)全体の古代からの国際交流の一つの証拠では?と思えば、我が故郷は正にはるか古から国際的な場所だった!ということになりそうです。
以上は縄文、弥生、古墳時代の話ですが、その後も多くの人々が三瀬に渡来し、交流のあったことは『三瀬村誌』などにもあるとおりです。これからより広くそうしたことの中身について、時代を追ってお話しさせていただければと思います。大いに「ロマン」を開花させて。
---------------------
2022年4月10日
嘉村孝
(三瀬出身。東京で「葉隠フォーラム」という名の歴史学者参加の勉強会を主宰。毎月開催で250回を数える。)
http://hagakurebushido.jp/
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
佐賀県の霊峰・天山の頂上から北を臨むと、まるで洗濯板(古い!)のように次々と山並みが見られ、一番北には右から脊振山、金山、井原山、雷山などが見通せます。太古の平原が北側から徐々に盛り上がって脊振山系がつくられたことがよくわかります。三瀬村はこうした山々の一角にある盆地であることは皆様ご承知の通りです。
さてそこで、この三瀬村がそんな単なる山村ではなく、古代から極めて国際的な場所であったということを「ロマン」を交えて記してみたいと思います。
☆ ☆
別の本にも書きましたが、脊振山や金山からは遥かに韓国が見えるということを江戸時代の福岡の学者・貝原益軒が『筑前国続風土記』に書いています(中村学園大学から無料のウェブで読めます)。
「背振山は、板屋村の西南に在り。国中にて勝れたる高山也。……山上より四方窺い望めばはなはだしく遠也。秋の頃天気晴朗にし烟靄なき時は、朝鮮国見ゆ。春月霞多き時と云へ共、曇らざる日は、壱岐対馬まで能(く)見ゆ。」、
「又里民の云傳ふるは、古(いにしえ)辯才百済国より爰に来り給ふ時、乗給ひし馬の背を振たる故に、背振山て(と)名付たりと云。」などと。
富士山も、京都や福島からも見ることができ、和歌山県の那智勝浦から見た富士山は、「証拠写真」もネットにあるとおりですから、それよりも距離的に近い韓国との話を述べた貝原説は本当でしょう。そして私は、三瀬からたくさんの土器や石器が発見されていることも、このことを裏付けるのではないかと正に「ロマン」ながら思うのです。
宿から山中に向かう三叉路の北、つまり263号線沿いからは、韓国などでよく見られる縄文時代の刷毛目紋土器が発見されたことが七田忠志先生により『佐賀県史跡名勝記念物調査報告(昭和22年)』に紹介されています(宮崎県立西都原考古博物館『人の来た道―東アジア旧石器時代と宮﨑―』)。
更には、黒曜石やサヌカイトの石鏃や破片が今原、松尾、釜頭、岸高などからも出ています。
そして、七田先生は、こうした石器が三瀬峠を越えて福岡側にまで点々と発見されていることに興味を示されています。
私の推測をたくましくすると、古代、福岡から登って来た渡来人が金山や脊振山に登って故郷・韓半島を眺め、そんな三瀬に定住して、よそから持ってきた黒曜石などの石器や土器をあちこちに残し、それが七田先生の報告で言うと宿から松尾や釜頭、岸高辺りにまで点々とそうした遺物が残ったのかもしれません(『三瀬村誌』には更にたくさんの発見例があります)。
私が生まれた今原は、今原と書いて「いまばる」と読みます。九州では一般的に「原」を「ばる」と読みますが、この原・ばるは、韓国のポル即ち村落を意味する言葉であるとも言われています。ですので、三瀬は山の上ですが、大陸と非常に近い、いわば国際的な場所なのだということをしっかりと自覚したいと思うのです。
ちょうどそんなことを物語るように、時代はずれますが、福岡側の室見川の左岸には、吉武遺跡があって、そこからは韓半島にもつながる装飾古墳が発見されています。装飾古墳、特に福岡と小倉との間にある竹原古墳においては、正に高麗やもっと北の胡服のようなものを着た武人の絵が描かれ、ここでも大陸との深いつながりが見えます。三瀬の遺跡もそういう九州(日本)全体の古代からの国際交流の一つの証拠では?と思えば、我が故郷は正にはるか古から国際的な場所だった!ということになりそうです。
以上は縄文、弥生、古墳時代の話ですが、その後も多くの人々が三瀬に渡来し、交流のあったことは『三瀬村誌』などにもあるとおりです。これからより広くそうしたことの中身について、時代を追ってお話しさせていただければと思います。大いに「ロマン」を開花させて。
---------------------
2022年4月10日
嘉村孝
(三瀬出身。東京で「葉隠フォーラム」という名の歴史学者参加の勉強会を主宰。毎月開催で250回を数える。)
http://hagakurebushido.jp/
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
2022年04月02日
三瀬村 人と山の色彩
うぐいすらしき鳴き声と共に3月末の山里は花の匂いに満ちていました。三瀬村の春で す。
国道263号沿いを車で通っていると、小学校や中学校の前には薄紫やピンクの紫桜や控 えめな黄色のすいれんがこちらに顔を向けています。まるで迎えられているようで、僕はこ の季節、この道を通る度に嬉しくなります。
村に通っているうちに、僕はこの花々の植え込みを始めた男性に出会いました。当時、村 の老人クラブの会長を務めていた80代後半の男性です。
「三瀬村は観光地だから名所みたいなものを作れないかと きれいな花のある村というこ とではじめのですよ」
男性は続けて、かつての村の思い出を語ってくれました。
「昔は雑木の生い茂る山の裾野にわらびを取りに行ったり、川で石を並べて魚とりの罠を 作ったり、それを夕食のおかずにしたり そんな山でたくさんの友達と遊んだり」。
目を細 めながら話す男性はとても誇らしげで、その様子から、僕はどれだけこの人が村を愛してい るかを感じることができました。 しかし男性は21歳の時、就職の為、当時まだ発足したばかりだった警察予備隊に入隊。 故郷を離れることになります。その後、高度経済成長期が訪れ、男性が長い年月を経て故郷 に戻った時、村は大きく変わってしまっていたと言います。
雑木の森は杉ヒノキの人工林に 変わり、道路近くまで迫っていました。
川も魚が少なくなり、故郷に残っていたはずの友達 の多くは病などで施設に入っていたり、亡くなっていたりして会うことさえ難しくなって いたと言います。
その時、男性は寂しさを感じると同時に「昔の誇れる故郷を取り戻したい」 と強く思い、「花いっぱい活動」という取り組みを始めることを決めました。
「花を見て腹を立てる人はいないと思いますので」
朗らかに笑う男性の表情が僕は今で も忘れられません。
その後、男性は老人クラブに声をかけ、小中学校の前や車通りの多い国道263号線沿い にたくさんの花を植えました。
僕が聞いただけでもあじさいを800株、芝桜5000株、 すいせんは2万2000株にものぼると言います。
男性の情熱に惹かれ、村の人たちは懸命 に株の植え込みや草取りなどの手入れを行い続け、およそ20年。手入れをする年配の人た ちも、その花が咲く通学路を通う子供たちも春に咲く花々の姿に自分たちの故郷への誇り を感じるようになりました。
近年、男性は亡くなられましたが、その思いは今も村の人たちの中に引き継がれています。 それは何気ない風景を見ると感じることが出来ます。
スイセンなどの花は畑の一角に、集落 の公民館の脇に、そして家の庭に積んである肥料袋の傍や石垣にも植えられ、村の暮らしを そっと彩っています。 仕事の合間に花を楽しみながら村を歩いていると、そんな庭先の花を嬉しそうに眺めて いる年配の女性に出会いました。
その女性は
「あの人が老人クラブなんかで株を配っていた だからみんな持って帰って 植えているんよ」
と教えてくれました。
村の人たちが故郷の為、懸命に植えてきた花々の周りには、それを見守るように菜の花や 山桜など山の花々が咲き誇っています。
その情景はそこに暮らす人達はもちろん、訪れる人 たちの心も豊かさにしてくれています。
男性が特に熱心に植えていた芝桜の花言葉は「合意」。
男性から始まった村の人たちの意 志が一つとなって、村に鮮やかな春の彩という豊かさを与えてくれているのだと僕は思い ます。






---------------------
2022年4月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
国道263号沿いを車で通っていると、小学校や中学校の前には薄紫やピンクの紫桜や控 えめな黄色のすいれんがこちらに顔を向けています。まるで迎えられているようで、僕はこ の季節、この道を通る度に嬉しくなります。
村に通っているうちに、僕はこの花々の植え込みを始めた男性に出会いました。当時、村 の老人クラブの会長を務めていた80代後半の男性です。
「三瀬村は観光地だから名所みたいなものを作れないかと きれいな花のある村というこ とではじめのですよ」
男性は続けて、かつての村の思い出を語ってくれました。
「昔は雑木の生い茂る山の裾野にわらびを取りに行ったり、川で石を並べて魚とりの罠を 作ったり、それを夕食のおかずにしたり そんな山でたくさんの友達と遊んだり」。
目を細 めながら話す男性はとても誇らしげで、その様子から、僕はどれだけこの人が村を愛してい るかを感じることができました。 しかし男性は21歳の時、就職の為、当時まだ発足したばかりだった警察予備隊に入隊。 故郷を離れることになります。その後、高度経済成長期が訪れ、男性が長い年月を経て故郷 に戻った時、村は大きく変わってしまっていたと言います。
雑木の森は杉ヒノキの人工林に 変わり、道路近くまで迫っていました。
川も魚が少なくなり、故郷に残っていたはずの友達 の多くは病などで施設に入っていたり、亡くなっていたりして会うことさえ難しくなって いたと言います。
その時、男性は寂しさを感じると同時に「昔の誇れる故郷を取り戻したい」 と強く思い、「花いっぱい活動」という取り組みを始めることを決めました。
「花を見て腹を立てる人はいないと思いますので」
朗らかに笑う男性の表情が僕は今で も忘れられません。
その後、男性は老人クラブに声をかけ、小中学校の前や車通りの多い国道263号線沿い にたくさんの花を植えました。
僕が聞いただけでもあじさいを800株、芝桜5000株、 すいせんは2万2000株にものぼると言います。
男性の情熱に惹かれ、村の人たちは懸命 に株の植え込みや草取りなどの手入れを行い続け、およそ20年。手入れをする年配の人た ちも、その花が咲く通学路を通う子供たちも春に咲く花々の姿に自分たちの故郷への誇り を感じるようになりました。
近年、男性は亡くなられましたが、その思いは今も村の人たちの中に引き継がれています。 それは何気ない風景を見ると感じることが出来ます。
スイセンなどの花は畑の一角に、集落 の公民館の脇に、そして家の庭に積んである肥料袋の傍や石垣にも植えられ、村の暮らしを そっと彩っています。 仕事の合間に花を楽しみながら村を歩いていると、そんな庭先の花を嬉しそうに眺めて いる年配の女性に出会いました。
その女性は
「あの人が老人クラブなんかで株を配っていた だからみんな持って帰って 植えているんよ」
と教えてくれました。
村の人たちが故郷の為、懸命に植えてきた花々の周りには、それを見守るように菜の花や 山桜など山の花々が咲き誇っています。
その情景はそこに暮らす人達はもちろん、訪れる人 たちの心も豊かさにしてくれています。
男性が特に熱心に植えていた芝桜の花言葉は「合意」。
男性から始まった村の人たちの意 志が一つとなって、村に鮮やかな春の彩という豊かさを与えてくれているのだと僕は思い ます。






---------------------
2022年4月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com