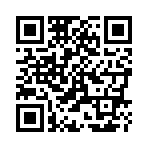2022年12月31日
あっちゃんの三瀬村お野菜時記(12月 柚子)
今年もあと数日で終わりというときに、川浪氏より連絡が来た。
三瀬の野菜などを紹介するコラム「三瀬村お野菜時記」のことだろうと思った。いつものことなら、上旬には川浪氏から連絡があるからだ。
「今月はちょっと立て込んでいて、お話を聞きにお伺いすることができません。今月は柚子だったですよね?」
「そうよ。連絡無いかと思ったー」
「ところで、12月18日と23日の大雪は大変でしたね。雪の写真があったら送ってくれませんか?」
そうなのだ。今月、三瀬村では大雪が降った。三瀬村は、標高400メートルくらいで脊振山系の麓にある盆地なので、冬は雪が降るし、積もる。二十年くらいまえからはあまり降らなくなったけど、冬は隣の富士町や脊振村と並んで、北部九州有数の降雪地域としても知られている。
(富士町には天山スキー場があった。今年の1月にコロナの影響もあって閉鎖になってしまったけど。。)
「わかったわ。ちょうどスマホで撮ってたのがあるから、雪の写真送っておくね」



「かなり積もりましたね・・・佐賀とは思えないですね。雪国みたい。。」
「そうね。びっくりするでしょう? 18日、19日で40センチくらい。23日で15センチくらい積もったよ」
「これは大変でしたね・・・」
まあね。三瀬の雪の大変さは、市街地に住む川浪氏には判らないだろうし、住んだことのない人には伝えようもないものね。三瀬の雪の生活については、また別の機会にでも話を聞いてもらおう。
「今月の柚子についてですが、去年、一度話を聞いたことがあったので、そのときのメモを元にコラムを書いてみますね」
「そう。じゃあ、お願いするわね」
ということで、川浪氏にある程度お任せすることにした。
三瀬村ではいまでも家の敷地内に柚子の木を植えているところも多い。十月を過ぎたころから、三瀬村を車で走ると、黄色い柚子がなっているのを見かけるようになる。
三瀬村を南へ下りた大和町はみかんで有名な地域だけど、みかんは標高が高い三瀬では栽培されていない。その代わり、昔から柚子の木が多い。柚子の使い方といえば、唐辛子と混ぜ合わせて作る柚子ごしょう。家の畑で作った唐辛子をミキサーなどですりつぶして、柚子の皮と塩を混ぜて作る。
寒い冬に、味噌汁や鍋物、麺類に入れて食べると、体が温まる。降雪地域の三瀬村の生活に根付いた調味料なのだ。
私たちのグループでは六軒の農家から柚子を、昨年までは350キロ~400キロ仕入れて、柚子こしょうを作っている。
ちょうどいま、11月下旬から12月下旬までが収穫の時期だ。夏に採れた唐辛子を使って、柚子ごしょう作りを行う。
来年はおかげさまで、柚子ごしょうの販路が増えたから、今年は580キロを仕入れた。
仕入れた柚子は柚子ごしょうを作るために、皮だけを使う。果肉はどうするのですか? と川浪氏から聞かれたけど、果肉は食べても酸っぱいし、とても食べられない。。必要な方がいれば(安価に)譲っている。果汁を絞って、ポン酢にするとか、柚子ジャムにするとか、焼き魚にかけるとか。
「三瀬村の柚子ごしょうの味の特徴は?」
九州の名産となった柚子ごしょうは、各県、各地で作られていて特徴らしい特徴を伝えることが難しい。
三瀬村の柚子ごしょうは、ほかの産地の柚子ごしょうと比べると、『辛い』というのが特徴だ。柚子ごしょうだから、辛いのは当たり前だろうと思う方も多いでしょうけど。
味噌汁、鍋物、うどん、湯どうふ、おでん、など何にでも入れてみてください。柚子ごしょうの辛さで、さらに味が際立つこと間違いないから。
あと、夏も、そうめんの麺つゆに入れて食べたら、とても美味しい。
あるとき、川浪氏が訊いた。
「三瀬村の特産品で一番有名なのは?」
「柚子ごしょう」
「そうですよね。三瀬村は柚子の村といっていいですよね。もっと三瀬と言えば、柚子、というくらいになればいいですね」
「そうね」
と返事をしたあと、私は胸の内で思った。
三瀬村の柚子ごしょうは、三瀬の柚子があってのものだから。柚子の木を絶やさないようにしたい。
あちらこちらに、柚子の黄色い実がなっている三瀬村でありますように、と。



三瀬村の柚子ごしょう(オンラインショップへジャンプします)

コラムをご覧のみなさま。読んでくださいまして、ありがとうございました。来年も何卒よろしくお願いいたします。それでは良いお年をお迎えください。
2022年12月31日
話し手:川﨑淳子(三瀬在住の農家)
文:川浪秀之
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
三瀬の野菜などを紹介するコラム「三瀬村お野菜時記」のことだろうと思った。いつものことなら、上旬には川浪氏から連絡があるからだ。
「今月はちょっと立て込んでいて、お話を聞きにお伺いすることができません。今月は柚子だったですよね?」
「そうよ。連絡無いかと思ったー」
「ところで、12月18日と23日の大雪は大変でしたね。雪の写真があったら送ってくれませんか?」
そうなのだ。今月、三瀬村では大雪が降った。三瀬村は、標高400メートルくらいで脊振山系の麓にある盆地なので、冬は雪が降るし、積もる。二十年くらいまえからはあまり降らなくなったけど、冬は隣の富士町や脊振村と並んで、北部九州有数の降雪地域としても知られている。
(富士町には天山スキー場があった。今年の1月にコロナの影響もあって閉鎖になってしまったけど。。)
「わかったわ。ちょうどスマホで撮ってたのがあるから、雪の写真送っておくね」



「かなり積もりましたね・・・佐賀とは思えないですね。雪国みたい。。」
「そうね。びっくりするでしょう? 18日、19日で40センチくらい。23日で15センチくらい積もったよ」
「これは大変でしたね・・・」
まあね。三瀬の雪の大変さは、市街地に住む川浪氏には判らないだろうし、住んだことのない人には伝えようもないものね。三瀬の雪の生活については、また別の機会にでも話を聞いてもらおう。
「今月の柚子についてですが、去年、一度話を聞いたことがあったので、そのときのメモを元にコラムを書いてみますね」
「そう。じゃあ、お願いするわね」
ということで、川浪氏にある程度お任せすることにした。
三瀬村ではいまでも家の敷地内に柚子の木を植えているところも多い。十月を過ぎたころから、三瀬村を車で走ると、黄色い柚子がなっているのを見かけるようになる。
三瀬村を南へ下りた大和町はみかんで有名な地域だけど、みかんは標高が高い三瀬では栽培されていない。その代わり、昔から柚子の木が多い。柚子の使い方といえば、唐辛子と混ぜ合わせて作る柚子ごしょう。家の畑で作った唐辛子をミキサーなどですりつぶして、柚子の皮と塩を混ぜて作る。
寒い冬に、味噌汁や鍋物、麺類に入れて食べると、体が温まる。降雪地域の三瀬村の生活に根付いた調味料なのだ。
私たちのグループでは六軒の農家から柚子を、昨年までは350キロ~400キロ仕入れて、柚子こしょうを作っている。
ちょうどいま、11月下旬から12月下旬までが収穫の時期だ。夏に採れた唐辛子を使って、柚子ごしょう作りを行う。
来年はおかげさまで、柚子ごしょうの販路が増えたから、今年は580キロを仕入れた。
仕入れた柚子は柚子ごしょうを作るために、皮だけを使う。果肉はどうするのですか? と川浪氏から聞かれたけど、果肉は食べても酸っぱいし、とても食べられない。。必要な方がいれば(安価に)譲っている。果汁を絞って、ポン酢にするとか、柚子ジャムにするとか、焼き魚にかけるとか。
「三瀬村の柚子ごしょうの味の特徴は?」
九州の名産となった柚子ごしょうは、各県、各地で作られていて特徴らしい特徴を伝えることが難しい。
三瀬村の柚子ごしょうは、ほかの産地の柚子ごしょうと比べると、『辛い』というのが特徴だ。柚子ごしょうだから、辛いのは当たり前だろうと思う方も多いでしょうけど。
味噌汁、鍋物、うどん、湯どうふ、おでん、など何にでも入れてみてください。柚子ごしょうの辛さで、さらに味が際立つこと間違いないから。
あと、夏も、そうめんの麺つゆに入れて食べたら、とても美味しい。
あるとき、川浪氏が訊いた。
「三瀬村の特産品で一番有名なのは?」
「柚子ごしょう」
「そうですよね。三瀬村は柚子の村といっていいですよね。もっと三瀬と言えば、柚子、というくらいになればいいですね」
「そうね」
と返事をしたあと、私は胸の内で思った。
三瀬村の柚子ごしょうは、三瀬の柚子があってのものだから。柚子の木を絶やさないようにしたい。
あちらこちらに、柚子の黄色い実がなっている三瀬村でありますように、と。



三瀬村の柚子ごしょう(オンラインショップへジャンプします)

コラムをご覧のみなさま。読んでくださいまして、ありがとうございました。来年も何卒よろしくお願いいたします。それでは良いお年をお迎えください。
2022年12月31日
話し手:川﨑淳子(三瀬在住の農家)
文:川浪秀之
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
2022年12月15日
北山公論ならぬ三瀬公論
北山ダムのヘラブナ釣りシリーズが終わって、さて、次に何を書くかなと思案していると、
ふと、佐賀県富士町(いまは佐賀市富士町)の図書館で目にしたことがある、【北山公論】という、昔発刊されていたという新聞のことが頭に浮かんだ。
北山公論に関するブログ記事
https://fujilib.sagafan.jp/e595052.html
北山公論について、ブログ記事から転載させてもらうと、
----------------------------------------------------
「北山公論」とは一体…?
それは、大正14(1925)年~昭和14(1939)年に富士町の北山村エリアで出されていた月刊の新聞です(タブロイド版・4面)。
北山村はもとより、県外や海外で活躍する村出身者にも配布されていたようです。
内容は、村内のニュースや行財政、時事評論、歴史文化、文芸投稿、広告など。
だれそれが結婚したとか、どこの大学を卒業したとか、どこそこで火事が起こったとか、地域密着のニュースもあります。
「北山公論」の創刊号にはこう書かれています。
「夜はまさに明けた。太陽は高く昇っている。
しかし田園人は眠っている。早く眼を覚まさねばならぬ。」(一部略)
山奥の地にあって、都市部の情報から取り残されてはならない。
日本の“今”を知り、伝えることで、北山村の生活や文化の質を向上させたい。
…そんな編集者の使命感が伝わってきます。
民主主義や自由主義をうたう大正デモクラシーの波が
九州の山間地にも押し寄せていた、ということでも興味深いですね。
・・・
---------------------------------------------------------
なぜ、北山公論のことが、頭に浮かんだかというと、二年前に三瀬村活性化会議の会合に参加したときの、ある会話が頭から離れないからだ。
ぼくは三瀬村活性化会議に、ネットショップを支援する立場で参加した。その際、三瀬村の将来についてや、活性化について、ネットショップ以外のことでもさまざまな話が交わされた。
観光客、買い物客など、いわゆる三瀬に来る人たちをどうやって増やすか、という話が中心になった。
そんななか、参加者の一人が、
「でもさ、三瀬って何で生活してきたと思うや? 観光? うんにゃ(ちがう)。そいもあるかもしれんけど、農業と林業で生活ばしてきたとばい」
続けて、
「三瀬以外のあんたたちは、観光、観光、っていうばってんね、じゃあ、農業はどうなってるのか? 三瀬の米は美味しか、というけど、本当に美味しいのかどうか? 美味しいというなら、どう美味しいのか? なぜ美味しいのか? 佐賀県内でも三瀬以外のところで採れる米も、いまは美味しかけんね。たしかに三瀬の米は美味しいと思うばってん、ほかのところも美味しくなってるけんさ。 それから、収穫量はどうなってるのか? これから三瀬の農業をどう考えたらよかとか。 そういうのも、三瀬におるものを入れて、話ばせんといかんと思う。 三瀬の実情ばね、話し合う機会のあればね。観光とか、イベントとか、そいばっかりじゃなくてね」
それを聞いて、ぼくは、黙りこんでしまった。
そして、そのとき、頭に浮かんだのも、【北山公論】という新聞のことだった。
インターネットを活用したマーケティングの業界で仕事をしているので、どうしても、観光とかネットショップとか、そういう角度からでしか地域活性化を話すことがないのだが、二年前の会議で聞いたその人の発言は、とても重要なことを言われたような気がしてならない。
それは、観光のことを語るな、ではなく、農業のことを語れ、でもない。
三瀬に住んでいる人と、外部の人と、一緒になって、公論をしようじゃないか、ということだったのではないかと思うのだ。
北山公論ならぬ三瀬公論。
実際に、【三瀬公論】をする場ができるかどうかは判らないが、【地域公論】というしくみ、またはそのような【場】について、もう少し関心を持ってみたいと思う。
---------------------
2022年12月15日
川浪秀之(Webプロデューサー、作家)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
ふと、佐賀県富士町(いまは佐賀市富士町)の図書館で目にしたことがある、【北山公論】という、昔発刊されていたという新聞のことが頭に浮かんだ。
北山公論に関するブログ記事
https://fujilib.sagafan.jp/e595052.html
北山公論について、ブログ記事から転載させてもらうと、
----------------------------------------------------
「北山公論」とは一体…?
それは、大正14(1925)年~昭和14(1939)年に富士町の北山村エリアで出されていた月刊の新聞です(タブロイド版・4面)。
北山村はもとより、県外や海外で活躍する村出身者にも配布されていたようです。
内容は、村内のニュースや行財政、時事評論、歴史文化、文芸投稿、広告など。
だれそれが結婚したとか、どこの大学を卒業したとか、どこそこで火事が起こったとか、地域密着のニュースもあります。
「北山公論」の創刊号にはこう書かれています。
「夜はまさに明けた。太陽は高く昇っている。
しかし田園人は眠っている。早く眼を覚まさねばならぬ。」(一部略)
山奥の地にあって、都市部の情報から取り残されてはならない。
日本の“今”を知り、伝えることで、北山村の生活や文化の質を向上させたい。
…そんな編集者の使命感が伝わってきます。
民主主義や自由主義をうたう大正デモクラシーの波が
九州の山間地にも押し寄せていた、ということでも興味深いですね。
・・・
---------------------------------------------------------
なぜ、北山公論のことが、頭に浮かんだかというと、二年前に三瀬村活性化会議の会合に参加したときの、ある会話が頭から離れないからだ。
ぼくは三瀬村活性化会議に、ネットショップを支援する立場で参加した。その際、三瀬村の将来についてや、活性化について、ネットショップ以外のことでもさまざまな話が交わされた。
観光客、買い物客など、いわゆる三瀬に来る人たちをどうやって増やすか、という話が中心になった。
そんななか、参加者の一人が、
「でもさ、三瀬って何で生活してきたと思うや? 観光? うんにゃ(ちがう)。そいもあるかもしれんけど、農業と林業で生活ばしてきたとばい」
続けて、
「三瀬以外のあんたたちは、観光、観光、っていうばってんね、じゃあ、農業はどうなってるのか? 三瀬の米は美味しか、というけど、本当に美味しいのかどうか? 美味しいというなら、どう美味しいのか? なぜ美味しいのか? 佐賀県内でも三瀬以外のところで採れる米も、いまは美味しかけんね。たしかに三瀬の米は美味しいと思うばってん、ほかのところも美味しくなってるけんさ。 それから、収穫量はどうなってるのか? これから三瀬の農業をどう考えたらよかとか。 そういうのも、三瀬におるものを入れて、話ばせんといかんと思う。 三瀬の実情ばね、話し合う機会のあればね。観光とか、イベントとか、そいばっかりじゃなくてね」
それを聞いて、ぼくは、黙りこんでしまった。
そして、そのとき、頭に浮かんだのも、【北山公論】という新聞のことだった。
インターネットを活用したマーケティングの業界で仕事をしているので、どうしても、観光とかネットショップとか、そういう角度からでしか地域活性化を話すことがないのだが、二年前の会議で聞いたその人の発言は、とても重要なことを言われたような気がしてならない。
それは、観光のことを語るな、ではなく、農業のことを語れ、でもない。
三瀬に住んでいる人と、外部の人と、一緒になって、公論をしようじゃないか、ということだったのではないかと思うのだ。
北山公論ならぬ三瀬公論。
実際に、【三瀬公論】をする場ができるかどうかは判らないが、【地域公論】というしくみ、またはそのような【場】について、もう少し関心を持ってみたいと思う。
---------------------
2022年12月15日
川浪秀之(Webプロデューサー、作家)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
2022年12月10日
少弍政資と三瀬 ―その1―
ここで久しぶりに、話を三瀬の歴史に戻したいと思います。
鎌倉時代が終って、三瀬の室町時代は、これまた資料には乏しいものの杠日向守の事跡などが『北肥戦史』などに載っています。
この話をするには、鎌倉時代以来の九州の法的枠組みを踏えなければなりません。
源頼朝によって北部九州、特に博多は今の横浜から来た武藤改め少弍氏によって治めることに。東九州は、やはり関東の小田原から来た大友氏によって治めることに。南九州は、同じ神奈川県の厚木から来た島津氏によって治めることになりました。彼らはいずれも関東武士というわけです。
この人達が守護や鎮西奉行になったということは、法律的な頼朝の任命を受けたということであって、以後彼らはその地位を死守しようとして頑張りました。
三瀬の歴史からは若干外れますが、その典型例が1375年に熊本であった水島の変です。これは南北朝時代、京都から派遣された足利の一族・今川了俊が、自らの勢力とバッティングする少弍冬資をおびき出して誘殺したことに腹を立てて、大友と島津がいずれも「こんなことには付き合ってられないよ」と兵を挙げて、自分の領国に引き上げたという話です。そのくらい少弍、大友、島津は固い団結心を持っていたとも言えるでしょう。
しかし、九州という島は桑の葉っぱの形に例えられるようなおいしい形をしていて、その一番おいしいところ、つまり中国や韓国との外国貿易の拠点の博多を狙って来る勢力がありました。それは、中国地方という蚕にそっくりの形をしたところに蟠踞する大内氏でした。その大内氏は、博多の利権を取ろうとして少弍氏をいじめてきます。それに対して、鎌倉以来の枠組みを死守しようとしたのが豊後の大友氏であり、一方、少し時代が下りますが、佐賀の龍造寺隆信の「隆」は、大内義隆の「隆」の字をもらっていますから、これは正に中国地方の雄と佐賀の新興勢力との連携による少弍追い落しです。三瀬は神代氏の代になっても大友側つまり鎌倉以来の枠組みを守ろうとしたわけです。
そんな中で、少弍氏は頑張ります。特に、少弍政資は、大内政弘が応仁文明の乱で京都にいる隙を狙って、対馬から一旦は大宰府に返り咲いたのですが、結局はそこを陥れられるということになります。
この過程の中に三瀬が登場します。『北肥戦史』では、「少弍政尚(政資)探題渋河萬寿丸の事」として、少弍政資が将軍足利義政の御教書を得て、対馬から船百余艘を艤し、その中には朝鮮貿易で得た財宝もたっぷり積んで、博多へ着船。大宰府に帰り付いて、筑前、肥前、豊前、壱岐、対馬の五州の太守と仰がれたこと、しかし、少々調子に乗り過ぎて、宗像大宮司や綾部の足利探題渋河萬寿丸を攻め滅ぼし、更にその子刀禰丸を追い出したという話が出てきます。
そして、三瀬の杠日向守に対し、筑前の今の那珂川町岩門の亀尾城にいた萬寿丸を滅ぼしたこと、更に今後の協力を求めています。
「去十七日亀尾城切捕候。敵城主森戸修理亮為始十余人打捕候。宗播磨守為人豊馳越高名候。馬場肥前守・筑紫下野守以下総勢あやべのしろへ、十八日未明差寄候。彼敵城内申談族候間、当日可落著候。至早良・横山・大窪伊代守為先勢申付候。此時馳走憑入候。委細経康可申談候。恐惶謹言。
七月二六日 政資(判)
杠日向守殿 」
大宰府から、今の鳥栖、みやき町、神埼等々が全部連携し、三瀬も北部九州の要地として政資と談合する力を持っていたものと思われます。
そんな政資でしたが、少しずつ少しずつ追い詰められ、遂に多久の専称寺で自刃することになりますが、そのことと三瀬との関係については次回書かせていただきます。
---------------------
2022年12月10日
嘉村孝
(三瀬出身。東京で「葉隠フォーラム」という名の歴史学者参加の勉強会を主宰。毎月開催で250回を数える。)
http://hagakurebushido.jp/
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
鎌倉時代が終って、三瀬の室町時代は、これまた資料には乏しいものの杠日向守の事跡などが『北肥戦史』などに載っています。
この話をするには、鎌倉時代以来の九州の法的枠組みを踏えなければなりません。
源頼朝によって北部九州、特に博多は今の横浜から来た武藤改め少弍氏によって治めることに。東九州は、やはり関東の小田原から来た大友氏によって治めることに。南九州は、同じ神奈川県の厚木から来た島津氏によって治めることになりました。彼らはいずれも関東武士というわけです。
この人達が守護や鎮西奉行になったということは、法律的な頼朝の任命を受けたということであって、以後彼らはその地位を死守しようとして頑張りました。
三瀬の歴史からは若干外れますが、その典型例が1375年に熊本であった水島の変です。これは南北朝時代、京都から派遣された足利の一族・今川了俊が、自らの勢力とバッティングする少弍冬資をおびき出して誘殺したことに腹を立てて、大友と島津がいずれも「こんなことには付き合ってられないよ」と兵を挙げて、自分の領国に引き上げたという話です。そのくらい少弍、大友、島津は固い団結心を持っていたとも言えるでしょう。
しかし、九州という島は桑の葉っぱの形に例えられるようなおいしい形をしていて、その一番おいしいところ、つまり中国や韓国との外国貿易の拠点の博多を狙って来る勢力がありました。それは、中国地方という蚕にそっくりの形をしたところに蟠踞する大内氏でした。その大内氏は、博多の利権を取ろうとして少弍氏をいじめてきます。それに対して、鎌倉以来の枠組みを死守しようとしたのが豊後の大友氏であり、一方、少し時代が下りますが、佐賀の龍造寺隆信の「隆」は、大内義隆の「隆」の字をもらっていますから、これは正に中国地方の雄と佐賀の新興勢力との連携による少弍追い落しです。三瀬は神代氏の代になっても大友側つまり鎌倉以来の枠組みを守ろうとしたわけです。
そんな中で、少弍氏は頑張ります。特に、少弍政資は、大内政弘が応仁文明の乱で京都にいる隙を狙って、対馬から一旦は大宰府に返り咲いたのですが、結局はそこを陥れられるということになります。
この過程の中に三瀬が登場します。『北肥戦史』では、「少弍政尚(政資)探題渋河萬寿丸の事」として、少弍政資が将軍足利義政の御教書を得て、対馬から船百余艘を艤し、その中には朝鮮貿易で得た財宝もたっぷり積んで、博多へ着船。大宰府に帰り付いて、筑前、肥前、豊前、壱岐、対馬の五州の太守と仰がれたこと、しかし、少々調子に乗り過ぎて、宗像大宮司や綾部の足利探題渋河萬寿丸を攻め滅ぼし、更にその子刀禰丸を追い出したという話が出てきます。
そして、三瀬の杠日向守に対し、筑前の今の那珂川町岩門の亀尾城にいた萬寿丸を滅ぼしたこと、更に今後の協力を求めています。
「去十七日亀尾城切捕候。敵城主森戸修理亮為始十余人打捕候。宗播磨守為人豊馳越高名候。馬場肥前守・筑紫下野守以下総勢あやべのしろへ、十八日未明差寄候。彼敵城内申談族候間、当日可落著候。至早良・横山・大窪伊代守為先勢申付候。此時馳走憑入候。委細経康可申談候。恐惶謹言。
七月二六日 政資(判)
杠日向守殿 」
大宰府から、今の鳥栖、みやき町、神埼等々が全部連携し、三瀬も北部九州の要地として政資と談合する力を持っていたものと思われます。
そんな政資でしたが、少しずつ少しずつ追い詰められ、遂に多久の専称寺で自刃することになりますが、そのことと三瀬との関係については次回書かせていただきます。
---------------------
2022年12月10日
嘉村孝
(三瀬出身。東京で「葉隠フォーラム」という名の歴史学者参加の勉強会を主宰。毎月開催で250回を数える。)
http://hagakurebushido.jp/
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
2022年12月02日
集落結ぶ新年行事“ホンゲンギョウ”
集落の人たちが力を合わせて年越しの準備をするという話を聞いて、取材で行ってみると、山つきの畑の傍の竹林には大勢の集落の人たちが集まっていました。竹は集落の公民館に飾る門松作りとホンゲンギョウに使われるそうです。
ホンゲンギョウとは厄除けの火祭り。三メートルほどの大きな竹と枯草などで作った櫓を年が明けてから炊きつけ、その年、集落の人たちが無病息災で過ごせることを祈る大切な新年行事です。
いつの頃から行われているのか定かではありませんが、この集落では少なくとも今の八十代の方々が幼いころには既に行われていたようです。
そんな行事が今も人々の手によって続けられているという話を聞いて、それがどのような形で、そんな思いの元に受け継がれているのか、実際のところを知りたいというのが僕が取材に伺ったきっかけでした。
霧雨が降る、師走の冷え込みの中、チェンソーを持った幾人かの人たちが畑に覆いかぶさるように成長した竹林の根の暗闇に分け入っていきます。すぐに雨の静寂を破る様に、けたたましいチェンソーの音が響き渡りました。
しばらく続いたその音が急に静かになったと思ったら、太い竹が一本、その細い体をしならせながら葉擦れの音を立てて畑に倒れてきました。その竹の周りに倒竹作業を見守っていた他の人たちが集まり、鉈で枝葉を切り落としていきます。そうして一本の長い柱になった竹は真ん中くらいで更に分割され、軽トラックの荷台に積み込まれました。新年を迎える為の、この倒竹作業は畑などに迫る竹林の除去作業も兼ねているのだとか。
冷え込みが増す中、そう言いながらカッパ姿で黙々と作業する人たちを見ていると、僕は山の行事と暮らしがいかに強く結びついているかを改めて感じました。
切り出された竹の一部は集落の公民館に運ばれます。そこで年間を通して集落の大事な会合を重ねる場所の為の、門松を作るのです。手掛けるのは主に年配の男性の人たちです。
そして、そのすぐ近くを流れる川の袂。畑との境にある野原では竹の櫓が組まれます。太く長い竹の柱を中心に、いくつかの方向から他の竹の柱を先端近くで交わらせ、骨組みを作ります。そうして後は枯草などを敷き詰めて太くしていくのです。この作業には更に多くの人たちが加わり、集落のリーダーの男性の指示に従って動いていきます。まだ霧雨は続いており、冷え込みは骨を痺れさせるほどです。しかし、人々は懸命に体を動かし、ホンゲンギョウの象徴である櫓を協力し合って作り上げていくのです。そうして櫓が完成したのは竹の切り出しからおよそ六時間近くが経った頃でした。
年が明けて間もない五日の早朝、僕は再び、この集落を訪れました。この日はホンゲンギョウ当日。
まだ薄暗い畑の櫓の周りには集落の大勢の人たちが集まっていました。作業を行った男性たちばかりではなく、その奥さんや子供たち、年配の人たちなど様々な世代の人たちです。その人たちが見守る中、朝六時を待って櫓には火がつけられます。枯草と竹で作られた櫓は瞬く間に巨大な炎に包まれました。
黙ってその炎を見つめたり、携帯で動画を撮ったり、人々はそれぞれのやり方で、新年最初に灯された厄除けの炎と相対し、家族や集落、ひいては村の仲間の無病息災を祈っていました。僕はこういった場に自分も立ち会えていることが嬉しく、受け入れていただいていることに感謝しながら、人々に習って鬼火に祈りを捧げました。
年末に六時間近くもかけて作り上げた櫓は、火を点けてわずか十五分ほどで崩れ落ちました。そこからは集落の人たちの新年の交流が始まります。
残り火の上に網を敷き、村で採れたイノシシの肉や持ち寄った魚の干物、餅などを焼くのです。大人はこれを肴に酒を飲みかわしますが、子供たちは更にこの熾火で焼き芋やウィンナー、マシュマロなどを焼いて食べるのを楽しみにしています。
孫が生まれた家族は集落の人たちのお披露目にと、その孫を連れてきたり、冬休みでしばらく会えていなかった友達にも、この時に会って話したり。賑やかな新年最初の交流の様子は日の出と共に行われるのです。
交流の終わりごろ、人々は竹で何やら作り始めました。熾火で竹の一部を熱して折り曲げて三角みたいな形にして作り上げたのは「鬼の手」と呼ばれるもの。これを家の玄関先に置くことで魔除けにするのだそうです。
この時、話を聞いた男性の言葉が強く印象に残っています。
「年々、少子高齢化などで山の暮らしは厳しくなっている。そんな中でホンゲンギョウをやってこうして交流できることが何より大事。皆で気合を入れて今年も一年、頑張ろうと思える。そんな思いを共有できる。山で暮らす中で大切なことだと思っている」
ホンゲンギョウはまさに集落の人たちにとって、結の炎なのだと、僕はつくづく思いました。この行事が今年も、来年も、その先もずっと続けられていくことを願わずにはいられません。





---------------------
2022年12月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
ホンゲンギョウとは厄除けの火祭り。三メートルほどの大きな竹と枯草などで作った櫓を年が明けてから炊きつけ、その年、集落の人たちが無病息災で過ごせることを祈る大切な新年行事です。
いつの頃から行われているのか定かではありませんが、この集落では少なくとも今の八十代の方々が幼いころには既に行われていたようです。
そんな行事が今も人々の手によって続けられているという話を聞いて、それがどのような形で、そんな思いの元に受け継がれているのか、実際のところを知りたいというのが僕が取材に伺ったきっかけでした。
霧雨が降る、師走の冷え込みの中、チェンソーを持った幾人かの人たちが畑に覆いかぶさるように成長した竹林の根の暗闇に分け入っていきます。すぐに雨の静寂を破る様に、けたたましいチェンソーの音が響き渡りました。
しばらく続いたその音が急に静かになったと思ったら、太い竹が一本、その細い体をしならせながら葉擦れの音を立てて畑に倒れてきました。その竹の周りに倒竹作業を見守っていた他の人たちが集まり、鉈で枝葉を切り落としていきます。そうして一本の長い柱になった竹は真ん中くらいで更に分割され、軽トラックの荷台に積み込まれました。新年を迎える為の、この倒竹作業は畑などに迫る竹林の除去作業も兼ねているのだとか。
冷え込みが増す中、そう言いながらカッパ姿で黙々と作業する人たちを見ていると、僕は山の行事と暮らしがいかに強く結びついているかを改めて感じました。
切り出された竹の一部は集落の公民館に運ばれます。そこで年間を通して集落の大事な会合を重ねる場所の為の、門松を作るのです。手掛けるのは主に年配の男性の人たちです。
そして、そのすぐ近くを流れる川の袂。畑との境にある野原では竹の櫓が組まれます。太く長い竹の柱を中心に、いくつかの方向から他の竹の柱を先端近くで交わらせ、骨組みを作ります。そうして後は枯草などを敷き詰めて太くしていくのです。この作業には更に多くの人たちが加わり、集落のリーダーの男性の指示に従って動いていきます。まだ霧雨は続いており、冷え込みは骨を痺れさせるほどです。しかし、人々は懸命に体を動かし、ホンゲンギョウの象徴である櫓を協力し合って作り上げていくのです。そうして櫓が完成したのは竹の切り出しからおよそ六時間近くが経った頃でした。
年が明けて間もない五日の早朝、僕は再び、この集落を訪れました。この日はホンゲンギョウ当日。
まだ薄暗い畑の櫓の周りには集落の大勢の人たちが集まっていました。作業を行った男性たちばかりではなく、その奥さんや子供たち、年配の人たちなど様々な世代の人たちです。その人たちが見守る中、朝六時を待って櫓には火がつけられます。枯草と竹で作られた櫓は瞬く間に巨大な炎に包まれました。
黙ってその炎を見つめたり、携帯で動画を撮ったり、人々はそれぞれのやり方で、新年最初に灯された厄除けの炎と相対し、家族や集落、ひいては村の仲間の無病息災を祈っていました。僕はこういった場に自分も立ち会えていることが嬉しく、受け入れていただいていることに感謝しながら、人々に習って鬼火に祈りを捧げました。
年末に六時間近くもかけて作り上げた櫓は、火を点けてわずか十五分ほどで崩れ落ちました。そこからは集落の人たちの新年の交流が始まります。
残り火の上に網を敷き、村で採れたイノシシの肉や持ち寄った魚の干物、餅などを焼くのです。大人はこれを肴に酒を飲みかわしますが、子供たちは更にこの熾火で焼き芋やウィンナー、マシュマロなどを焼いて食べるのを楽しみにしています。
孫が生まれた家族は集落の人たちのお披露目にと、その孫を連れてきたり、冬休みでしばらく会えていなかった友達にも、この時に会って話したり。賑やかな新年最初の交流の様子は日の出と共に行われるのです。
交流の終わりごろ、人々は竹で何やら作り始めました。熾火で竹の一部を熱して折り曲げて三角みたいな形にして作り上げたのは「鬼の手」と呼ばれるもの。これを家の玄関先に置くことで魔除けにするのだそうです。
この時、話を聞いた男性の言葉が強く印象に残っています。
「年々、少子高齢化などで山の暮らしは厳しくなっている。そんな中でホンゲンギョウをやってこうして交流できることが何より大事。皆で気合を入れて今年も一年、頑張ろうと思える。そんな思いを共有できる。山で暮らす中で大切なことだと思っている」
ホンゲンギョウはまさに集落の人たちにとって、結の炎なのだと、僕はつくづく思いました。この行事が今年も、来年も、その先もずっと続けられていくことを願わずにはいられません。





---------------------
2022年12月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com