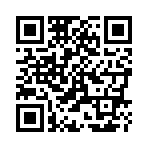2022年11月23日
あっちゃんの三瀬村お野菜時記(11月 キクイモ)
11月上旬に、また川浪氏がやまびこロッジにやってきた。
口ひげを生やした七十歳くらいの男性が一緒だった。
数日前に電話で話したときに、似顔絵画家を連れてくると言っていたので、その人だろうと思った。
「Oといいます。今日はよろしくお願いします」
普段はデザインの仕事をしていらっしゃるみたいで、芸術家のような風采だ。
「似顔絵描かせてくださいね」
「ええ。それはいいですけど、急に用事ができて、三十分しか時間が取れないけど、大丈夫ですか?」
「10分くらいで描きますよ」とOさん。
「あ、そうなんですね」
「じゃあ、似顔絵を描かせてもらいながら、話を聞かせてください」
「わたし、どうしたらいいですか?」
「座ってもらっててよかですよ。川浪君と話よってください。適当に描きますから」
似顔絵なんて描いてもらったことないので、なんだか恥ずかしい。
O画家は、わたしの斜め前の椅子に深く座って、紙袋から色紙と、100円ショップで買ったという絵具付きのプラスチックパレットを取り出した。
そして、わたしの顔の全体を眺めると、おもむろに黒マジックのキャップを外して、いきおいよく右手を動かしていった。
色紙の裏しか見えないので、どんなふうに描いているのか判らない。
「そうそう。ブログに掲載した10月の聞き書きエッセイは、まだあんまり見られていませんけど、ぼちぼちアクセス増えてくると思いますから」
どんな人が見てくれるのかわからないけど、一人でも読んでくださった方がいるのなら、それは嬉しい。
「今月はキクイモですね。キクイモって、あんまり食べたことが無くて。生姜みたいなやつでしょう? 一度生姜と間違って買って帰ったことがあって、、品名見てなくて、、」
「笑 怒られたでしょう?」
「ノーコメントで^^」
「食べたことないって人が多いのかな? どうかなあ?」
「数年前から産直店とかでよく見かけるようになった印象なんですけど、それまではあまり見なかったと思いますけど?」
「そうね。いまから8年前くらいからかな。わたしたちも北海道と長野県から種芋をもらって、それで作るようになったのよ」
「へえ。そうだったのですね。それまでは三瀬村には無かった? 作って無かった?」
「ううん。あったのはあった。この辺では、てんちく芋とかてんつく芋っていっていて、その辺の山に自生しているのがあるのはあるのよ。9月ごろに菊のような黄色い花が咲くの。そのてんちく芋を掘って、酢漬けとか味噌漬けとかにして食べてはいたのよ」
「味噌漬けは食べたことあったよ」
Oさんが口を挟んだ。Oさんはたしか福岡の糸島あたりの出身だった。三瀬のとなりの富士町の山を越えるとすぐに糸島で、雷山・脊振山系の土地柄ではある。
「てんちく芋? てんつく? どういう漢字書くのですか?」
「漢字?」
わからない。。考えたことなかった。どういう漢字当てるのだろう。
(川浪氏があとでインターネットで調べたところ、キクイモのことを、てんちく芋、てんつく芋という言い方は何も情報が無かったみたいだ。三瀬村だけの呼び名なのかもしれない。ちなみに青森ではキクイモのことをカライモというらしい)
「それで、キクイモにはイヌリンが含まれているって、食べたら健康に良いっていって、三瀬村でも作ろうってことになってね。そのまま売ったり、キクイモパウダーにして売ってもらっているの」
「キクイモは、今の時期なのですか?」
「そうね。10月下旬から3月まで」
「種芋を植えて育てるのですか?」
「3月に種芋を植えて、あとはほったらかし^^」
「ほったらかしでいいのですか? 冬の霜は? 里芋は霜に弱かったけど」
「キクイモは強いけんね、ほったらかしでいいとよね。霜にも強か。家の畑に植えるだけで手のかからんけん、自分で作っている人も増えているみたい。三年前くらいまでは店でも売れていたけど、いまも売れるのは売れるけど、去年くらいからちょっと減った気がする。でも畑に植えるときは、気をつけとかんと、どうかするとどんどん根が広がっていくけんね」
「おすすめの食べ方は?」
「そうね。スライスして、きんぴら、天ぷら、酢の物。スープの具にしたり、すりおろしてポタージュにしたり。生でサラダに入れても美味しいよね」
「キクイモ酢ってありますよね? どっかで見たような?」
「わたしたちもキクイモ酢作っていた。いまは作ってないけど」
「出来たよ」
Oさんが、来る途中に、佐賀大学近くのワタナベ画材店で買った筆洗器に絵筆を差して、もぞもぞと濯いだ。そして色紙をくるりと反転させてこっちに見せた。
「わあ、ありがとうございます!」
「お! 似てる! かわいらしい」
「ハハハ。この辺とかね、線は少なめにしましたよ^^」
ありがとうございます。こんな風に描いてもらえるなんて。

「今日は畑に行く時間はないですね。じゃあ、キクイモの写真はあっちゃんが撮って、僕に送ってください。じゃあ、今日はこれで帰りますね。ありがとうございました」
「ありがとうございました」
ということで、11月の『あっちゃんの三瀬村お野菜時期』の取材が終わった。
読者のみなさん。来月も楽しみにしてくださいね。




菊芋パウダー(みつせ村農園オンラインショップ)

https://mitsuse.official.ec/items/18307129
--------------------------------------------------------------
【イヌリンの効果】
イヌリンとは水溶性の食物繊維の一種で血糖値の上昇を抑える働きがあり、イヌリンは体内に吸収されることがありません。
水溶性食物繊維のため、腸内で水分を吸収してゲル状になり、一緒に摂った糖質の吸収を抑制する働きがあります。
また、腸のぜん動運動を促進や腸内でフラクトオリゴ糖となるため、玉菌のエサとしても働くといわれています。
--------------------------------------------------------------
2022年11月20日
話し手:川﨑淳子(三瀬在住の農家)
文:川浪秀之
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
口ひげを生やした七十歳くらいの男性が一緒だった。
数日前に電話で話したときに、似顔絵画家を連れてくると言っていたので、その人だろうと思った。
「Oといいます。今日はよろしくお願いします」
普段はデザインの仕事をしていらっしゃるみたいで、芸術家のような風采だ。
「似顔絵描かせてくださいね」
「ええ。それはいいですけど、急に用事ができて、三十分しか時間が取れないけど、大丈夫ですか?」
「10分くらいで描きますよ」とOさん。
「あ、そうなんですね」
「じゃあ、似顔絵を描かせてもらいながら、話を聞かせてください」
「わたし、どうしたらいいですか?」
「座ってもらっててよかですよ。川浪君と話よってください。適当に描きますから」
似顔絵なんて描いてもらったことないので、なんだか恥ずかしい。
O画家は、わたしの斜め前の椅子に深く座って、紙袋から色紙と、100円ショップで買ったという絵具付きのプラスチックパレットを取り出した。
そして、わたしの顔の全体を眺めると、おもむろに黒マジックのキャップを外して、いきおいよく右手を動かしていった。
色紙の裏しか見えないので、どんなふうに描いているのか判らない。
「そうそう。ブログに掲載した10月の聞き書きエッセイは、まだあんまり見られていませんけど、ぼちぼちアクセス増えてくると思いますから」
どんな人が見てくれるのかわからないけど、一人でも読んでくださった方がいるのなら、それは嬉しい。
「今月はキクイモですね。キクイモって、あんまり食べたことが無くて。生姜みたいなやつでしょう? 一度生姜と間違って買って帰ったことがあって、、品名見てなくて、、」
「笑 怒られたでしょう?」
「ノーコメントで^^」
「食べたことないって人が多いのかな? どうかなあ?」
「数年前から産直店とかでよく見かけるようになった印象なんですけど、それまではあまり見なかったと思いますけど?」
「そうね。いまから8年前くらいからかな。わたしたちも北海道と長野県から種芋をもらって、それで作るようになったのよ」
「へえ。そうだったのですね。それまでは三瀬村には無かった? 作って無かった?」
「ううん。あったのはあった。この辺では、てんちく芋とかてんつく芋っていっていて、その辺の山に自生しているのがあるのはあるのよ。9月ごろに菊のような黄色い花が咲くの。そのてんちく芋を掘って、酢漬けとか味噌漬けとかにして食べてはいたのよ」
「味噌漬けは食べたことあったよ」
Oさんが口を挟んだ。Oさんはたしか福岡の糸島あたりの出身だった。三瀬のとなりの富士町の山を越えるとすぐに糸島で、雷山・脊振山系の土地柄ではある。
「てんちく芋? てんつく? どういう漢字書くのですか?」
「漢字?」
わからない。。考えたことなかった。どういう漢字当てるのだろう。
(川浪氏があとでインターネットで調べたところ、キクイモのことを、てんちく芋、てんつく芋という言い方は何も情報が無かったみたいだ。三瀬村だけの呼び名なのかもしれない。ちなみに青森ではキクイモのことをカライモというらしい)
「それで、キクイモにはイヌリンが含まれているって、食べたら健康に良いっていって、三瀬村でも作ろうってことになってね。そのまま売ったり、キクイモパウダーにして売ってもらっているの」
「キクイモは、今の時期なのですか?」
「そうね。10月下旬から3月まで」
「種芋を植えて育てるのですか?」
「3月に種芋を植えて、あとはほったらかし^^」
「ほったらかしでいいのですか? 冬の霜は? 里芋は霜に弱かったけど」
「キクイモは強いけんね、ほったらかしでいいとよね。霜にも強か。家の畑に植えるだけで手のかからんけん、自分で作っている人も増えているみたい。三年前くらいまでは店でも売れていたけど、いまも売れるのは売れるけど、去年くらいからちょっと減った気がする。でも畑に植えるときは、気をつけとかんと、どうかするとどんどん根が広がっていくけんね」
「おすすめの食べ方は?」
「そうね。スライスして、きんぴら、天ぷら、酢の物。スープの具にしたり、すりおろしてポタージュにしたり。生でサラダに入れても美味しいよね」
「キクイモ酢ってありますよね? どっかで見たような?」
「わたしたちもキクイモ酢作っていた。いまは作ってないけど」
「出来たよ」
Oさんが、来る途中に、佐賀大学近くのワタナベ画材店で買った筆洗器に絵筆を差して、もぞもぞと濯いだ。そして色紙をくるりと反転させてこっちに見せた。
「わあ、ありがとうございます!」
「お! 似てる! かわいらしい」
「ハハハ。この辺とかね、線は少なめにしましたよ^^」
ありがとうございます。こんな風に描いてもらえるなんて。

「今日は畑に行く時間はないですね。じゃあ、キクイモの写真はあっちゃんが撮って、僕に送ってください。じゃあ、今日はこれで帰りますね。ありがとうございました」
「ありがとうございました」
ということで、11月の『あっちゃんの三瀬村お野菜時期』の取材が終わった。
読者のみなさん。来月も楽しみにしてくださいね。




菊芋パウダー(みつせ村農園オンラインショップ)

https://mitsuse.official.ec/items/18307129
--------------------------------------------------------------
【イヌリンの効果】
イヌリンとは水溶性の食物繊維の一種で血糖値の上昇を抑える働きがあり、イヌリンは体内に吸収されることがありません。
水溶性食物繊維のため、腸内で水分を吸収してゲル状になり、一緒に摂った糖質の吸収を抑制する働きがあります。
また、腸のぜん動運動を促進や腸内でフラクトオリゴ糖となるため、玉菌のエサとしても働くといわれています。
--------------------------------------------------------------
2022年11月20日
話し手:川﨑淳子(三瀬在住の農家)
文:川浪秀之
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
2022年11月15日
北山ダムのヘラブナ釣り(終章)
前回の続きから
三瀬で一番有名な産直店、まっちゃん、から釣り場へ戻った。Kさんが釣りを再開した。
八女から来た方は、僕たちが釣り座を離れた間も、快調に釣り上げていたみたいで、入れ喰い状態になっている。
地合いができているということのなのだろう。
「振り込み方とかアワセ方とか、よく見ておいたらいいですよ」と、Kさんが言った。
八女の方は力感なく、振り込み、素早くアワセる。
「また乗りましたばい」といい、いつも行っている筑後の釣り場と比べて、北山ダムの魚影の濃さと、型の良さに満足する言葉を発した。
初めてなので、何も知らないのだが、北山ダムのヘラブナは型が良いのだそうだ。尺上(しゃっかみ)が普通に釣れるという。
そうこうしているうちに、午後2時になった。
「いま何枚くらいですか?」とKさんが八女の方に訊いた。
「あと1枚で90枚です。あと1枚釣れたら終わりにします」
そろそろ納竿しないと、家に着くのが遅くなるから、ということだった。
ほどなくラストの1枚を釣り上げて、八女の方は納竿した。「また来るときは連絡ばしますね」といって、車に乗って帰っていった。
Kさんが僕に、交代しましょうか? といって竿を預けた。
「ちょっと波が出てきて、浮子(ウキ)が見えにくくなってきたので、これかけてやってみてください」
といって、眼鏡の上からかけるタイプの偏光グラスを貸してくれた。
日差しと、さざ波で、湖面がチラチラと光って、裸眼では浮子がどこにあるのかよく見えない。凝視しても見えないし、裸眼のままで長く見ていると、湖面から反射する光で目がやられそうな気がした。
僕は再び、日よけのパラソルの下で、釣り座にあぐらをかいて偏光グラスをつけて竿を振った。
偏光グラスをかけた視界は、黄色のセロファンを通して見える世界だった。
湖面に垂直に立った浮子に神経を集中する。
不思議なもので、気のせいなのだが、耳に入ってくる自然の音も遮断されたみたいで、辺りがしんと静まり返った感じがする。
さっきまで聞こえていた、車の走る音、鳥の声、風の音など一切の音が消えて、僕と竿と浮子が、一直線に並んでいる。
ただただ、目の前の浮子を見ている。それ以外は目に入らない。
なんともいえない無の境地だ。
そのとき、ふと、
「あー、これはヘラブナ釣りにはまるかもしれんな」と思った。
左手でマッシュポテトを握って、丸め、上下二本のハリに付けて、目の前に振り込む。
餌とウキが着水する。寝ていた浮子が起き上がる。そして、沈下しはじめて、水面から消える。
数秒後、浮子のトップが水面から現れる。そしてゆっくりとトップが上にあがってくる。
サワリがある。アタリがあればアワセる。
乗るときもあれば、空振りするときもある。
竿を上げて、餌の無くなったハリを手元に戻して掴む。
そしてすぐに左手に握ったマッシュポテトをハリに付けて、目の前に振り込む。
もくもくと、その動作を繰り返す。
単調な動作の繰り返しなのだが、なんだか心地よいのだ。
Kさんもしばらく僕に話しかけてこなかった。
そうやって、僕は5枚くらいを釣り上げた。初めてのへら釣り経験で、全部で10枚くらい釣ることができた。もちろんKさんが朝から先に来て準備をしてくれたり、餌の打ち方、アワセ方など、一から十まで教えてくれたおかげである。
午後4時になっていた。僕はKさんに今日のお礼をいった。
「またぜひ行きましょう。もし続けれるようだったら、けっして無理せずに、へら釣りやってみてください」
「お盆に秋田のトガシさんのところへ行く前に、もう1回は練習したいので、また教えてください」
「ぜひぜひ^^」
僕は、先に釣り座を離れて、北山ダムをあとにした。五月の中旬のことだった。
僕のはじめてのヘラブナ釣りは、これにておしまい。
追伸
その日の夜、Kさんからメッセージが届いた。
「結局あのあと入れ喰いになって、18時まで釣って100枚になりましたよ^^」
その後、単独で北山ダムにへら釣りに行った際に撮った写真

---------------------
2022年11月15日
川浪秀之(Webプロデューサー、作家)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
三瀬で一番有名な産直店、まっちゃん、から釣り場へ戻った。Kさんが釣りを再開した。
八女から来た方は、僕たちが釣り座を離れた間も、快調に釣り上げていたみたいで、入れ喰い状態になっている。
地合いができているということのなのだろう。
「振り込み方とかアワセ方とか、よく見ておいたらいいですよ」と、Kさんが言った。
八女の方は力感なく、振り込み、素早くアワセる。
「また乗りましたばい」といい、いつも行っている筑後の釣り場と比べて、北山ダムの魚影の濃さと、型の良さに満足する言葉を発した。
初めてなので、何も知らないのだが、北山ダムのヘラブナは型が良いのだそうだ。尺上(しゃっかみ)が普通に釣れるという。
そうこうしているうちに、午後2時になった。
「いま何枚くらいですか?」とKさんが八女の方に訊いた。
「あと1枚で90枚です。あと1枚釣れたら終わりにします」
そろそろ納竿しないと、家に着くのが遅くなるから、ということだった。
ほどなくラストの1枚を釣り上げて、八女の方は納竿した。「また来るときは連絡ばしますね」といって、車に乗って帰っていった。
Kさんが僕に、交代しましょうか? といって竿を預けた。
「ちょっと波が出てきて、浮子(ウキ)が見えにくくなってきたので、これかけてやってみてください」
といって、眼鏡の上からかけるタイプの偏光グラスを貸してくれた。
日差しと、さざ波で、湖面がチラチラと光って、裸眼では浮子がどこにあるのかよく見えない。凝視しても見えないし、裸眼のままで長く見ていると、湖面から反射する光で目がやられそうな気がした。
僕は再び、日よけのパラソルの下で、釣り座にあぐらをかいて偏光グラスをつけて竿を振った。
偏光グラスをかけた視界は、黄色のセロファンを通して見える世界だった。
湖面に垂直に立った浮子に神経を集中する。
不思議なもので、気のせいなのだが、耳に入ってくる自然の音も遮断されたみたいで、辺りがしんと静まり返った感じがする。
さっきまで聞こえていた、車の走る音、鳥の声、風の音など一切の音が消えて、僕と竿と浮子が、一直線に並んでいる。
ただただ、目の前の浮子を見ている。それ以外は目に入らない。
なんともいえない無の境地だ。
そのとき、ふと、
「あー、これはヘラブナ釣りにはまるかもしれんな」と思った。
左手でマッシュポテトを握って、丸め、上下二本のハリに付けて、目の前に振り込む。
餌とウキが着水する。寝ていた浮子が起き上がる。そして、沈下しはじめて、水面から消える。
数秒後、浮子のトップが水面から現れる。そしてゆっくりとトップが上にあがってくる。
サワリがある。アタリがあればアワセる。
乗るときもあれば、空振りするときもある。
竿を上げて、餌の無くなったハリを手元に戻して掴む。
そしてすぐに左手に握ったマッシュポテトをハリに付けて、目の前に振り込む。
もくもくと、その動作を繰り返す。
単調な動作の繰り返しなのだが、なんだか心地よいのだ。
Kさんもしばらく僕に話しかけてこなかった。
そうやって、僕は5枚くらいを釣り上げた。初めてのへら釣り経験で、全部で10枚くらい釣ることができた。もちろんKさんが朝から先に来て準備をしてくれたり、餌の打ち方、アワセ方など、一から十まで教えてくれたおかげである。
午後4時になっていた。僕はKさんに今日のお礼をいった。
「またぜひ行きましょう。もし続けれるようだったら、けっして無理せずに、へら釣りやってみてください」
「お盆に秋田のトガシさんのところへ行く前に、もう1回は練習したいので、また教えてください」
「ぜひぜひ^^」
僕は、先に釣り座を離れて、北山ダムをあとにした。五月の中旬のことだった。
僕のはじめてのヘラブナ釣りは、これにておしまい。
追伸
その日の夜、Kさんからメッセージが届いた。
「結局あのあと入れ喰いになって、18時まで釣って100枚になりましたよ^^」
その後、単独で北山ダムにへら釣りに行った際に撮った写真

---------------------
2022年11月15日
川浪秀之(Webプロデューサー、作家)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
2022年11月10日
三瀬に残る中世の雰囲気・方言あれこれ
佐賀県全体の方言としては志津田藤四郎先生らの詳しい報告がありますが、時間もないので頭に浮かぶ代表的なものとしてよく挙げられるのが「とぜんなか」でしょうか。
「とぜんなか」は、『徒然草』の「徒然」という字から出ているわけで中世の言葉です。
「淋しい」という強さでもなく、もちろん嬉しいでもない。正に『徒然草』が言うように、「心に浮かぶよしなしごとを…」みたいにぼんやりと考えを廻らしたり…。そんな雰囲気を表しているわけですね。
現在のいわゆる共通語や標準語では到底出せない雰囲気があると思います。私が小さいころ三瀬に帰って、今はもう亡くなってしまったおばっちゃん達が「孝ちゃん帰るね。母さんな徒然なかね」などと言われたものです。
先日、JVCケンウッド社長の江口祥一郎氏の講演会を主宰したところ、彼はいの一番にこの方言を話されました。
こうして全国的に見て、方言には古語や漢語が含まれていることが多いわけです。
例えば、きつねを「やこ」と言うのは、字で書けば「野狐」ですし、柿のことを「じゅくし」と言いますが、これは「熟柿」という漢字で書くわけです。『葉隠』の山本常朝が書いた『寿量庵中座の日記』の中にも、「熟柿にかよう山烏(からす)」などという話が出てきますから、享保の頃にはよく使われた言葉かもしれません。三瀬の言葉の中に中世や江戸がしっかり残っているということでしょう。
しかし、そういう傾向も徐々に無くなりつつあるように思います。
例えば、稲を肩に担ぐ「かたげる」という言葉は、最近のようにお米を作る家が徐々に減れば、「かたげる」こと自体もなくなりますから、いずれ無くなってしまうかもしれません。「かたげる」については、物を斜めにするという意味で使っている地方もあると紹介されたりしますが、それは「傾ける」という字から出ているわけですから、「担う」という字から出ている「かたげる」とは出自が異なるものでしょう。この辺りは全国的に混ざったりして、場所によって混同されているかもしれません。
伊達政宗の亡くなる前を記した『名語集』には、
「或時の事なるに、若林御城の川除御普請過ぎ候て、御咄に、・・・(政宗は)南次郎吉と云ふ小姓を相手にして、如何にもむさき畚(もっこ)に土を入れ、各すすめやすすめや、我等も自身此の有様見よとて、六七度かたげ候故、下々は申すに及ばず、諸侍其の外、普請見物にとて、町々在々の者、川に並居たる者どもまで自ら進みたてられ、一度におめきさけびて、土砂くれ何によらず、手に当るを幸と、持ち寄り持ち寄り、水をせき候故、さばかりの大川なれども、我れ一人の下知に依って、片時ばかりに普請進みしが、かやうの事に付けても、昔なつかしきなり。」
とありますから、九州と全く同じ用法が仙台にもあったということだと思います。これは、古代から、言葉は京都から広がったので、同心円状に九州にも東北にも同じ言葉がある、ということの一つの典型例なのかもしれません。
こういう種類の言葉は雰囲気や動作ですから、そう簡単にはなくならないかもしれませんが、目に見えるもの、例えば、「みゃーらど」は、「みゃーらど」がなくなることによって本当になくなってしまうかもしれません。「みゃーらど」は舞良戸と書く引戸で、要は間仕切りとして木の板を貼った引き戸、重いふすまのようなものです。
ちなみに、教科書等に載っている舞良戸は細い桟が横に貼ってありますが、三瀬の場合は縦だというのは、一般的な舞良戸ではないものを言うのかもしれませんが。
三瀬村でも真っ黒い大黒柱や真っ黒い梁、真っ黒い天井、そして濃い飴色の「みゃーらど」という家が急速になくなっていっています。
一方、今は現代建築、マンションの中などに舞良戸を使用するということもあるようで、通信販売などで売っているのを見てびっくりしました。
三瀬の新しい家にこういうものを使えば「みゃーらど」という言葉も残っていくのかもしれません。
---------------------
2022年11月10日
嘉村孝
(三瀬出身。東京で「葉隠フォーラム」という名の歴史学者参加の勉強会を主宰。毎月開催で250回を数える。)
http://hagakurebushido.jp/
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
「とぜんなか」は、『徒然草』の「徒然」という字から出ているわけで中世の言葉です。
「淋しい」という強さでもなく、もちろん嬉しいでもない。正に『徒然草』が言うように、「心に浮かぶよしなしごとを…」みたいにぼんやりと考えを廻らしたり…。そんな雰囲気を表しているわけですね。
現在のいわゆる共通語や標準語では到底出せない雰囲気があると思います。私が小さいころ三瀬に帰って、今はもう亡くなってしまったおばっちゃん達が「孝ちゃん帰るね。母さんな徒然なかね」などと言われたものです。
先日、JVCケンウッド社長の江口祥一郎氏の講演会を主宰したところ、彼はいの一番にこの方言を話されました。
こうして全国的に見て、方言には古語や漢語が含まれていることが多いわけです。
例えば、きつねを「やこ」と言うのは、字で書けば「野狐」ですし、柿のことを「じゅくし」と言いますが、これは「熟柿」という漢字で書くわけです。『葉隠』の山本常朝が書いた『寿量庵中座の日記』の中にも、「熟柿にかよう山烏(からす)」などという話が出てきますから、享保の頃にはよく使われた言葉かもしれません。三瀬の言葉の中に中世や江戸がしっかり残っているということでしょう。
しかし、そういう傾向も徐々に無くなりつつあるように思います。
例えば、稲を肩に担ぐ「かたげる」という言葉は、最近のようにお米を作る家が徐々に減れば、「かたげる」こと自体もなくなりますから、いずれ無くなってしまうかもしれません。「かたげる」については、物を斜めにするという意味で使っている地方もあると紹介されたりしますが、それは「傾ける」という字から出ているわけですから、「担う」という字から出ている「かたげる」とは出自が異なるものでしょう。この辺りは全国的に混ざったりして、場所によって混同されているかもしれません。
伊達政宗の亡くなる前を記した『名語集』には、
「或時の事なるに、若林御城の川除御普請過ぎ候て、御咄に、・・・(政宗は)南次郎吉と云ふ小姓を相手にして、如何にもむさき畚(もっこ)に土を入れ、各すすめやすすめや、我等も自身此の有様見よとて、六七度かたげ候故、下々は申すに及ばず、諸侍其の外、普請見物にとて、町々在々の者、川に並居たる者どもまで自ら進みたてられ、一度におめきさけびて、土砂くれ何によらず、手に当るを幸と、持ち寄り持ち寄り、水をせき候故、さばかりの大川なれども、我れ一人の下知に依って、片時ばかりに普請進みしが、かやうの事に付けても、昔なつかしきなり。」
とありますから、九州と全く同じ用法が仙台にもあったということだと思います。これは、古代から、言葉は京都から広がったので、同心円状に九州にも東北にも同じ言葉がある、ということの一つの典型例なのかもしれません。
こういう種類の言葉は雰囲気や動作ですから、そう簡単にはなくならないかもしれませんが、目に見えるもの、例えば、「みゃーらど」は、「みゃーらど」がなくなることによって本当になくなってしまうかもしれません。「みゃーらど」は舞良戸と書く引戸で、要は間仕切りとして木の板を貼った引き戸、重いふすまのようなものです。
ちなみに、教科書等に載っている舞良戸は細い桟が横に貼ってありますが、三瀬の場合は縦だというのは、一般的な舞良戸ではないものを言うのかもしれませんが。
三瀬村でも真っ黒い大黒柱や真っ黒い梁、真っ黒い天井、そして濃い飴色の「みゃーらど」という家が急速になくなっていっています。
一方、今は現代建築、マンションの中などに舞良戸を使用するということもあるようで、通信販売などで売っているのを見てびっくりしました。
三瀬の新しい家にこういうものを使えば「みゃーらど」という言葉も残っていくのかもしれません。
---------------------
2022年11月10日
嘉村孝
(三瀬出身。東京で「葉隠フォーラム」という名の歴史学者参加の勉強会を主宰。毎月開催で250回を数える。)
http://hagakurebushido.jp/
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
2022年11月01日
山の魅力に溢れた“三瀬村 ふれあい祭り”
「3年ぶりにふれあい祭りが開催される」
三瀬村の人から、その知らせを聞きつけ、僕が会場を訪れたのは先月10月22日、土曜日のことでした。
高く抜けた秋空の下、三瀬小学校のグランドは3年ぶりに村の人たちの活気に溢れていました。ステージでは子供たちが生き生きとダンスを踊り、消防局の楽団が音楽を生演奏し、会場を沸かせています。周りのテントでは、サツマイモやキャベツなどの取れたての野菜を売る威勢のいい村の人たちの声が飛び交い、そこに嬉しそうな観光客の声が混じります。
その隙間を縫うように、ふるまいのイノシシ焼肉やしし汁の食欲をそそる香りが立ち込めてきます。祭りの会場はまさに“山の魅力”に溢れていました。訪れた人たちはそれぞれのテントに立ち寄り、村の人たちと明るく声を交わします。地元の子供たちや学校や仕事で村を離れて暮らしている人たちも訪れ、久しぶりの故郷の祭りを楽しんでいました。
「三瀬村・田舎と都市(まち)のふれあい祭り」
今年で36回目を迎える、この祭りは隣接する福岡を中心とした都市の人たちに向け、村の魅力を知ってもらう為に開かれてきました。
地場産品を扱う部会、商工会や地元の飲食店、農園など16ほどの団体が店を出し、都市部から訪れる人たちをもてなすのです。村の人たちは、この日に向けて名産のゆずごしょうや様々な野菜、食材加工品などを準備し、祭りを通して村外の人たちと文字通り、“ふれあう”機会を楽しみにしてきました。訪れる常連客にとっても、この祭りは三瀬の魅力が凝縮した、楽しみな行事です。
しかし、ここ2年、コロナ禍の為、祭りは中止となり、村では寂しい秋が続いていました。
会場で村の人たちに話を聞くと、祭りの再開の喜びと共に複雑な心境を語ってくれました。
「まだコロナ感染を懸念して止めた方がいいのではないか、という声もあった。でも祭りに携わり、続けてきた人たちは再開を待ち望んでいたし、是非、やりたいという思いもあった」
その言葉を聞いて、僕は今年、この祭りが再開され、本当によかったと心から思いました。仕事の中で様々なお祭りごとを取材してきた僕は、そういった取り組みが何かしらの理由によって一度、中止された後、そのまま再開されることなくなくなっていった事例を数多く見てきました。
「中止することは容易だが、再開は難しい」
とかつての取材先の人が漏らしていた言葉が未だに頭の片隅に残っていたからです。
しかし、閉塞感の中、じっとしていても何も始まらないこともまた事実。現に祭りの会場は、コロナ前に取材した時よりも出店数が減ってはいたものの、人々の顔には以前の祭りとはまた違った深い喜びの色があったことが僕には嬉しく感じられたのです。
祭りの中で、特に印象深かったのは「三瀬もりの会」という森の保全活動を行う団体の人たちの様子です。佐賀市の委託を受け、森の保全活動を進める為、もりの会の人たちは訪れる人たちに募金を求めます。そして募金してくれた人にはイロハモミジ、コブシ、コムラサキ、ヤマツツジといった樹木の苗木をプレゼントします。
その様子を見ていると、苗木を渡し、受け取るやりとりの中には明るい笑い声が聞こえてきました。会の人に話を聞くと「かつて募金してくれた人が、「苗木がこんなに大きな木になった」といって写真を見せによってくれる。そんな常連さんとの再会が嬉しい」と、その喜びの心情を話してくれました。
祭りは小さな苗木が、大きく成長するまでの長い年月、村の人たちと常連客との縁をつないでいたのだ。僕にはそう思えました。
年に一度、村外の三瀬ファンをもてなす「ふれあい祭り」。それはただのイベントではなく、村の人たちが常連客との絆を確かめ合い、深める為の大切な行事です。
この先も祭りが大切に受け継がれていって欲しいと僕は切に願っています。





---------------------
2022年11月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
三瀬村の人から、その知らせを聞きつけ、僕が会場を訪れたのは先月10月22日、土曜日のことでした。
高く抜けた秋空の下、三瀬小学校のグランドは3年ぶりに村の人たちの活気に溢れていました。ステージでは子供たちが生き生きとダンスを踊り、消防局の楽団が音楽を生演奏し、会場を沸かせています。周りのテントでは、サツマイモやキャベツなどの取れたての野菜を売る威勢のいい村の人たちの声が飛び交い、そこに嬉しそうな観光客の声が混じります。
その隙間を縫うように、ふるまいのイノシシ焼肉やしし汁の食欲をそそる香りが立ち込めてきます。祭りの会場はまさに“山の魅力”に溢れていました。訪れた人たちはそれぞれのテントに立ち寄り、村の人たちと明るく声を交わします。地元の子供たちや学校や仕事で村を離れて暮らしている人たちも訪れ、久しぶりの故郷の祭りを楽しんでいました。
「三瀬村・田舎と都市(まち)のふれあい祭り」
今年で36回目を迎える、この祭りは隣接する福岡を中心とした都市の人たちに向け、村の魅力を知ってもらう為に開かれてきました。
地場産品を扱う部会、商工会や地元の飲食店、農園など16ほどの団体が店を出し、都市部から訪れる人たちをもてなすのです。村の人たちは、この日に向けて名産のゆずごしょうや様々な野菜、食材加工品などを準備し、祭りを通して村外の人たちと文字通り、“ふれあう”機会を楽しみにしてきました。訪れる常連客にとっても、この祭りは三瀬の魅力が凝縮した、楽しみな行事です。
しかし、ここ2年、コロナ禍の為、祭りは中止となり、村では寂しい秋が続いていました。
会場で村の人たちに話を聞くと、祭りの再開の喜びと共に複雑な心境を語ってくれました。
「まだコロナ感染を懸念して止めた方がいいのではないか、という声もあった。でも祭りに携わり、続けてきた人たちは再開を待ち望んでいたし、是非、やりたいという思いもあった」
その言葉を聞いて、僕は今年、この祭りが再開され、本当によかったと心から思いました。仕事の中で様々なお祭りごとを取材してきた僕は、そういった取り組みが何かしらの理由によって一度、中止された後、そのまま再開されることなくなくなっていった事例を数多く見てきました。
「中止することは容易だが、再開は難しい」
とかつての取材先の人が漏らしていた言葉が未だに頭の片隅に残っていたからです。
しかし、閉塞感の中、じっとしていても何も始まらないこともまた事実。現に祭りの会場は、コロナ前に取材した時よりも出店数が減ってはいたものの、人々の顔には以前の祭りとはまた違った深い喜びの色があったことが僕には嬉しく感じられたのです。
祭りの中で、特に印象深かったのは「三瀬もりの会」という森の保全活動を行う団体の人たちの様子です。佐賀市の委託を受け、森の保全活動を進める為、もりの会の人たちは訪れる人たちに募金を求めます。そして募金してくれた人にはイロハモミジ、コブシ、コムラサキ、ヤマツツジといった樹木の苗木をプレゼントします。
その様子を見ていると、苗木を渡し、受け取るやりとりの中には明るい笑い声が聞こえてきました。会の人に話を聞くと「かつて募金してくれた人が、「苗木がこんなに大きな木になった」といって写真を見せによってくれる。そんな常連さんとの再会が嬉しい」と、その喜びの心情を話してくれました。
祭りは小さな苗木が、大きく成長するまでの長い年月、村の人たちと常連客との縁をつないでいたのだ。僕にはそう思えました。
年に一度、村外の三瀬ファンをもてなす「ふれあい祭り」。それはただのイベントではなく、村の人たちが常連客との絆を確かめ合い、深める為の大切な行事です。
この先も祭りが大切に受け継がれていって欲しいと僕は切に願っています。





---------------------
2022年11月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com