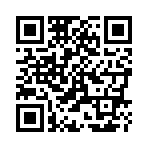2023年05月10日
神代勝利公にまつわる遺跡など
三瀬の人にとって戦国時代の一番の英雄はなんといっても神代勝利公でしょう。その居城は三瀬城であり、宿はその城下町です。勝玉神社は無事ですが、昭和38年(1963年)観音寺が焼けたのは残念でした。
三瀬城は、その昔登ってみた経験から言うと、縄張りは連郭式。曲輪の配置が本丸の目の前に二の丸がある、という形ですが、曲輪自体はさほど大規模ではありません。ただ、関東は土塁主体であるのに対して、関西(九州)らしく石垣がしっかりあるのが特徴かと思います。
神代勝利公は、龍造寺・鍋島と戦いましたが、その支配圏は尼寺の南にまで及んでいました。元々北部九州の主と言えた少弐を担いでいたわけですが新興勢力の勢いには抗しがたく二回に渡って山内を追い出されましたが、最終的には復帰し、畑瀬に閑居して息子の長良に後を譲り、永禄8年(1565年)、畑瀬城に没しました。彼を葬った宗源院は、嘉瀬川ダムの都合で墓もやや上ったところに移されていますが、当時の佇まいは残っているようです。
まずこのお墓ですが、宝篋印塔と呼ばれるものです。宝篋印塔は元々中国の呉越国(907~978)の王・銭弘俶が父母の菩提をとむらうために、印度のアショカ王の故事に習って作った八万四千の小塔に由来するとされ、鎌倉以来武士の供養塔などがあります。関東型、関西型があり、時代の変化もあって面白いものです。
勝利公の場合は、少々細くてさほど豪華版とはいえない、そこがまあ良いところかもしれません。三瀬村内には、これよりも更に中世的かつ立派な宝篋印塔の残欠も見られますが、こちらはやや近世に近い、むしろ近世になって建て替えられたものかもしれません。ただ、小型なのは、その「政敵」であった鍋島直茂と共通する素晴らしさとも言える気がします。
直茂は、自身の墓を小さなものにするように、ただし、敵・神代一党に向けて作るように遺言しました。今の佐賀市宗智寺の話です。
「日峯様(直茂)御遺言に任せ、多布施御隠居を転じて…寺地御取立あり。……兼て思召入られ候御賢慮の儀は、此の以後若し乱世にも相成り候はば、他国より必ず佐嘉へ人数を差向くべき事ある時に、北山筋の儀至って大切の儀と思召され候。右の所へ御遺骸御納まり御座成され候はば、御家中の者共定めて敵の馬の蹄には懸け申すまじと覚悟致すべく候。多布施より内に敵を入れ立て申さず候はば、佐嘉は持ち堪へ申すべしとの御賢慮にて候由。」と。
小さな墓でも、神代方に向けておけば、家来は殿さまの墓が蹴とばされては大変だ、と頑張るだろうという「ご賢慮」による、というのです。プロシヤのフリードリッヒ大王の墓も小さく、英雄共通かもしれません。
そんなわけで、陣内の万福寺には勝利公の孫・千寿丸の墓とか様々な故地があり、先にも書きましたが、私が産まれた家の南側には、小さな池があって、叔母の話しによると、神代勝利公の軍勢が馬に水をやった所とのこと。あちこちで水をあげたのでしょうから、その一つかもしれません。
さらに、よりアクティブな行動を思わせてくれるのが、大日橋から下ったところにある「よいあんでゃーら(寄合平)」でしょうか。弘治3年(1557年)の金鋪峠の戦いに当たっては、高野岳から大鐘を鳴り響かせて北山諸郷の軍勢がそこに集まり名尾筋、三反田筋に向かったと言われます。
その他、三瀬にも富士町にもあちこちに城つまりは砦があって、それぞれ興味が持たれますが、私が特に面白いと思うのは、263号線を福岡側に下って右に曲がった所水源地の向かいにある曲渕城です。神代と最後には同盟した曲渕氏の城です。入口には山神社と書いた小さな鳥居が見えるだけですが、ここから上に登るのは、極めて急で大変です。登りきったところに小さな社がありますが、その裏は、どーんと下に落ちています。つまり、いざとなったら渡してある橋を落として避難する仕組みでしょう。上記の通り関西の城は、どちらかというと石垣が多く、三瀬城にも石垣があって感動しますが、こちらの曲淵城では、私は今のところ石垣を見ていません。しかし、その防御施設としての厳しさは、相当なもので、龍造寺隆信もこの道を通って博多を焼き討ちしに行ったという話しですから、色々なドラマがあったのではないかと思います。
こうして三瀬の「周り」との対比も面白いのではないかと思います。
---------------------
2023年5月10日
嘉村孝
(三瀬出身。東京で「葉隠フォーラム」という名の歴史学者参加の勉強会を主宰。毎月開催で250回を数える。)
http://hagakurebushido.jp/
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
三瀬城は、その昔登ってみた経験から言うと、縄張りは連郭式。曲輪の配置が本丸の目の前に二の丸がある、という形ですが、曲輪自体はさほど大規模ではありません。ただ、関東は土塁主体であるのに対して、関西(九州)らしく石垣がしっかりあるのが特徴かと思います。
神代勝利公は、龍造寺・鍋島と戦いましたが、その支配圏は尼寺の南にまで及んでいました。元々北部九州の主と言えた少弐を担いでいたわけですが新興勢力の勢いには抗しがたく二回に渡って山内を追い出されましたが、最終的には復帰し、畑瀬に閑居して息子の長良に後を譲り、永禄8年(1565年)、畑瀬城に没しました。彼を葬った宗源院は、嘉瀬川ダムの都合で墓もやや上ったところに移されていますが、当時の佇まいは残っているようです。
まずこのお墓ですが、宝篋印塔と呼ばれるものです。宝篋印塔は元々中国の呉越国(907~978)の王・銭弘俶が父母の菩提をとむらうために、印度のアショカ王の故事に習って作った八万四千の小塔に由来するとされ、鎌倉以来武士の供養塔などがあります。関東型、関西型があり、時代の変化もあって面白いものです。
勝利公の場合は、少々細くてさほど豪華版とはいえない、そこがまあ良いところかもしれません。三瀬村内には、これよりも更に中世的かつ立派な宝篋印塔の残欠も見られますが、こちらはやや近世に近い、むしろ近世になって建て替えられたものかもしれません。ただ、小型なのは、その「政敵」であった鍋島直茂と共通する素晴らしさとも言える気がします。
直茂は、自身の墓を小さなものにするように、ただし、敵・神代一党に向けて作るように遺言しました。今の佐賀市宗智寺の話です。
「日峯様(直茂)御遺言に任せ、多布施御隠居を転じて…寺地御取立あり。……兼て思召入られ候御賢慮の儀は、此の以後若し乱世にも相成り候はば、他国より必ず佐嘉へ人数を差向くべき事ある時に、北山筋の儀至って大切の儀と思召され候。右の所へ御遺骸御納まり御座成され候はば、御家中の者共定めて敵の馬の蹄には懸け申すまじと覚悟致すべく候。多布施より内に敵を入れ立て申さず候はば、佐嘉は持ち堪へ申すべしとの御賢慮にて候由。」と。
小さな墓でも、神代方に向けておけば、家来は殿さまの墓が蹴とばされては大変だ、と頑張るだろうという「ご賢慮」による、というのです。プロシヤのフリードリッヒ大王の墓も小さく、英雄共通かもしれません。
そんなわけで、陣内の万福寺には勝利公の孫・千寿丸の墓とか様々な故地があり、先にも書きましたが、私が産まれた家の南側には、小さな池があって、叔母の話しによると、神代勝利公の軍勢が馬に水をやった所とのこと。あちこちで水をあげたのでしょうから、その一つかもしれません。
さらに、よりアクティブな行動を思わせてくれるのが、大日橋から下ったところにある「よいあんでゃーら(寄合平)」でしょうか。弘治3年(1557年)の金鋪峠の戦いに当たっては、高野岳から大鐘を鳴り響かせて北山諸郷の軍勢がそこに集まり名尾筋、三反田筋に向かったと言われます。
その他、三瀬にも富士町にもあちこちに城つまりは砦があって、それぞれ興味が持たれますが、私が特に面白いと思うのは、263号線を福岡側に下って右に曲がった所水源地の向かいにある曲渕城です。神代と最後には同盟した曲渕氏の城です。入口には山神社と書いた小さな鳥居が見えるだけですが、ここから上に登るのは、極めて急で大変です。登りきったところに小さな社がありますが、その裏は、どーんと下に落ちています。つまり、いざとなったら渡してある橋を落として避難する仕組みでしょう。上記の通り関西の城は、どちらかというと石垣が多く、三瀬城にも石垣があって感動しますが、こちらの曲淵城では、私は今のところ石垣を見ていません。しかし、その防御施設としての厳しさは、相当なもので、龍造寺隆信もこの道を通って博多を焼き討ちしに行ったという話しですから、色々なドラマがあったのではないかと思います。
こうして三瀬の「周り」との対比も面白いのではないかと思います。
---------------------
2023年5月10日
嘉村孝
(三瀬出身。東京で「葉隠フォーラム」という名の歴史学者参加の勉強会を主宰。毎月開催で250回を数える。)
http://hagakurebushido.jp/
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com