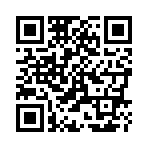2023年01月01日
“美しい里山” 三瀬村
“美しい里山”。
それは「三瀬ってどんなところ?」と尋ねられた時、浮かんできた言葉でした。でもそのまま口にしても、うまく伝わらないし、その理由を語ろうとすると長くなるので、僕はいつも「自然豊かで空気も食べ物もおいしい村だよ」と答えてしまっていました。今回は、そんな“美しい里山”について話です。
最初にそう感じたのは、取材を始めたばかりだった六年近く前の秋。取材の為、稲刈りを行う初老の男性に出会った時でした。日に焼けた男性の浅黒い肌には力強さが漲り、節くれだった手には内に身に秘めている苦労がにじみ出ていました。しかし、その男性は苦労などは一切、語らず、朗らかに「今年もよう実った。豊作よ」と言って笑いました。その背後にはまだ狩り残してある黄金の海が広がっていて、時折拭く秋風に身重の穂を大きく揺らしていました。
その光景に僕は、この実りの為に男性が掛けてきた苦労と時間、そしてそんな人々の営みの連続が里山を作り上げてきたことを想像し、それがそのまま人と山との関わりの歴史であることにも気づいて、三瀬村を“美しい里山”だと思ったのでした。
その印象は長年の取材の中で、今も確かに息づく人の営みの姿としてより具体的に像を結んでいくようになっていきました。
例えば冬。三瀬村は平野部とは全く違う様相を呈します。脊振山系の裾野に広がる標高400~500ほどの村のあちこちには雪が降り積もり、木々などで少しでも陰ったところはなかなか溶けることがありません。
佐賀駅周辺では見たこともないような、大きなつららが家の軒先に伸びている光景を僕は何度も目にしてきました。村の土木建築会社の人たちは冬場、天気予報を小まめにチェックしながら、困っている人たちがいないか村のあちこちを見回ります。雪の予報の出ている時には道路凍結防止の薬を散布したり、積雪後、塞がれてしまった生活道路の除雪をしたりするのです。この冬の厳しさへの対策は農家でも行われます。
ある女性の家では、氷点下の気候から収穫した里芋を守る為、畑に穴を掘って石灰をまき、その中に里芋を入れて藁で蓋をして土などを被せます。こうすることで冬場、里芋を貯蔵することが出来るのだそうです。今はほとんど行われていませんが、一昔前は、冬場は炭焼きが行われ、山のあちこちから煙が上がっていたのだそうです。
冬はそればかりではありません。年末に向けて行われる、収穫した稲わらを使ったしめ縄作り。田んぼで採れたもち米を使った餅つきに、畑で採れた蕎麦を粉にして農家自らが打ち、親戚や親類に配る年越しの傍作り。新年になれば、子どもたちが集落の家々を回り、無病息災を祈る七福神や櫓を汲んで火を炊くホンゲンギョウなどの行事も行われます。恐らく、僕が知らないだけで冬場に行われる大小さまざまな行事はまだたくさん、あるのだと思います。
こういった山に暮らす人々の営みは春から秋にかけても続いていきます。水路に水を引くための井手区役や水の恵みに感謝する川祭りと田植え。日照りで水が足りない年には、川の上流に田を持つ人がわざと米を作らず、下流の人の田の為にに水を流すといった光景も見られました。
初夏にはブルーベリー園も開園。さらに真夏になれば村の若者が夏祭りを開き、やがて運動会や村の産品を販売し、都市部の人と交流するふれあい祭りなども開催されます。稲刈りが終わるとそれぞれの集落の神社では、五穀豊穣を感謝する神社のお祭りが行われます。山の営みはそれだけではありません。暮らしを守る為、地域の消防団は山からの川の堰から水を取り、消火を行う訓練が定期的に行われています。
賑やかでひたむきな人々の山の営み。高台に上ると山と人とが紡いできた、その里山の光景を前にすると、僕はこの土地に暮らす人たちの生きざまにただただ頭を垂れる思いを抱くようになりました。そして昔、何かの本で読んだ「人間は自然界では一つの動物である。山でその生を営むことは、それそのものが奇跡であることを知らねばならない」という言葉を思い出したのです。恐らく、三瀬村の人たちが見ている世界は、町中に暮らす僕が見ているものよりもずっと広くて深いのです。
集落に子どもが生まれると、皆が祝いの言葉をささげ、子ど達は野山や川に親しんで遊ぶ。青年たちは勤めに出ながらも、集落の生活道路に伸びてくる山の草木を刈るために共同の草刈りに参加するし、集落ごとに地域の営みを守り、引き継いできた年配者へ感謝を伝える為の敬老会が開かれる。村の誰かが亡くなれば、皆で弔いながら葬儀も協力して行う。村の人たちは命というものの、かけがえのない大切さを日々の営みの中で常に感じながら、だからこそ今を懸命に生きている、だからこそ、そんな人たちが暮らす里山が美しいのだと、僕はつくづく思いました。
人の命を脅かす積雪や洪水、水不足。そんな自然の厳しさを力を合わせ、乗り越えながら、その恵みを共に分かち合って感謝する。祭りや共同作業の後には決まって宴会が開かれ、大人たちは笑い合いながら酒を酌み交わします。肴になるのは山で採れたイノシシの肉を焼いたものや里芋などの畑での収穫物。そんなごちそう目当てに子どもたちも宴会に加わり、にぎやかな会場はさながら正月を迎えた大所帯の家族の集まりのようです。
少子高齢化や過疎化で人が減っていく中、今も村の年配の人たちは山の暮らしを大切にしています。その暮らしを引き継ぐため、若者や子供たちも年配者に稲刈り機の使い方を教わったり、米の乾燥作業を共に行うなどして、各々が必死にその営みに参加しています。その思いはどこから生まれるのか、尋ねたことがあります。
ある30代の若者は「うちのお母さんが集落の人に農作業とか家のこととかで本当にお世話になった。今度は僕がお返しせんといかん。ふるさとも好きやしね」と答えてくれました。その言葉を補足するように、ある農家の年配の女性は言います。
「大人たちが集まって楽しそうにしている姿を見て育っているからね。あれが子供たちにとっては「ふるさとの幸せな暮らし」
だからふるさとを、この里山の三瀬村を大切に引き継いでいきたいと思っているんだろうね」
受け継がれてきた“美しさ”。それを大切にし、今を生きる三瀬村の人々と出会えたことは、僕の人生にとって大きな財産です。
---------------------
2023年1月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
それは「三瀬ってどんなところ?」と尋ねられた時、浮かんできた言葉でした。でもそのまま口にしても、うまく伝わらないし、その理由を語ろうとすると長くなるので、僕はいつも「自然豊かで空気も食べ物もおいしい村だよ」と答えてしまっていました。今回は、そんな“美しい里山”について話です。
最初にそう感じたのは、取材を始めたばかりだった六年近く前の秋。取材の為、稲刈りを行う初老の男性に出会った時でした。日に焼けた男性の浅黒い肌には力強さが漲り、節くれだった手には内に身に秘めている苦労がにじみ出ていました。しかし、その男性は苦労などは一切、語らず、朗らかに「今年もよう実った。豊作よ」と言って笑いました。その背後にはまだ狩り残してある黄金の海が広がっていて、時折拭く秋風に身重の穂を大きく揺らしていました。
その光景に僕は、この実りの為に男性が掛けてきた苦労と時間、そしてそんな人々の営みの連続が里山を作り上げてきたことを想像し、それがそのまま人と山との関わりの歴史であることにも気づいて、三瀬村を“美しい里山”だと思ったのでした。
その印象は長年の取材の中で、今も確かに息づく人の営みの姿としてより具体的に像を結んでいくようになっていきました。
例えば冬。三瀬村は平野部とは全く違う様相を呈します。脊振山系の裾野に広がる標高400~500ほどの村のあちこちには雪が降り積もり、木々などで少しでも陰ったところはなかなか溶けることがありません。
佐賀駅周辺では見たこともないような、大きなつららが家の軒先に伸びている光景を僕は何度も目にしてきました。村の土木建築会社の人たちは冬場、天気予報を小まめにチェックしながら、困っている人たちがいないか村のあちこちを見回ります。雪の予報の出ている時には道路凍結防止の薬を散布したり、積雪後、塞がれてしまった生活道路の除雪をしたりするのです。この冬の厳しさへの対策は農家でも行われます。
ある女性の家では、氷点下の気候から収穫した里芋を守る為、畑に穴を掘って石灰をまき、その中に里芋を入れて藁で蓋をして土などを被せます。こうすることで冬場、里芋を貯蔵することが出来るのだそうです。今はほとんど行われていませんが、一昔前は、冬場は炭焼きが行われ、山のあちこちから煙が上がっていたのだそうです。
冬はそればかりではありません。年末に向けて行われる、収穫した稲わらを使ったしめ縄作り。田んぼで採れたもち米を使った餅つきに、畑で採れた蕎麦を粉にして農家自らが打ち、親戚や親類に配る年越しの傍作り。新年になれば、子どもたちが集落の家々を回り、無病息災を祈る七福神や櫓を汲んで火を炊くホンゲンギョウなどの行事も行われます。恐らく、僕が知らないだけで冬場に行われる大小さまざまな行事はまだたくさん、あるのだと思います。
こういった山に暮らす人々の営みは春から秋にかけても続いていきます。水路に水を引くための井手区役や水の恵みに感謝する川祭りと田植え。日照りで水が足りない年には、川の上流に田を持つ人がわざと米を作らず、下流の人の田の為にに水を流すといった光景も見られました。
初夏にはブルーベリー園も開園。さらに真夏になれば村の若者が夏祭りを開き、やがて運動会や村の産品を販売し、都市部の人と交流するふれあい祭りなども開催されます。稲刈りが終わるとそれぞれの集落の神社では、五穀豊穣を感謝する神社のお祭りが行われます。山の営みはそれだけではありません。暮らしを守る為、地域の消防団は山からの川の堰から水を取り、消火を行う訓練が定期的に行われています。
賑やかでひたむきな人々の山の営み。高台に上ると山と人とが紡いできた、その里山の光景を前にすると、僕はこの土地に暮らす人たちの生きざまにただただ頭を垂れる思いを抱くようになりました。そして昔、何かの本で読んだ「人間は自然界では一つの動物である。山でその生を営むことは、それそのものが奇跡であることを知らねばならない」という言葉を思い出したのです。恐らく、三瀬村の人たちが見ている世界は、町中に暮らす僕が見ているものよりもずっと広くて深いのです。
集落に子どもが生まれると、皆が祝いの言葉をささげ、子ど達は野山や川に親しんで遊ぶ。青年たちは勤めに出ながらも、集落の生活道路に伸びてくる山の草木を刈るために共同の草刈りに参加するし、集落ごとに地域の営みを守り、引き継いできた年配者へ感謝を伝える為の敬老会が開かれる。村の誰かが亡くなれば、皆で弔いながら葬儀も協力して行う。村の人たちは命というものの、かけがえのない大切さを日々の営みの中で常に感じながら、だからこそ今を懸命に生きている、だからこそ、そんな人たちが暮らす里山が美しいのだと、僕はつくづく思いました。
人の命を脅かす積雪や洪水、水不足。そんな自然の厳しさを力を合わせ、乗り越えながら、その恵みを共に分かち合って感謝する。祭りや共同作業の後には決まって宴会が開かれ、大人たちは笑い合いながら酒を酌み交わします。肴になるのは山で採れたイノシシの肉を焼いたものや里芋などの畑での収穫物。そんなごちそう目当てに子どもたちも宴会に加わり、にぎやかな会場はさながら正月を迎えた大所帯の家族の集まりのようです。
少子高齢化や過疎化で人が減っていく中、今も村の年配の人たちは山の暮らしを大切にしています。その暮らしを引き継ぐため、若者や子供たちも年配者に稲刈り機の使い方を教わったり、米の乾燥作業を共に行うなどして、各々が必死にその営みに参加しています。その思いはどこから生まれるのか、尋ねたことがあります。
ある30代の若者は「うちのお母さんが集落の人に農作業とか家のこととかで本当にお世話になった。今度は僕がお返しせんといかん。ふるさとも好きやしね」と答えてくれました。その言葉を補足するように、ある農家の年配の女性は言います。
「大人たちが集まって楽しそうにしている姿を見て育っているからね。あれが子供たちにとっては「ふるさとの幸せな暮らし」
だからふるさとを、この里山の三瀬村を大切に引き継いでいきたいと思っているんだろうね」
受け継がれてきた“美しさ”。それを大切にし、今を生きる三瀬村の人々と出会えたことは、僕の人生にとって大きな財産です。
---------------------
2023年1月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
Posted by みつせファン
at 12:00
│樋口浩一