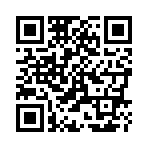2021年09月01日
稲穂が教えてくれるもの
八月下旬、三瀬村の田んぼでは鈴虫の声が響いていました。
合唱にあわせ、頭を揺らす稲穂は黄金に色づき、収穫間近。毎年、三瀬村の稲刈りは平野部より一月早く始まります。稲穂が広がる里山の風景は私にとって、三瀬村の象徴的な風景です。
この季節、村の人たちは稲刈りを手分けして行います。大型の稲刈り機を共同で所有し、みなで話し合って地域全体の田んぼを回る計画を立てるのです。
そもそも村の米作りは、共同作業によって始まります。
春、名残を残す寒さに凍えながら人々は川から田んぼに水を引く為の水路を掃除する井手(いで)(※1)区役(くやく)(※2)に取り掛かります。それから日に日に上達していくウグイスの声色を楽しみながら田植えを行い、夏になると、草いきれの中、雑草を切ります。秋になると熟れた稲穂で大きくしなる稲を刈るのです。
そして秋が深まると、人々は収穫できた稲穂を神饌(しんせん)として、神社で秋祭りを行ないます。恵みの有り難さと苦労を仲間たちと分かち合い、神様に感謝するのです。
横のつながりによる村の米作りを支えてきたのは、長年、村で結ばれてきた縦のつながり。区役も秋祭りも村の人々が百年以上前から、自分たちが生きてきた土地を守るためのものとして先祖代々受け継いできた営みです。
三瀬村の標高およそ四百メートル。冬になると多くの道が通れなくなるほど雪が積もります。天候も変わりやすく、日照りや日照不足、水害などを被ることも少なくありません。さらに山の間近にあるため、獣の被害もあります。
近年では「せっかく育てた米が、イノシシにやられてほとんど全滅」なんて話も珍しくありません。私は四季を通して村の営みを見つめているうちに、たった一人ではどうにもならない厳しい自然の中、人々が助け合って生きてきたのだということを知りました。そして、その営みが文字通り、命をつなぐ営みなのだという、当たり前のことに今更ながら気付きました。
三瀬村で豊かだと思うことがあります。
村の人たちが何気なく口にする「バチの当たるけん ちゃんとしとかんといかん」や「神様の恵みよね 感謝せんと」という言葉です。その中には常に神様の存在があり、畏怖と畏敬の念が込められています。
私は、その精神が小さな村の社会の中で他者を受け入れ、敬うという人間同士のつながりの為、必要な心の姿勢を育んできたのではないかと思うようになりました。特に用事がなくても、村で出会えば、互いの体を気遣い、苦労を労い、今日元気で会えたことを喜び合う。過疎化や高齢化など、きれい事では済まない問題が多くある中、村の人たちは問題を素直に受け止め、謙虚に向き合いながら今も人とのつながりを大切にしています。私は、そんな村の人たちの懐の深さに豊かさを感じるのです。
厳しい暑さを乗り越え、今年も村の田んぼには黄金の穂がたわわに実っています。
コロナ禍で人々のつながりが薄れている今、私は三瀬村に広がる稲穂の風景を見ると励まされるような心地になります。それは村の人たちがつながりの中で培い、幾重にも積み重ねてきた先にある豊かさの象徴に映るからです。その一見すると当たり前の、しかし、尊い事実を忘れてはならないのだと思います。
※1井手(いで)とは水路の意味。
※2区役(くやく)とは地区の住民で行う共同作業のこと。
三瀬村 初秋の稲穂

春先の井手区役

初秋の稲穂の風景

2021年9月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com
合唱にあわせ、頭を揺らす稲穂は黄金に色づき、収穫間近。毎年、三瀬村の稲刈りは平野部より一月早く始まります。稲穂が広がる里山の風景は私にとって、三瀬村の象徴的な風景です。
この季節、村の人たちは稲刈りを手分けして行います。大型の稲刈り機を共同で所有し、みなで話し合って地域全体の田んぼを回る計画を立てるのです。
そもそも村の米作りは、共同作業によって始まります。
春、名残を残す寒さに凍えながら人々は川から田んぼに水を引く為の水路を掃除する井手(いで)(※1)区役(くやく)(※2)に取り掛かります。それから日に日に上達していくウグイスの声色を楽しみながら田植えを行い、夏になると、草いきれの中、雑草を切ります。秋になると熟れた稲穂で大きくしなる稲を刈るのです。
そして秋が深まると、人々は収穫できた稲穂を神饌(しんせん)として、神社で秋祭りを行ないます。恵みの有り難さと苦労を仲間たちと分かち合い、神様に感謝するのです。
横のつながりによる村の米作りを支えてきたのは、長年、村で結ばれてきた縦のつながり。区役も秋祭りも村の人々が百年以上前から、自分たちが生きてきた土地を守るためのものとして先祖代々受け継いできた営みです。
三瀬村の標高およそ四百メートル。冬になると多くの道が通れなくなるほど雪が積もります。天候も変わりやすく、日照りや日照不足、水害などを被ることも少なくありません。さらに山の間近にあるため、獣の被害もあります。
近年では「せっかく育てた米が、イノシシにやられてほとんど全滅」なんて話も珍しくありません。私は四季を通して村の営みを見つめているうちに、たった一人ではどうにもならない厳しい自然の中、人々が助け合って生きてきたのだということを知りました。そして、その営みが文字通り、命をつなぐ営みなのだという、当たり前のことに今更ながら気付きました。
三瀬村で豊かだと思うことがあります。
村の人たちが何気なく口にする「バチの当たるけん ちゃんとしとかんといかん」や「神様の恵みよね 感謝せんと」という言葉です。その中には常に神様の存在があり、畏怖と畏敬の念が込められています。
私は、その精神が小さな村の社会の中で他者を受け入れ、敬うという人間同士のつながりの為、必要な心の姿勢を育んできたのではないかと思うようになりました。特に用事がなくても、村で出会えば、互いの体を気遣い、苦労を労い、今日元気で会えたことを喜び合う。過疎化や高齢化など、きれい事では済まない問題が多くある中、村の人たちは問題を素直に受け止め、謙虚に向き合いながら今も人とのつながりを大切にしています。私は、そんな村の人たちの懐の深さに豊かさを感じるのです。
厳しい暑さを乗り越え、今年も村の田んぼには黄金の穂がたわわに実っています。
コロナ禍で人々のつながりが薄れている今、私は三瀬村に広がる稲穂の風景を見ると励まされるような心地になります。それは村の人たちがつながりの中で培い、幾重にも積み重ねてきた先にある豊かさの象徴に映るからです。その一見すると当たり前の、しかし、尊い事実を忘れてはならないのだと思います。
※1井手(いで)とは水路の意味。
※2区役(くやく)とは地区の住民で行う共同作業のこと。
三瀬村 初秋の稲穂

春先の井手区役

初秋の稲穂の風景

2021年9月1日
樋口浩一(映像ディレクター)
-------------------------------------
三瀬のおと(佐賀県三瀬村のコラムやエッセイ)
三瀬村・里山の恵み みつせファン https://mitsusefan.com